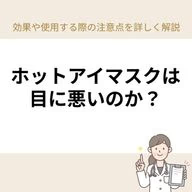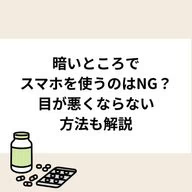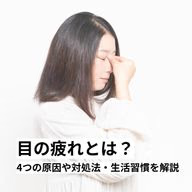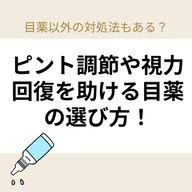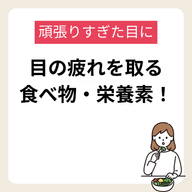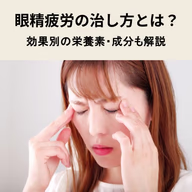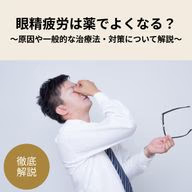2025-11-19
目の疲れを取る方法3選!スマホやパソコンと上手に付き合いクリアな毎日に
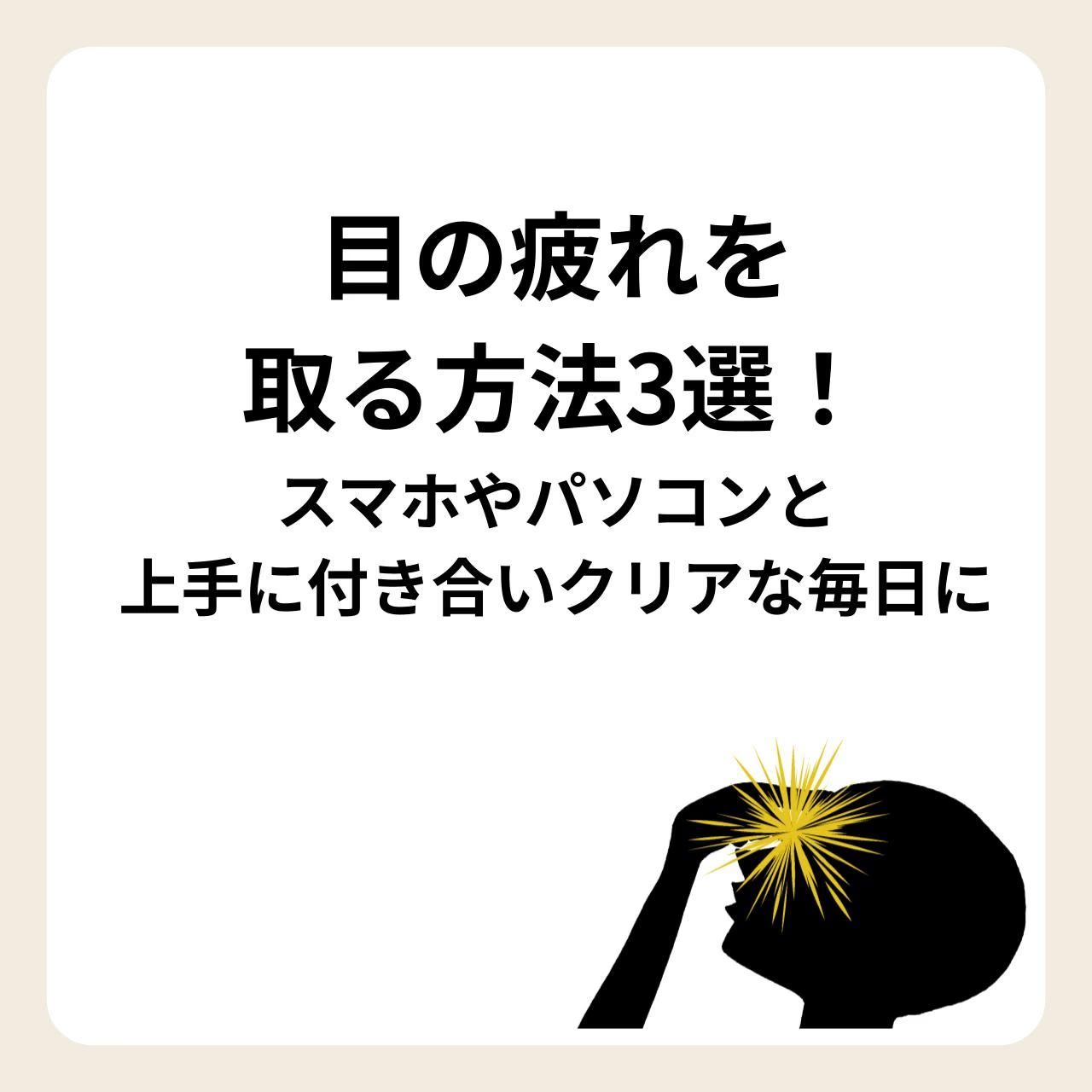
パソコン作業の後に目が乾く、スマホゲームをしていたら目がかすむといった症状を感じていたら、それは目の疲れかもしれません。
目の疲れは病名ではなく症状や状態を表すものですが、大したことはないと侮ると、悪化して目以外にも症状が出る可能性もあります。とはいえ、パソコンやスマホに触れる時間はなかなか減らせないという方も多いでしょう。
そこで、この記事では、すぐにできる目の疲れを取る方法を3つご紹介します。目の疲れの症状や原因、防ぐための対策もご紹介しますので、目の疲れが気になる方はぜひ参考にしてみてください。
この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長
福永 ひろ美

Webライター
木原かおる
- コスメ薬機法管理者
- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)
- 景品表示法・特定商取引法広告遵守個人認証(KTAA)
目の疲れを取る方法3選

今すぐにできる目の疲れを取る方法を3つご紹介します。
- 目を休ませる
- 温める、冷やす
- マッサージ
日常生活や仕事の合間でも簡単に取り入れられるものばかりなので、目の疲れを感じている場合は、まず実践してみましょう。
目を休ませる
道具も不要ですぐに行える最も簡単な方法として、目を休めることが挙げられます。具体的には、1分ほど目を閉じる、画面から目を離して遠く眺めることを行いましょう。
パソコンやスマホを使用する際は画面との距離が近くなります。近くにピントを合わせる際には目の毛様体筋が緊張しますが、画面を見続けていると、毛様体筋も緊張しっぱなしとなり、これが目の疲れの原因になるのです。
アメリカの眼科医会は「20-20-20ルール」を提唱しています。20分に1回、20秒間、20フィート(約6m)離れたところを見るというもので、目を休めるタイミングの具体的な目安として意識するとよいでしょう。
目を閉じたり、遠くを眺めたりすることで、毛様体筋の緊張が緩み、リラックスできます。また、同時に疲れ目を訴求した目薬を使うのもよいでしょう。画面から目を離して作業を中断することは、頭のリフレッシュにもなるので一石二鳥の方法です。
温める、冷やす
目を温めることも、目の疲れを取るのに役立つ方法です。温めることで血行が良くなり、毛様体筋の緊張を緩め、目をリラックスできます。最近は開封すると温かくなる個包装タイプのアイマスクがあるので、デスクやカバンに常備しておきましょう。
水に濡らしたタオルを絞って、600Wの電子レンジで約40秒加熱した蒸しタオルを使うのもおすすめです。お風呂に入ったついでに、お湯で濡らしたタオルを固く絞って使うのもよいでしょう。
目の疲れがひどく、充血や痛みがある場合は、冷やすのがおすすめです。冷たい水で濡らしたタオルを目元にのせれば、目の疲れを取るだけでなく、冷たい刺激で気分転換にもつながります。
マッサージ
目の周りをマッサージすることも目の疲れを取る方法の1つです。目の周りにはたくさんのツボがあると言われているので、指の腹でやさしく押しましょう。目の周りの代表的なツボは以下の通りです。
- 攅竹(さんちく):眉頭の下にある骨のきわのへこんだ部分
- 太陽(たいよう):眉尻と目尻の中間から少し外側のくぼみ
- 睛明(せいめい):目頭の少し内側のくぼみ
マッサージをすることで、目の周りの筋肉をほぐすことにもつながります。画面から目を離して休めるときに、マッサージを組み合わせるのもおすすめの方法です。
目の疲れはどんな症状?

パソコンやスマホを使っていて、目に違和感があるけれど、目の疲れなのか分からない方もいるでしょう。日本眼科医会は感じ方に個人差はあると前置きしつつも、以下を目の疲れの症状として挙げています。
- 目が重い
- 目が痛い
- 目がショボショボする
- 目がかすむ
- 目が乾いた感じがする
- まぶたがピクピクする
- まばたきが多くなる
スマホやパソコンを多用していて、上記の症状を感じているのであれば、目の疲れを生じている可能性が高いでしょう。今すぐできる目の疲れを取る方法を実践するのがおすすめです。
目の疲れの原因と対策

目の疲れを取る方法や症状について紹介してきましたが、前もって目の疲れを防ぐ対策を取り入れることがベストです。ここでは、目の疲れの主な原因と、原因に応じた対策をご紹介します。
度が合わない眼鏡の使用
目の疲れの原因として最も多いのが、合わない眼鏡をかけていることや細かい文字が見づらいのに我慢していることです。視力が良かった人が、老眼になって生じるケースもあります。ピントを合わせるために、毛様体筋に余計な負担がかかるので、目が疲れてしまうでしょう。
普段使いしているコンタクトレンズや眼鏡が、遠くを見るのにはいいが、近くを見るのには合っていないというケースも。また、眼鏡の場合はレンズの度数だけでなく、フレームが合っておらず、痛くなったり、ズレたりして、目の疲れにつながることもあります。
視力は年齢とともに変化することもあるため、定期的に視力検査を受け、度数やフレームが合った眼鏡・コンタクトレンズを使用しましょう。
ドライアイ
目の疲れのもう1つの大きな原因がドライアイです。文字通り、目の乾きを感じる他、ゴロゴロする、目が開けにくいと言った症状を感じることもあります。目が乾くと不快感だけでなく、見えにくさや疲れにもつながるのです。
対策としては、まず室内の湿度に注意しましょう。特に、冬に暖房が効いた部屋は快適ですが、乾燥しやすくなることがあります。加湿器を設置するなどして、程よい湿度を維持しましょう。
また、目薬の活用もおすすめです。市販品でも目の乾きを訴求した目薬が販売されています。よりしっかりと対策するのであれば、眼科で診察を受けて、医療用医薬品の目薬を処方してもらうのもおすすめです。
さらに、画面を見続けていると、どうしてもまばたきの回数が減ってしまいます。意識的にまばたきの回数を増やすことも、ドライアイによる目の疲れを防ぐ方法の1つです。
画面と目の距離
画面と目の距離が適切でない場合も、目の疲れにつながってしまいます。適切な距離を保って作業できるように、パソコンの画面の位置や角度を調節しましょう。
参考となるのが、厚生労働省がパソコンなどを使う仕事における労働衛生管理の一環として出している「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」です。ガイドラインの中では、ディスプレイは目から40cm以上離すことを推奨しています。
また、画面を見上げるような角度も目が疲れる原因となります。ディスプレイは、画面の上端が目の高さとほぼ同じか、やや下になる高さになるように設置しましょう。
椅子を調整して、姿勢を意識することも大切です。椅子に深く腰掛けて、ひざは90度以上にすることで、作業負担の軽減が期待できます。
目の健康に役立つ栄養の不足
食生活も重要なポイントです。栄養が偏ったり、不足したりしている場合は、眼精疲労を含め、体のさまざまな部位に不調を及ぼします。目の健康を意識するのであれば、特にビタミンAの摂取を重視しましょう。ビタミンAは夜間の視力の維持を助けるなど、目の機能を正常に保つために欠かせません。ニンジンや小松菜などの緑黄色野菜、レバーなどを積極的にとりましょう。
他にも、ルテインやアスタキサンチンのようなカロテノイド、アントシアニンも目を使う人がとりたい成分です。健康維持の基本となるビタミンCやビタミンE、亜鉛などのミネラルも欠かせません。
普段の食事でバランス良く栄養をとれるのがベストですが、難しい場合はサプリメントを活用しましょう。普段の食事で十分ではない栄養を補えるようなサプリメントを組み合わせるのがおすすめです。
原因不明の場合は医師に相談
目の疲れを取る方法を取り入れても楽にならない、あてはまる原因がないのに目の疲れのような症状が出ているといった場合は、眼科を受診しましょう。
目の疲れが悪化しすぎていると、セルフケアだけでは変化がない場合もあります。また、思い当たる原因がない場合は、もっと深刻な目の病気が隠れていることも。白内障、緑内障、加齢黄斑変性、糖尿病網膜症によって、目の疲れが引き起こされることもあるので要注意です。気になる症状がある場合は、早めに眼科を受診しましょう。
目の疲れを放置すると目以外にも悪影響

一時的に目が疲れても、目を休めたり、十分に眠ったりすれば、すっきりすることが多いです。しかし、休息や睡眠を取っても、目の疲れが解消しない場合は「眼精疲労」に移行している可能性があり、注意が必要です。
眼精疲労は、目の疲れが全身に及んだ状態を指します。首や肩のこり、頭痛といった身体的な症状の他、イライラ感などの精神的な症状が出るケースも。
眼精疲労には治療法や治療薬はないので、原因を特定して、取り除くことが対処方法となります。原因が特定できない場合は、眼科に相談しましょう。医療用医薬品の目薬が処方されることもあります。
画面をよく見る人に欠かせない栄養素が詰まったサプリメント「Eyepa」

パソコンやスマホをよく使う方に欠かせない成分を詰め込んだサプリメント「Eyepa」をおすすめします。夜間の視力の維持や皮膚や粘膜の健康維持を助けるビタミンAを配合。さらに、注目成分のルテインだけでなく、ゼアキサンチンも含んだマリーゴールド色素を配合しています。
アントシアニンを含むビルベリー、カロテノイドの一種であるアスタキサンチン、健康にも欠かせないビタミンCやビタミンE、亜鉛などを凝縮した、画面を見る人にぴったりのオールインワンサプリです。
香料、酸味料、着色料、保存料、甘味料、増粘安定剤の6つの添加物不使用で、国内のGMPに準拠した工場で打錠されており、品質面にもしっかりと気を配っています。
定期購入は約1カ月分を初回43%オフで購入できるので、自分に合うかをじっくり試してみたい方にもおすすめです。2回目以降も29%オフで購入できるので、コツコツと続けられます。縛りやキャンセル料もなく、送料無料で15日間の返金保証もあるので、まずは気軽に試してみましょう。
目の疲れを取る方法を取り入れてクリアな毎日に

すぐにできる目の疲れを取る方法、目の疲れの症状や原因、防ぐための対策をご紹介しました。目の疲れは、病名ではなく、目の症状を指す言葉であり、休息や睡眠を十分に取れば翌日まで残ることは少ないです。しかし、翌日に残ったり、体にも症状が出たりしている場合は、眼精疲労になっている可能性があるので、よりしっかりとしたケアを行いましょう。
目の疲れを取る方法も目の疲れを防ぐ方法も、それほど難しくはなく、すぐに行えるものがほとんどです。積極的に取り入れて、すっきりとしたクリアな毎日につなげていきましょう。
この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長
福永 ひろ美
【ひとみケアサプリEyepa監修・眼科医】 日々の生活の中で、バランスよく必要な栄養素を摂取することも大切なのです。Eyepaは眼の潤いをサポートしてくれるビルベリーを始め、抗酸化成分であるルテインやアスタキサンチン、その他多様な成分がオールインワンに含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。

Webライター
木原かおる
- コスメ薬機法管理者
- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)
- 景品表示法・特定商取引法広告遵守個人認証(KTAA)
国内化粧品メーカー、外資系消費財メーカーで、品質管理や薬機法業務に約15年従事した後にフリーライターに。薬機法や成分関連の知識をいかして、コスメやサプリのライティング、校正、記事監修などを手がける。
あなたへのおすすめ
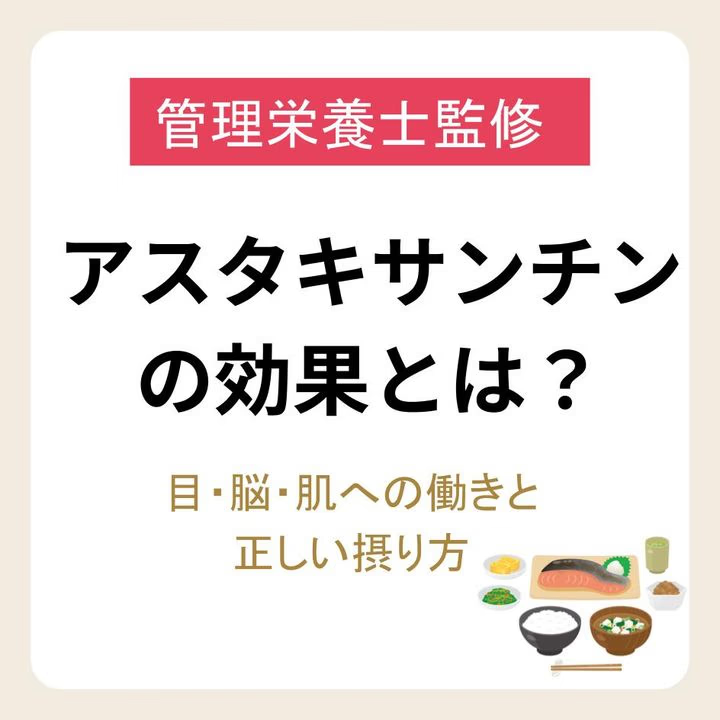
眼の健康
【管理栄養士監修】アスタキサンチンの効果とは?目・脳・肌への働きと正しい摂り方
「アスタキサンチンって、本当に目の疲れに効くの?」「アスタキサンチンが多い食べ物を...
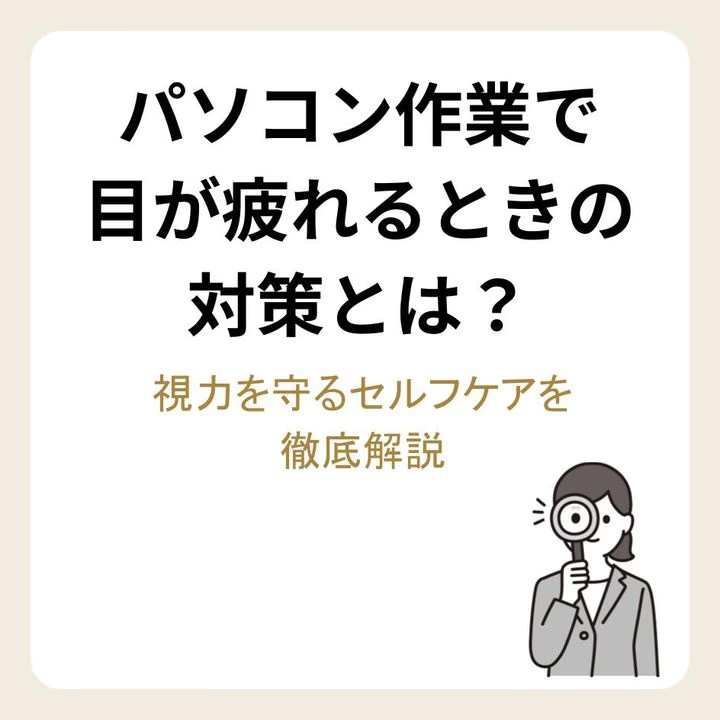
眼の健康
パソコン作業で目が疲れるときの対策とは?視力を守るセルフケアを徹底解説
「以前は一日中モニターを見ていても平気だったのに、最近は夕方になると目がしょぼしょ...
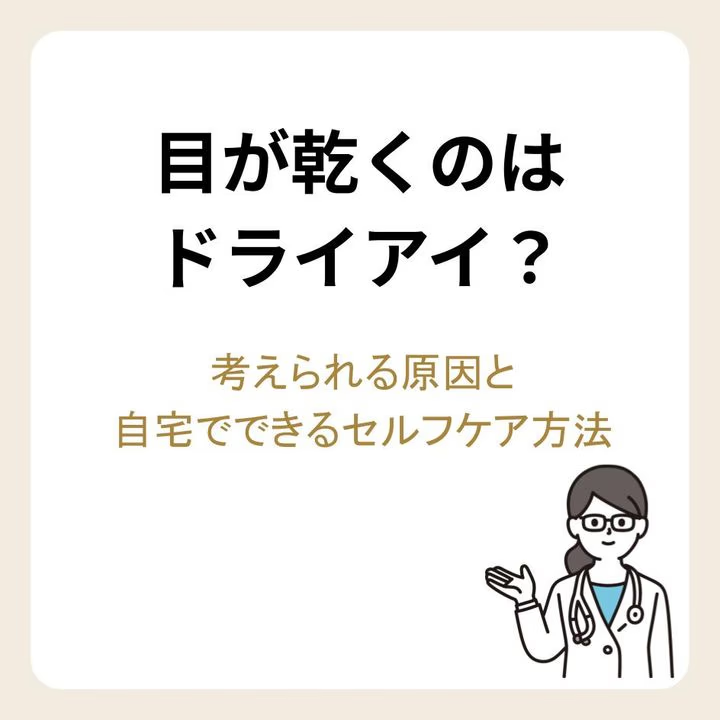
眼の健康
目が乾くのはドライアイ?考えられる原因と自宅でできるセルフケア方法
「最近、夕方になると目がショボショボして、目が乾く感覚がつらい」「ドライアイかもし...