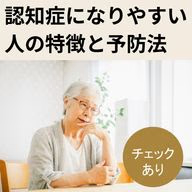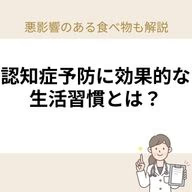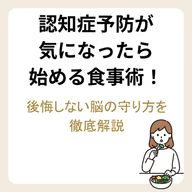2025-11-19
認知症と睡眠の関係とは?生活習慣を見直すための必須知識を徹底解説
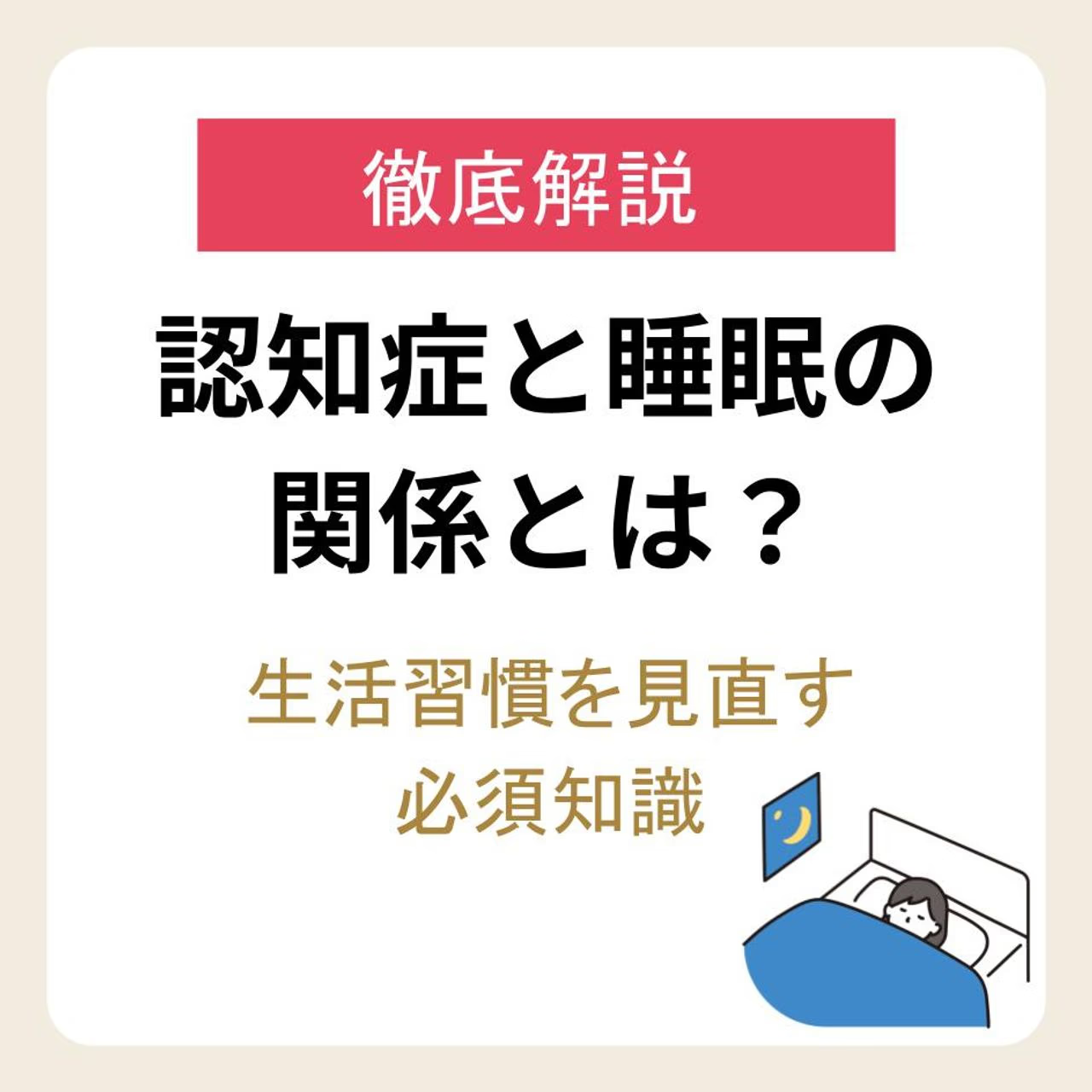
「最近、どうも寝つきが悪くて、夜中に何度も目が覚めてしまう……」
「若い頃より物忘れが増えた気がする。もしかして、認知症の始まりなのかな?」
このようなお悩みを抱えていませんか?忙しい毎日を送るなか、ふとした瞬間に感じる心身の変化に、大きな不安を覚えてしまうこともあるでしょう。
特に「睡眠の質の低下」と「物忘れ」は、多くの方が経験する悩みですが、実はこの2つ、無関係ではありません。質の良い睡眠は、私たちの脳の健康を守るうえで、とても大切な役割を担っているのです。
本記事では、認知症と睡眠の深い関係性から、加齢によって眠りが浅くなる原因、そして今日から実践できる睡眠の質を高める具体的な方法まで、網羅的に解説します。
最後まで読むことで、睡眠に関する正しい知識が身につき、認知症予防に向けた最初の一歩を踏み出すことができるでしょう。
目次
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授

Webライター
神屋ヒロキ
認知症と睡眠の深い関係

質の高い睡眠がとれていない状態は、将来の認知症発症リスクと関係があるといわれています。
特に、認知症の中でも最も多くの割合を占める「アルツハイマー型認知症」は、睡眠との関連性が指摘されているのです。
Check
脳の老廃物の排出メカニズム
私たちの脳内では、日中の活動によってアルツハイマー型認知症を引き起こす原因の一つと考えられている「アミロイドβ」というたんぱく質が作られます。
健康な脳では、このアミロイドβは睡眠中に脳の外へと排出されます。特に、ぐっすりと深い眠りである「ノンレム睡眠」の間に、このお掃除タイムが活発になることがわかっています。
つまり、睡眠不足が続いたり、眠りが浅くてノンレム睡眠の時間が短くなったりすると、アミロイドβがうまく排出されずに脳内に溜め込まれ、認知症のリスクを高めてしまう可能性があるのです。
だからといって、ただ長く眠れば良いというわけでもありません。最適な睡眠時間は人それぞれ。大切なのは、時間だけでなく「睡眠の質」を高め、脳をしっかり休ませてあげることです。
加齢とともに眠りが浅くなる主な原因
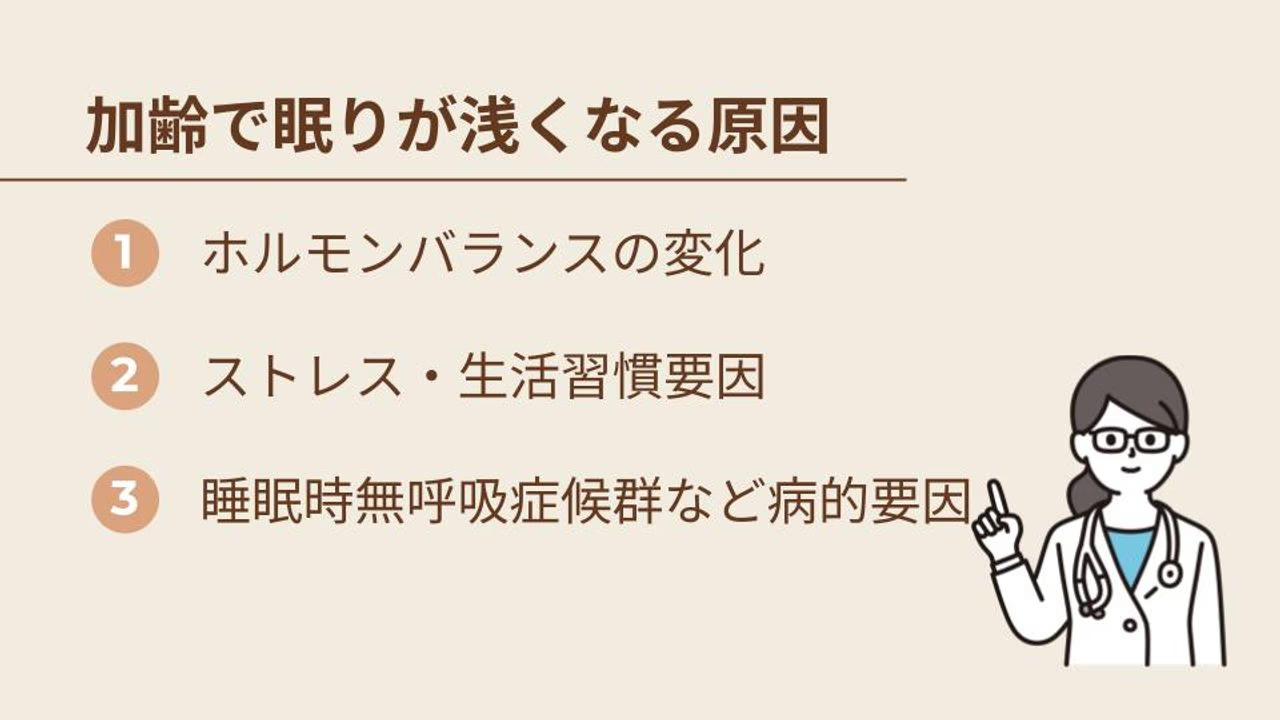
「若い頃はどこでもぐっすり眠れたのに……」と感じる方は多いのではないでしょうか。
年齢を重ねるとともに睡眠の質が変化するのは、ある意味で自然なことです。しかし、その背景には、単なる老化現象だけではない、さまざまな原因が隠されています。
放置してしまうと、認知症のリスクにもつながりかねない睡眠の問題。まずは、なぜ眠りが浅くなってしまうのか、その主な原因を知ることから始めましょう。
ホルモンバランスの変化

加齢によるホルモンバランスの変化は、睡眠の質に影響を与える大きな要因の一つです。
特に女性の場合、一生を通じて女性ホルモンの分泌量が変動するため、年代ごとに特有の睡眠の悩みを抱えやすいといえます。
例えば、月経周期。排卵後から月経前にかけては、眠気を誘う「プロゲステロン」というホルモンの分泌が増えるため、日中に強い眠気を感じることがあります。一方で、この時期は基礎体温が上がるため、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりする人も少なくありません。
さらに、50代前後の更年期になると、女性ホルモンである「エストロゲン」の分泌が急激に減少します。エストロゲンは自律神経の働きを安定させる役割も担っているため、この減少が自律神経の乱れを引き起こし、ほてりや発汗、気分の落ち込みといった不調とともに、不眠の症状が現れやすくなるのです。
このように、ホルモンの波は自分ではコントロールしづらいものですが、体の仕組みを理解しておくことは、適切な対策を考える第一歩になります。
ストレス・生活習慣要因

疲れているはずなのに、布団に入ると目が冴えてしまって眠れない。そんな経験はありませんか?その原因は、もしかしたら日々のストレスにあるかもしれません。
私たちの体には、「自律神経」という体の機能を自動でコントロールしてくれる神経があります。
自律神経には、心身を活動モードにする「交感神経」と、リラックスモードにする「副交感神経」の2種類があり、日中は交感神経が、夜になると副交感神経が優位になることで、自然な眠りへと誘われます。
しかし、仕事のプレッシャーや人間関係の悩みなど、強いストレスにさらされ続けると、この切り替えがうまくいかなくなってしまうのです。夜になっても交感神経が優位なままだと、心も体も興奮状態が続き、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。
さらに、睡眠不足はストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌バランスを乱し、日中のストレスをより感じやすくさせてしまうという悪循環に陥ることも。
ストレスを溜め込まず、質の良い睡眠を確保する生活習慣が大切です。
睡眠時無呼吸症候群など病的要因

十分な時間をとって寝ているはずなのに、日中に耐えがたい眠気に襲われたり、朝起きてもスッキリしなかったりする場合、何らかの病気が隠れている可能性も考えなくてはなりません。
その代表的なものが「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」です。
Check
睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは
眠っている間に呼吸が何度も止まったり、浅くなったりする病気。最も多い「閉塞性」というタイプは、加齢などでのどの筋肉が緩み、空気の通り道である気道が狭くなることで起こるとされています。
呼吸が止まると体内の酸素が不足するため、脳は危険を察知して目を覚まさせ、呼吸を再開させようとします。この小さな覚醒が一晩に何度も繰り返されるため、本人は気づかなくても、脳や体は全く休めていない状態に。
結果として、深刻な睡眠不足に陥り、日中のパフォーマンスが低下するだけでなく、認知症のリスクを高めることも指摘されています。
大きないびきや、ご家族から睡眠中の無呼吸を指摘されたことがある方は、一度専門の医療機関に相談してみることをおすすめします。
認知症予防に役立つ睡眠改善法
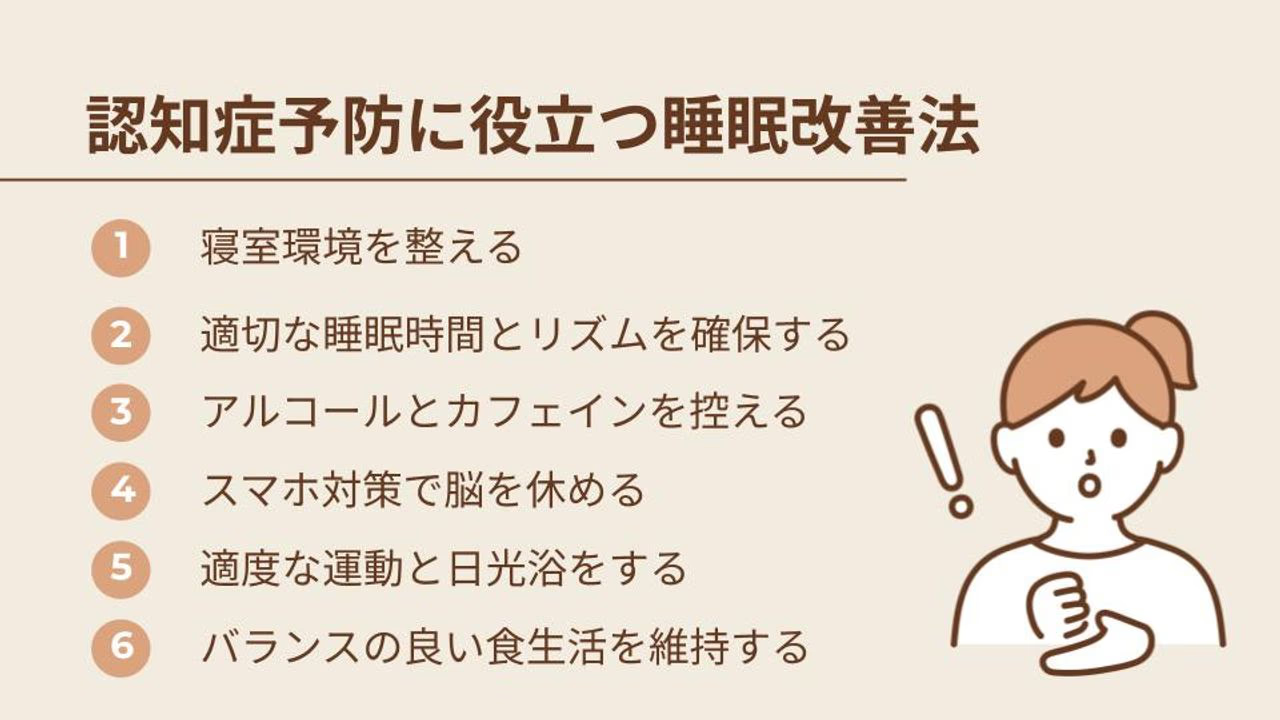
認知症と睡眠の深い関係や、眠りが浅くなる原因について理解が深まったところで、ここからは具体的な改善策について見ていきましょう。
「なんだか難しそう……」と感じるかもしれませんが、特別なことばかりではありません。日々の生活習慣を少し見直すだけで、睡眠の質は大きく変わる可能性があります。
あなたの快眠と脳の健康を守るための、具体的なヒントをご紹介します。
寝室環境を整える

質の高い睡眠を得るためには、寝室が心からリラックスできる「安全基地」であることが大切です。毎日当たり前のように使っている寝室ですが、一度その環境を見直してみませんか?
快適な睡眠のために、ぜひチェックしてほしいポイントが3つあります。
温度と湿度
私たちは体温が少し下がることで、自然な眠りに入りやすくなります。スムーズな入眠のためには、室温を夏場は26℃前後、冬場は16~19℃程度に保つのがおすすめです。
また、湿度は年間を通して50~60%が快適とされています。まずは寝室に温湿度計を置いて、現状を把握することから始めてみましょう。
空気(換気)
意外と見落としがちなのが、寝室の換気です。窓を閉め切ったままだと、呼吸によって二酸化炭素濃度が上がり、睡眠の質を下げてしまうことがあります。
朝起きた時や、就寝前に少し窓を開けて空気を入れ替える習慣をつけましょう。
ホコリ
日中の活動で舞い上がったホコリは、夜間に床から30cmほどの高さに滞留するといわれています。もし床に布団を敷いて寝ている場合、知らず知らずのうちにホコリを吸い込んでいるかもしれません。
これを機に、高さのあるベッドに変えてみるのも一つの有効な対策です。
適切な睡眠時間とリズムを確保する

質の高い睡眠のためには、「時間」と「リズム」の両方を整えることが重要です。
よく「8時間睡眠が良い」などといわれますが、必要な睡眠時間は年齢や体質によって異なり、一概に何時間がベストとはいえません。大切なのは、日中に眠気で困ることなく、元気に活動できる自分なりの睡眠時間を確保することです。
そして、それ以上に意識してほしいのが「睡眠のリズム」を整えること。
私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計」が備わっています。この体内時計を整える最も効果的な方法が、「毎朝同じ時間に起きる」ことです。
休日だからといって昼過ぎまで寝てしまうと、体内時計が乱れ、夜の寝つきが悪くなる原因に。たとえ寝る時間が遅くなった日でも、起きる時間はなるべく一定に保つよう心がけてみましょう。
アルコールとカフェインを控える

「寝る前にお酒を飲むとよく眠れる」と感じている方、実は注意が必要です。
アルコールにはリラックス作用があるため、一時的に寝つきを良くしてくれるのは事実です。しかし、アルコールが体内で分解される過程で生まれる「アセトアルデヒド」という物質には覚醒作用があります。
このため、飲み始めて数時間後には眠りが浅くなり、夜中に目が覚める原因になってしまうのです。質の良い睡眠と認知症予防を考えるなら、就寝直前の飲酒は避けるのが賢明です。
また、コーヒーや緑茶、栄養ドリンクなどに含まれるカフェインにも強い覚醒作用があります。カフェインの効果は3~4時間ほど続くといわれているため、夕方以降の摂取は控えたほうがよいでしょう。
寝る前の水分補給には、ノンカフェインである麦茶やルイボスティー、リラックス効果が期待できるハーブティーなどがおすすめです。
スマホ対策で脳を休める

スマホやタブレットなどの電子機器が放つ「ブルーライト」は、太陽の光に近い性質を持っています。夜にこの光を浴びてしまうと、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、眠りを促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制してしまいます。
その結果、脳が覚醒モードになってしまい、寝つきが悪くなったり、睡眠の質が低下したりするのです。
また、SNSのタイムラインやネットニュース、動画など、次から次へと流れてくる情報は、知らず知らずのうちに脳を興奮させてしまいます。リラックスすべき時間に脳を刺激し続けることは、質の高い睡眠の妨げになるのです。
質の良い睡眠のためにも、脳をしっかり休ませる時間を意識的に作りましょう。具体的には、以下のようなルールを決めるのがおすすめです。
- 1就寝1時間前になったらスマホを見ない
- 2どうしても触ってしまう方は、寝室とは別の部屋で充電する
- 3枕元にスマホを置かない
スマホとの上手な距離感が、深い眠りへの近道になります。
適度な運動と日光浴をする

日中にウォーキングや軽いジョギング、ストレッチなどの適度な運動を行うと、心地よい疲労感が得られ、夜の寝つきがスムーズになります。運動はストレス解消にもつながるため、精神的な理由で眠りが浅くなっている方にもおすすめです。
ただし、寝る直前に激しい運動をすると、逆に交感神経が活発になり目が冴えてしまうので、運動は就寝の2~3時間前までに終えるのが理想的です。
そしてもう一つ、ぜひ意識してほしいのが「日光浴」。特に午前中に太陽の光を浴びると、乱れがちな体内時計がリセットされます。体内時計が整うと、夜になるにつれて自然な眠りを誘うホルモン「メラトニン」が分泌されやすくなるのです。
特別な運動をする時間がなくても、例えば一駅手前で降りて歩いてみたり、日当たりの良い窓際で少し過ごしたりするだけでも効果が期待できます。
バランスの良い食生活を維持する

「睡眠」と「食事」、一見すると別々のものに思えるかもしれませんが、実はこの2つは密接に関係しています。
特に、年齢を重ねるにつれて栄養状態が睡眠の質に与える影響は大きくなり、「低栄養の状態が睡眠を悪化させる」という報告もあるほどです。
例えば、食事の量が減ったり、同じようなものばかり食べていたりすると、体に必要な栄養素が不足しがちになります。すると、体のさまざまな機能がうまく働かなくなり、結果として寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりすることがあるのです。
質の高い睡眠のためには、特定の栄養素だけを摂るのではなく、さまざまな食材からバランス良く栄養を摂ることが基本となります。
肉、魚、大豆製品からたんぱく質を、野菜やきのこ、海藻類からビタミンやミネラル、食物繊維を、といったように、彩り豊かな食卓を意識することが大切です。
三度の食事をしっかり摂り、体の中から健康を整えることが、質の良い睡眠への土台作りにつながります。
食事で確保しきれない栄養素はオールインワンサプリ「Rimenba」で!

バランスの良い食事が大切だとわかっていても、毎日完璧な食事を用意するのはなかなか難しいものですよね。特に忙しい毎日を送っていると、どうしても栄養が偏りがちになってしまうこともあるでしょう。
そんな時に頼りになるのが、食事だけでは補いきれない栄養素を手軽にサポートしてくれるサプリです。
「Rimenba(リメンバ)」は、まさにそんな現代人の悩みに寄り添うために開発されたオールインワンサプリ。日々の食事のベースを整えながら、プラスアルファの栄養素をしっかりと補給することで、体の内側から健やかな毎日をサポートします。

睡眠の質を高める土台となる体作りはもちろん、その先にある「知力健康」を見据えた栄養補給の選択肢として、あなたの心強い味方になってくれるはずです。
興味をお持ちになった方は、ぜひ下記のバナーから公式サイトを参照してみてください。
認知症リスクを下げるその他の日常習慣
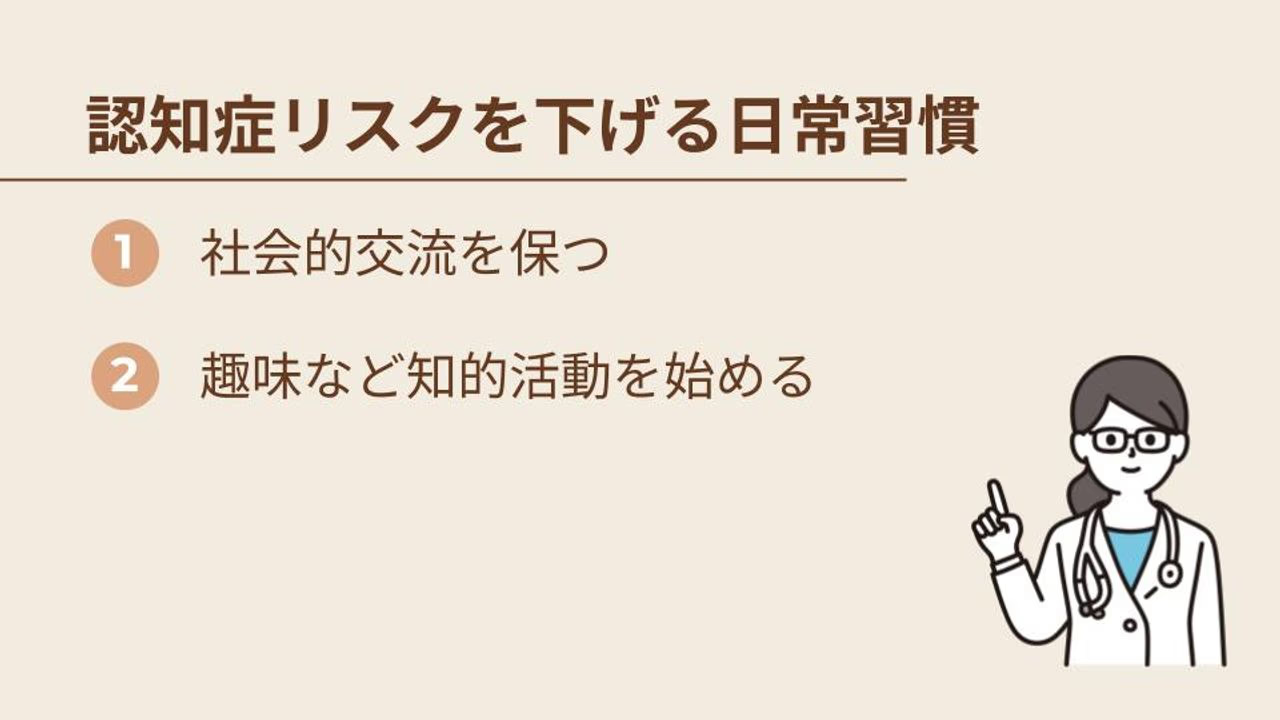
ここまで、認知症予防の鍵となる「睡眠」に焦点を当てて解説してきましたが、脳の健康を維持するためには、睡眠以外の生活習慣も同じように大切です。
質の高い睡眠を土台としながら、これからご紹介するような習慣を日々の暮らしに取り入れることで、より多角的に認知症のリスクにアプローチできます。
いきいきとした毎日を送るためにも、ぜひ参考にしてみてください。
社会的交流を保つ

定年退職や子どもの独立などを機に、人との交流が減ってしまうことがあります。
しかし、社会とのつながりが少なくなることは、認知症のリスクを高める一因となることがわかっています。人と会話をしたり、一緒に笑ったりすることは、脳にとって良い刺激になります。
家族とのコミュニケーションはもちろん、地域のイベントや趣味のサークル活動などに積極的に参加し、新しい人との出会いを楽しむことも大切です。認知症対策としてだけでなく、日々の生活に彩りと活気をもたらしてくれます。
趣味など知的活動を始める

読書や囲碁・将棋、楽器の演奏といった知的な活動は、脳を活性化させ、認知機能の維持に役立ちます。
大切なのは、楽しみながら無理なく続けられること。難しすぎるとストレスになってしまうため、自分が「面白い」と感じるものを見つけるのが長続きのコツです。
また、編み物やガーデニング、料理など、手先を細かく使う趣味もおすすめです。指先は「第二の脳」とも言われるほど多くの神経が通っており、手先を使う作業は脳に直接的な刺激を与え、効率的に活性化させることができます。
物忘れを感じたときのセルフチェックと医療相談

「あれ、今何をしようとしてたんだっけ?」そんな物忘れが増えてくると、ご本人もご家族も不安な気持ちになりますよね。
日常生活では、以下のような工夫を取り入れてみるのもよいでしょう。
- 1大事なことはメモを取り、目につく場所に貼る
- 2カレンダーに予定を書き込み、家族と共有する
- 3鍵や財布など、物の定位置を決めておく
こうした対策をしても、物忘れが生活に支障をきたすようになったり、頻度が増えたりするようであれば、一度かかりつけ医や専門の医療機関に相談することをおすすめします。
早期に相談することで、適切なアドバイスやサポートを受けることができ、ご本人とご家族の負担を軽減することにもつながります。
認知症を判断するチェックリスト

ご自身の物忘れが、単なる加齢によるものなのか、それとも認知症の始まりなのか、ご自身で判断するのは難しいことです。
最終的な診断は専門医に委ねるべきですが、現在の状態を客観的に把握するためのセルフチェックリストも存在します。
以下にご紹介するサイトでは、いくつかの簡単な質問に答えることで、認知症の傾向を自分である程度確認することができます。
あくまでも簡易的なものですが、ご自身の状態を知る一つのきっかけとして、また医療機関に相談する際の参考として、気になる方は一度試してみてはいかがでしょうか。
「知力健康」をサポートするならオールインワンサプリ「Rimenba」!

いつまでも自分らしく、いきいきとした毎日を送りたい。そう願うすべての方に自信を持っておすすめしたいのが、オールインワンサプリ「Rimenba(リメンバ)」です。
「知力健康」というコンセプトのもと、脳神経内科の専門医が監修し、現代人に不足しがちな栄養素から、知的パフォーマンスの維持に役立つとされる成分まで、実に20種類以上もの栄養素を黄金比で配合しています。

毎日口にするものだからこそ、その品質にも徹底的にこだわりました。医薬品レベルの品質管理基準である「GMP認定工場」で製造。
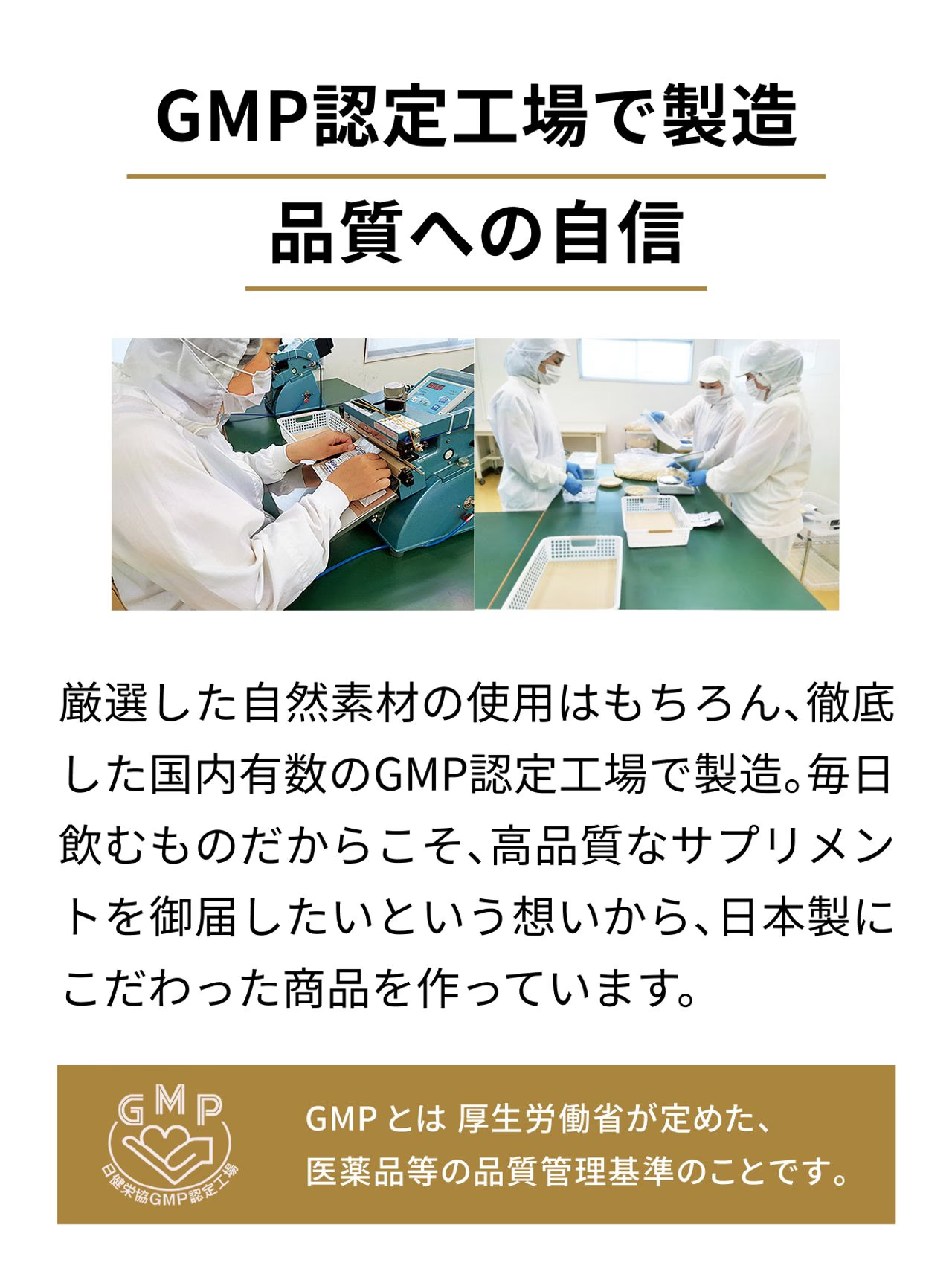
香料や着色料、保存料といった余計な添加物は一切使用していません。

さらに、お客様が始めやすいように、お得な初回割引をご用意しており、継続回数のお約束もないため、いつでも解約が可能です。
「自分に合うか試してみたい」という方でも、安心してお申し込みいただけます。いきいきとした毎日を力強くサポートする選択肢として、ぜひ「Rimenba」をお役立てください。
認知症予防は質の高い睡眠から!しっかり眠って脳の健康を維持しよう

質の良い睡眠は、脳の老廃物を掃除し、記憶を整理し、心身の疲れを癒すために不可欠です。
加齢やストレスで眠りが浅くなりがちな今だからこそ、寝室の環境を整え、生活リズムを意識し、日中の過ごし方を見直しましょう。今日からできる小さな一歩が、10年後、20年後のあなたの脳の健康を守る大きな力となります。
認知症は、決して他人事ではありません。しかし、日々の生活習慣を改善することで、そのリスクを下げられる可能性があります。まずは、今夜の睡眠から意識を変えてみませんか?
そして、バランスの良い食事を心がけるとともに、不足しがちな栄養素を補う賢い選択肢として、オールインワンサプリ「Rimenba」があなたの健やかな未来作りをサポートします。
しっかり眠り、しっかり栄養を摂って、いつまでもクリアで活力に満ちた毎日を送りましょう。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授
【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター
神屋ヒロキ
執筆実績500記事を超える専業Webライター。ITから法律、ECビジネス、健康問題まで幅広く執筆。趣味は小説執筆と音声入力と生活改善。
あなたへのおすすめ
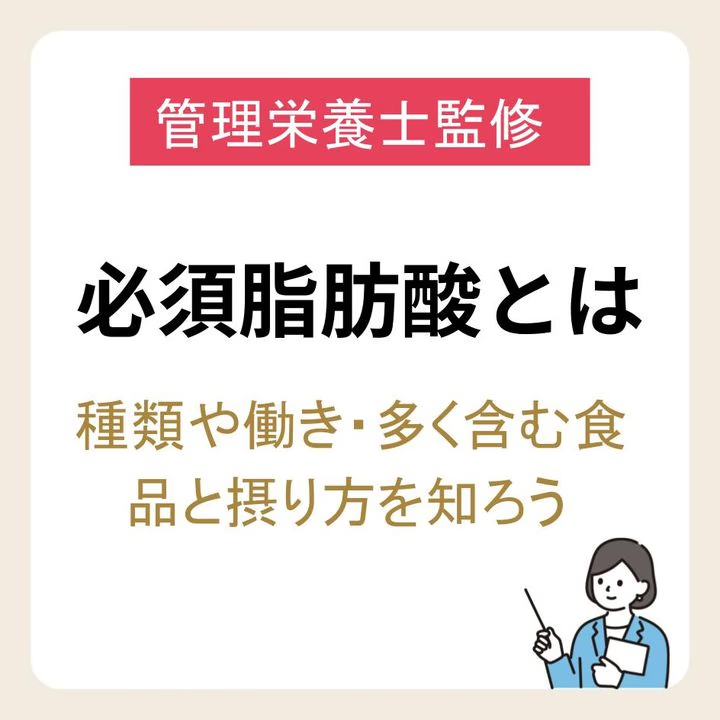
知力健康
【管理栄養士監修】必須脂肪酸とは?種類や働き・多く含む食品と摂取方法を知ろう
近年の健康意識への高まりとともに「必須脂肪酸」という言葉を耳にする機会も増えていま...
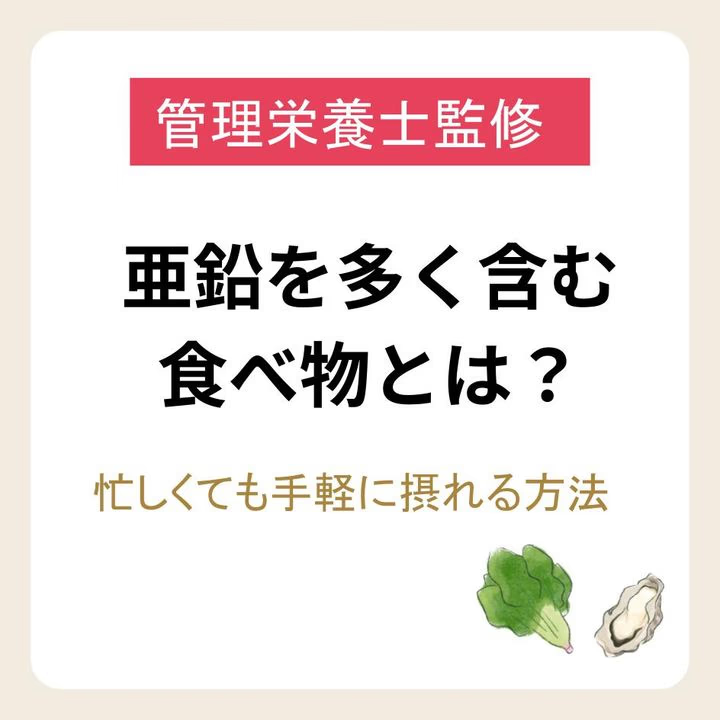
知力健康
【管理栄養士監修】亜鉛を多く含む食べ物とは?忙しくても手軽に摂れる方法
「亜鉛不足かもしれない、どんな食べ物に多く含まれているの?」「毎日の食事で、自然に...
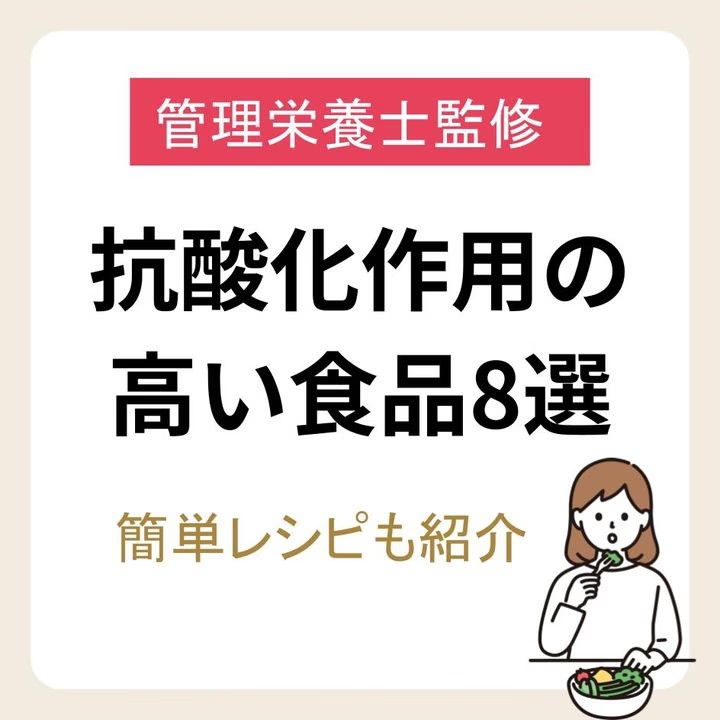
知力健康
【管理栄養士監修】抗酸化作用の高い食品ランキング8選|簡単レシピも紹介
「最近、疲れがとれにくい」「肌のハリやツヤが気になってきた」と感じることはありませ...