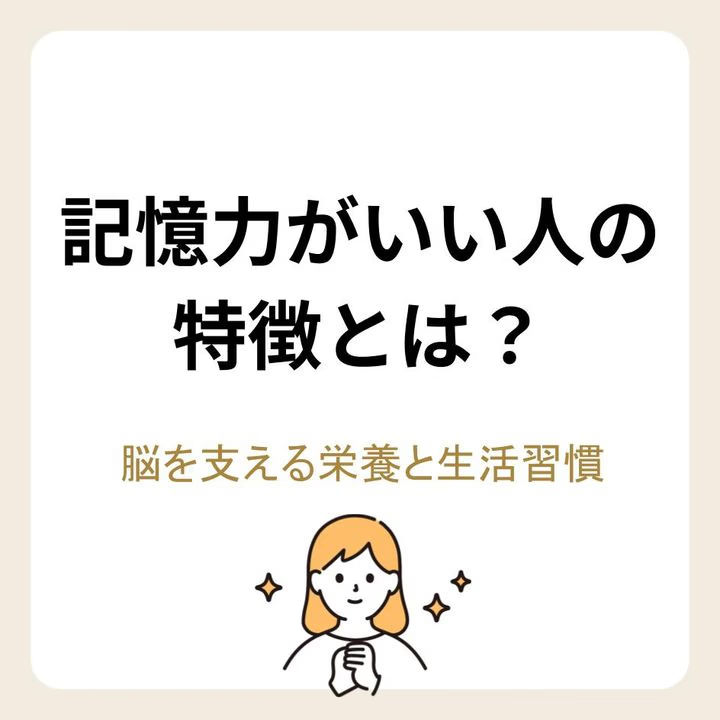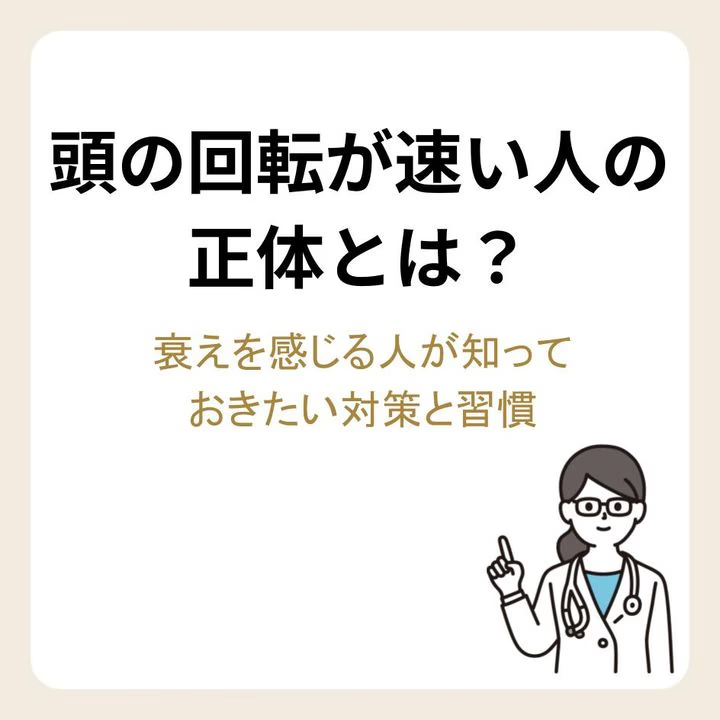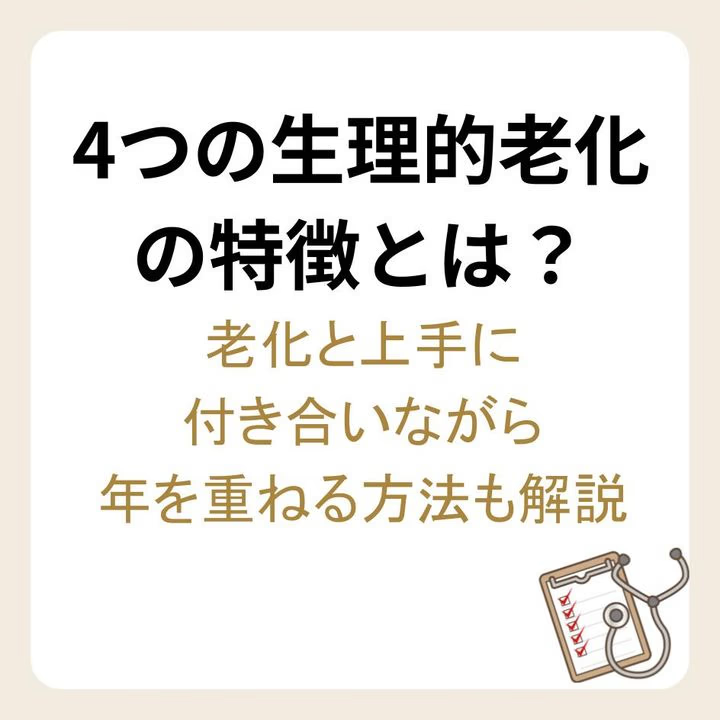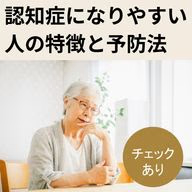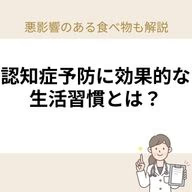2026-02-23
睡眠の質を向上させる7つのポイントとは?良い睡眠には時間と質の両方が重要

睡眠時間が少ない、睡眠時間は十分なのに疲れが残っているなど、睡眠の悩みを抱えている方は少なくないでしょう。良い睡眠には時間と質の両方が必要です。
睡眠時間は明確な数字があるので意識しやすいですが、睡眠の質については確保の仕方がよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では睡眠の質の正体や、睡眠の質を向上させるための7つのポイント、睡眠不足により引き起こされる悪影響を解説します。睡眠の時間と質、両方を意識して、翌日に疲れを残さないようにしましょう。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授

Webライター
木原かおる
- コスメ薬機法管理者
- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)
- 景品表示法・特定商取引法広告遵守個人認証(KTAA)
睡眠時間は確保しているのに疲れがとれないのはなぜ?
 睡眠時間は確保しているのに、翌朝疲れが残っている場合は、睡眠の質が不十分である可能性が高いです。では、睡眠の質とはそもそも何なのでしょうか?
睡眠時間は確保しているのに、翌朝疲れが残っている場合は、睡眠の質が不十分である可能性が高いです。では、睡眠の質とはそもそも何なのでしょうか?
厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」の中では、睡眠の質のことを「睡眠休養感」としています。分かりやすく言い換えると、朝目覚めた時にしっかりと休まった感覚があるかどうかということです。
ガイドの中では、良い睡眠は睡眠の量である睡眠時間と質である睡眠休養感の両方が十分であることが必要とも述べています。睡眠時間が不十分である場合は、まず生活を見直して、睡眠時間を確保することから始めましょう。
睡眠の質を向上させる7つのポイント
 睡眠の質を向上させるためには、環境面の4つのポイントと、習慣面の3つのポイントがあります。できそうなものから取り入れて、睡眠の質を高めていきましょう。
睡眠の質を向上させるためには、環境面の4つのポイントと、習慣面の3つのポイントがあります。できそうなものから取り入れて、睡眠の質を高めていきましょう。
体内時計を意識して光を調整する
睡眠の質を向上させる環境面の1つ目のポイントが光です。夜、ぐっすり眠るためには体内時計を整えることが大切です。体内時計を整えるためには、朝日を浴び、日中は明るく、夜は暗い環境で過ごしましょう。
朝はカーテンを開けて室内に光を取り入れる、夜は照明を少し暗くするなど、時間に応じて光を調節するのがおすすめです。
また、スマホなどの画面からはブルーライトが出ており、夜に浴びると体内時計に影響を与え、睡眠の質を下げてしまう可能性があります。眠る1時間前からは、画面を見ないことを習慣にしましょう。
暑すぎず、寒すぎない温度を維持する
寝室の温度を快適に保つことも、睡眠の質の向上につながります。夏は寝苦しくなるので、以下の方法も取り入れてみましょう。
- 1エアコンを活用し、涼しい環境を保つ
- 2エアコンを付けたままだと体調や電気代が不安な場合は、タイマーや扇風機を活用する
- 3室温が28℃未満であれば、送風だけでも快適に過ごせる場合も
逆に寒さは布団をかぶれば何とかなると考えがちです。しかし、トイレに行きたくて起きた際に、部屋が寒いと目が覚めてしまい、再び眠りにくくなるので、室温が18℃を下回らないようにしましょう。
また、眠る1~2時間前にお風呂に入り、一度体温を上げ、徐々に下げていくことで、眠りやすくなります。シャワーで済ませる方も多いでしょうが、シャワーだけでは体が十分に温まりません。他にも健康面、美容面でメリットがあるので、湯船につかる習慣を取り入れましょう。
音を遮断して静かな環境を作る
静かな環境を作ることも、睡眠の質の向上に重要なポイントです。窓や壁の構造により、外からの音を遮断できるような静かな部屋で眠るのがベストです。
賃貸の場合は壁や窓を自分で改良するわけにはいかないので、耳栓を活用しましょう。ゴムやスポンジでできたものであれば、種類も豊富で手に入りやすいです。また、最近はノイズキャンセリング機能を活用したイヤホン型の耳栓も出ています。
耳栓をつけると、目覚ましのアラームの音が聞こえるか不安という場合は、振動で起こすスマートウォッチや、光で起こす目覚まし時計などを組み合わせましょう。
快適に眠れる寝具を選ぶ
快適に眠れる寝具を選ぶことも、睡眠の質の向上につながります。寝具には掛け布団、体の下に敷くマットレスや敷き布団、枕の3つがありますが、それぞれに異なるポイントがあります。
| 寝具の種類 | ポイント | 選ぶ際に注意する点 |
|---|---|---|
| 掛け布団 | ・保温性 ・吸放湿性 | 放熱や発汗により体から熱が奪われ過ぎないもの、汗を吸収・透過させて放出させるものを選ぶ |
| マットレス、敷き布団 | ・クッション性 ・フィット性 | 背骨を自然な形でバランス良く支えられるように、適度な硬さを持ったものを選ぶ |
| 枕 | 寝具と後頭部から首にかけての隙間を埋める | 隙間は個人差が大きいので、自分の体型にあった高さのものを選ぶ |
既製品だと体にぴったり合わせるには限界があります。自分に合ったものが見つからない場合は、体の状態を計測して、オーダーメイドで作れる寝具メーカーを利用しましょう。
寝る前にリラックスできる習慣を取り入れる
興奮していては、当然寝付けないので、睡眠の質を向上させるために、寝る前のリラックス習慣を取り入れましょう。
- 1ゆったりとした音楽を聴く
- 2水の流れや波の音など自然の音を流す
- 3アロマオイルやお香、ハーブティーなどで香りを楽しむ
- 4アイマスクで目元を温める
眠る前にハーブティーを飲む場合は、ノンカフェインのものを選びましょう。
日中の適度な運動で眠りやすくする
日中の活動で疲れがたまっていれば、夜には自然に眠くなります。そこで、日中に適度な運動を取り入れることも、睡眠の質の向上にはおすすめです。習慣的に運動している人の70% 以上は睡眠の質がよいとも報告されています。
厚生労働省が発行している「良い目覚めは良い眠りから 知っているようで知らない睡眠のこと」の中では、現役世代は中・高強度の運動、リタイア世代は低強度の運動が睡眠不足のリスクを減らすとされています。
しかし、いきなり体に負荷をかけてしまうと、ケガの原因にもなり、長続きもしません。まずは、続けられそうなものから始めましょう。
Check
<運動強度の目安>
低強度…散歩、体操、ストレッチ、ヨガ、家の掃除、草むしり、軽い荷物の運搬など
中強度…野球、ハイキング、子供と活発に遊ぶ、適度な重さの荷物の運搬など
高強度…ジョギング、テニス、サイクリング、水泳、農作業、重い荷物の運搬など
ただし、眠る2~4時間前の運動は目が覚めてしまい、睡眠の質を下げるので、運動を行う時間にも注意する必要があります。
食生活のリズムや嗜好品の取り方に注意する
食生活も睡眠の質に影響します。栄養バランスのとれた食べ物を選ぶだけでなく、体内時計を整えるという点で、食事の時間やリズムを意識しましょう。特に重要なのが朝食と夕食です。
朝食は抜かずにきちんと食べる
朝食を抜いてしまうと、体内時計が後ろにずれて、夜の眠りにも影響してしまいます。
また、眠る前の2時間以内に食事をすると、消化器官が働くことで、睡眠の質を低下させてしまうので、遅い時間の夕食も要注意です。
カフェインとアルコールに注意する
カフェインは目を覚ます作用や利尿作用があるため、眠りが浅くなったり、トイレに起きたりする原因となってしまいます。特に夕方以降のカフェインは少量であっても睡眠に影響する可能性があるので、注意しましょう。
カフェインはコーヒーだけでなく、緑茶、紅茶、栄養ドリンクなど、さまざまな飲み物に含まれます。また、近年ブームになっているエナジードリンクにもカフェインが使われているものがあるので、よく飲む方は要注意です。
アルコールについては、寝付きがよくなるからと、寝酒を飲むこともあるでしょう。しかし、アルコールは睡眠の質を悪化させるので、一時的に寝付きはよくなりますが、夜中に目が覚めることが少なくありません。
飲酒量が増えれば、さらに顕著になります。睡眠の質を向上させるためには、晩酌はほどほどにして、寝酒は控えましょう。
睡眠時間は多すぎても少なすぎてもダメ
 良い眠りには睡眠の質だけでなく、睡眠時間も必要ですが、やみくもに長く眠ればいいというわけではありません。一晩に眠れる時間には限度があり、身体が必要とする睡眠時間以上に眠ろうとすると、眠るまでに長く時間がかかったり、途中で目が覚める回数が増えたりして、かえって睡眠の質を下げてしまうのです。
良い眠りには睡眠の質だけでなく、睡眠時間も必要ですが、やみくもに長く眠ればいいというわけではありません。一晩に眠れる時間には限度があり、身体が必要とする睡眠時間以上に眠ろうとすると、眠るまでに長く時間がかかったり、途中で目が覚める回数が増えたりして、かえって睡眠の質を下げてしまうのです。
必要な睡眠時間には個人差がある他、年齢や季節によっても変わります。「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、子供、成人、高齢者に分けて、睡眠時間の目安を設定しています。
まずはスマホのアプリやスマートウォッチを活用して、自分の睡眠時間を把握し、不十分である場合は目安の睡眠時間を確保できるようにしましょう。
| 睡眠時間の目安 | |
|---|---|
| 子供 | 小学生は9〜12時間、中学・高校生は8〜10時 |
| 成人 | 6時間以上 |
| 高齢者 | 8時間以上にならないこと |
高齢者の場合、睡眠時間や床上時間が長いことが健康リスクになるとのデータが出ています。また、長時間の昼寝もリスクにつながる可能性があります。高齢者の方は睡眠時間よりも、起きている時間を意識しましょう。
睡眠不足による悪影響
 睡眠が不十分だと、翌日に眠気や疲労が残り、仕事や学業などの活動に支障が出ます。
睡眠が不十分だと、翌日に眠気や疲労が残り、仕事や学業などの活動に支障が出ます。
Check
2025年に株式会社ポケモンと筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構が、睡眠ゲームアプリのユーザー8万人を対象に行った調査では、健康的な睡眠をとっていない人は年間で13.6万円の経済損失に相当するほど労働生産性が低下すると発表されました。
経済損失の数字を日本全体に当てはめると、年間約1兆円の経済損失になると試算されています。
また、睡眠不足はさまざまな疾患のリスクにつながることも報告されています。近年クローズアップされている生活習慣病、精神疾患、認知症とも関連するため、影響をよく理解しておきましょう。
参考:プレスリリース『Pokémon Sleep』×『筑波大学』共同大規模調査 第三弾 不規則な睡眠と労働生産性の低下の関係が明らかに! 年間の経済損失推定値は約1兆円にのぼる可能性も。
生活習慣病
慢性的な睡眠不足が生活習慣病のリスクにつながる可能性があります。平日に睡眠時間を確保できないからと、休日に寝だめをしようとする方は少なくないでしょう。しかし、寝だめにより、平日と休日で寝る時間や起きる時間にズレが生じてしまいます。
時差のある外国への旅行と似ていることから、ソーシャルジェットラグ(社会的時差ボケ)と呼ばれ、体内時計の乱れにつながるのです。ソーシャルジェットラグは肥満や糖尿病などの生活習慣病の他、脳血管障害や心血管系疾患のリスクとなることが報告されています。
精神疾患
精神疾患と睡眠が関連していることを示唆する結果が報告されています。国立精神・神経医療研究センターの研究では、睡眠時間4時間半ほどの睡眠不足が5日間続くと、うつ病や統合失調症などの患者に似た脳機能変化がみられ、不安や混乱、抑うつ傾向が強まるとの結果が出ました。
さらに、先に述べたソーシャルジェットラグはうつ病のリスク要因にもなると報告されている他、睡眠不足がうつ病と関連することを示唆した日本人を対象とした研究結果もあります。
また、うつ病患者は高い確率で不眠症も抱えているとの報告や、うつ病患者の約41%で不眠症状が他の抑うつ症状よりも先に現れるとの報告もあります。
認知症
睡眠不足や質の悪い睡眠は認知症のリスク要因になります。質の悪い睡眠や短い睡眠時間、24時間眠らないことで、アルツハイマー型認知症の原因であるアミロイドβが増えたとの結果が報告されています。
また、眠りすぎることも認知症のリスクになることを覚えておきましょう。9時間以上の長い睡眠はアルツハイマー型認知症の発症リスクを高めることが報告されています。
睡眠の質を向上させて疲れを残さない毎日に
 睡眠が不十分だと、単にパフォーマンスを低下させるだけでなく、生活習慣病、精神疾患、認知症のリスクにもつながります。よい睡眠をとるためには、睡眠時間だけでなく、睡眠の質を向上させることも重要です。
睡眠が不十分だと、単にパフォーマンスを低下させるだけでなく、生活習慣病、精神疾患、認知症のリスクにもつながります。よい睡眠をとるためには、睡眠時間だけでなく、睡眠の質を向上させることも重要です。
光、温度、音、寝具といった環境面と、運動、リラックス、食事といった習慣面での対策を取り入れて、睡眠の質を向上させ、朝目覚めた時にしっかりと休まった感覚が得られることを目指しましょう。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授
【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター
木原かおる
- コスメ薬機法管理者
- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)
- 景品表示法・特定商取引法広告遵守個人認証(KTAA)
国内化粧品メーカー、外資系消費財メーカーで、品質管理や薬機法業務に約15年従事した後にフリーライターに。薬機法や成分関連の知識をいかして、コスメやサプリのライティング、校正、記事監修などを手がける。