2025-11-19
ビタミンDサプリはいつ飲む?働き・タイミング・注意点などを詳しく解説
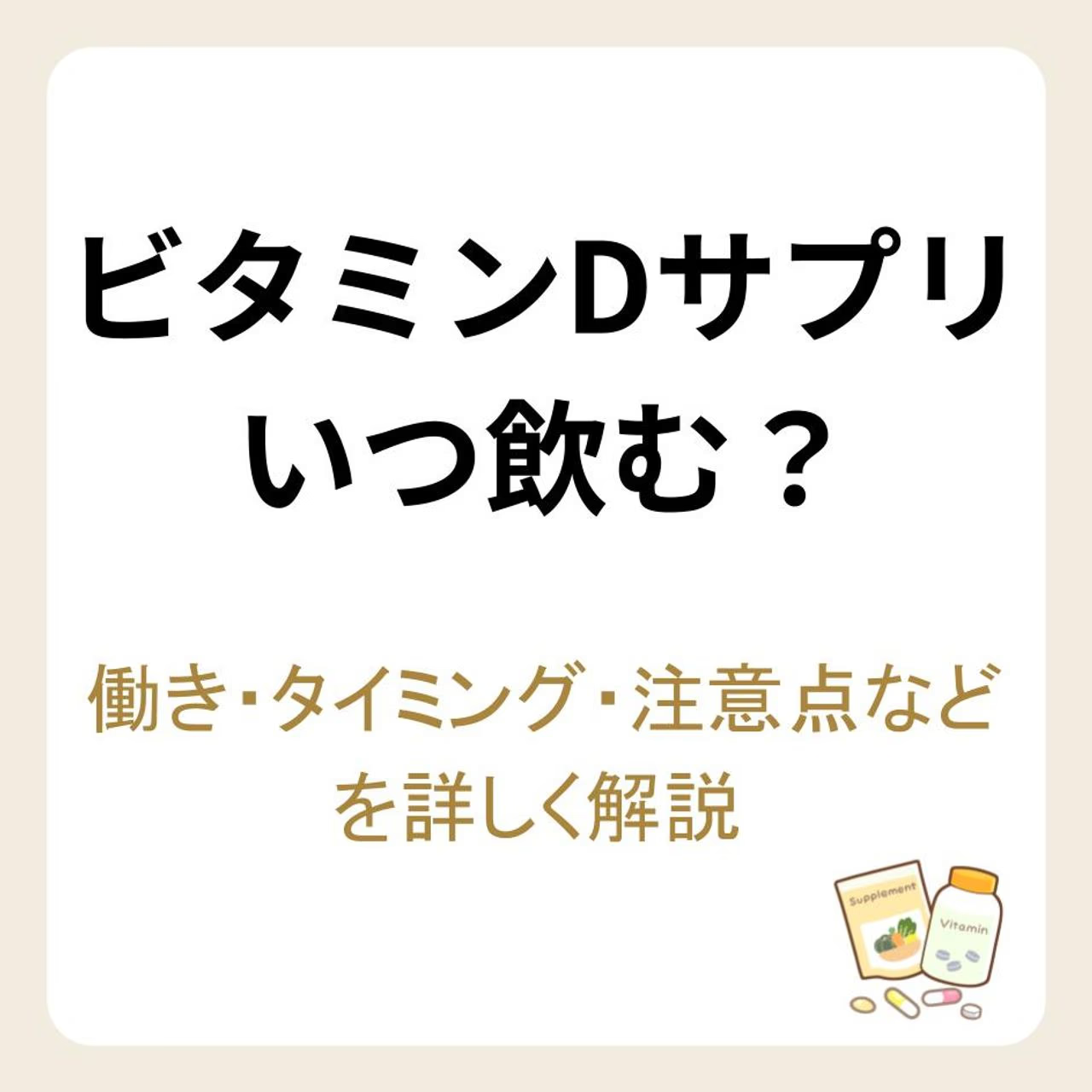
「ビタミンDサプリって、朝と夜どっちに飲むべき?」
「食前と食後、どちらが吸収されやすいんだろう?」
このような疑問はありませんか?
サプリメントは薬ではなく「食品」に分類されるため、基本的に「いつ飲むべき」といった指定はありません。しかし、おすすめのタイミングはあります。
本記事では、ビタミンDサプリメントを取り入れるタイミング、ビタミンDの働き、一緒に摂取したい栄養素について解説します。
目次
- ビタミンDサプリはいつ飲むのがおすすめ?
- ベストタイミングは食中もしくは食後
- 時間帯の推奨は特になし
- ビタミンDとは?
- ビタミンDの特徴・役割とは
- ビタミンDの摂取方法
- ビタミンDサプリが必要な理由
- ビタミンDサプリと一緒に摂取したい栄養素
- 骨を強くする|カルシウム・ビタミンK
- ビタミンDを腎臓で活性化|マグネシウム
- ビタミンDサプリの摂取目安量と過剰摂取のリスク
- 1日の摂取目安量
- ビタミンDを過剰摂取するリスク
- 信頼できるビタミンDサプリの選び方
- 医師・専門家の監修が入っている
- サポート成分が入っている
- GMP認証工場で製造されている
- 添加物を使用していない
- ビタミンDを含むサプリなら「Rimenba(リメンバ)」がおすすめ!
- ビタミンDサプリを活用して元気な毎日を目指そう
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授

Webライター
のん
- 薬膳調整士
- 漢方コーディネーター
- 化粧品3級
ビタミンDサプリはいつ飲むのがおすすめ?

ここでは、ビタミンDサプリを飲むおすすめのタイミングを紹介します。ビタミンDの働きを高めるための参考として、ぜひチェックしてみてください。
ベストタイミングは食中もしくは食後

ビタミンDのサプリメントを飲むタイミングは、食事中もしくは食後をおすすめします。ビタミンDは脂溶性のビタミンであり、脂質と一緒に摂ると溶けて吸収効率が高くなるためです。
ただし、食事内容は脂質を含む必要があります。野菜のみ、塩おにぎりのみといった、脂質が少ない食事を済ませる場合には向きません。
野菜を食べる際は鶏肉や豚肉を足したり、オリーブオイルやオイルドレッシングをかけたりしましょう。おにぎりは、シャケやツナマヨといった脂質を含む具材のおにぎりを選ぶのがポイントです。
時間帯の推奨は特になし

ビタミンDは、朝に飲んだほうがよい、夜がよいといったことはありません。ご自身が忘れずに続けられる時間帯を選択しましょう。
ビタミンDにおいては、脂質と一緒に摂る必要があるため、時間帯ではなく食事内容に合わせて摂取することが大切です。
例えば、朝食をプロテインで済ませる方は、脂質が摂取しやすいランチやディナーの時間帯がおすすめです。反対に、朝からバランスよくしっかりと食べる方であれば、朝の食事中や食後が向いています。
ビタミンDとは?
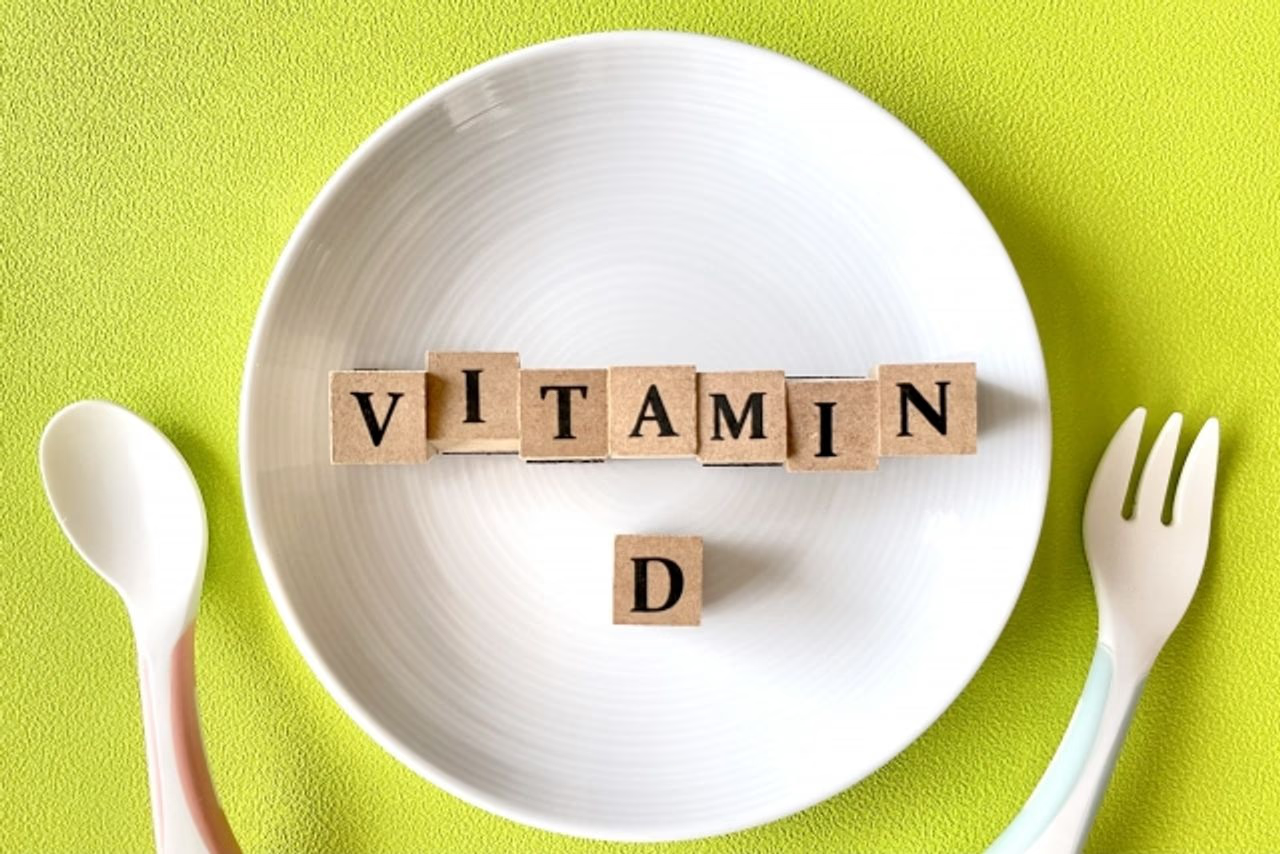
ここでは、ビタミンDの特徴や役割、基本的な摂取方法、サプリメントの必要性について解説します。
ビタミンDの特徴・役割とは
ビタミンには水溶性と脂溶性があり、ビタミンDは脂溶性に該当します。
ビタミンDは、全身の健康を保つために重要な栄養素で、以下のような働きを持っています。
- 1血中のカルシウム濃度を一定に調節する
- 2カルシウム・リンの吸収促進
- 3筋肉の動作・神経物質の伝達・免疫に関与
ビタミンDは、血中カルシウム濃度を一定に調節してくれます。また、食事から摂取したカルシウム・リンの吸収を促し、骨や歯の健康を維持することも働きの一つです。
このほか、筋肉を動かしたり、神経物質を伝達したり、免疫機能の調整に関わったりします。
ビタミンDの摂取方法
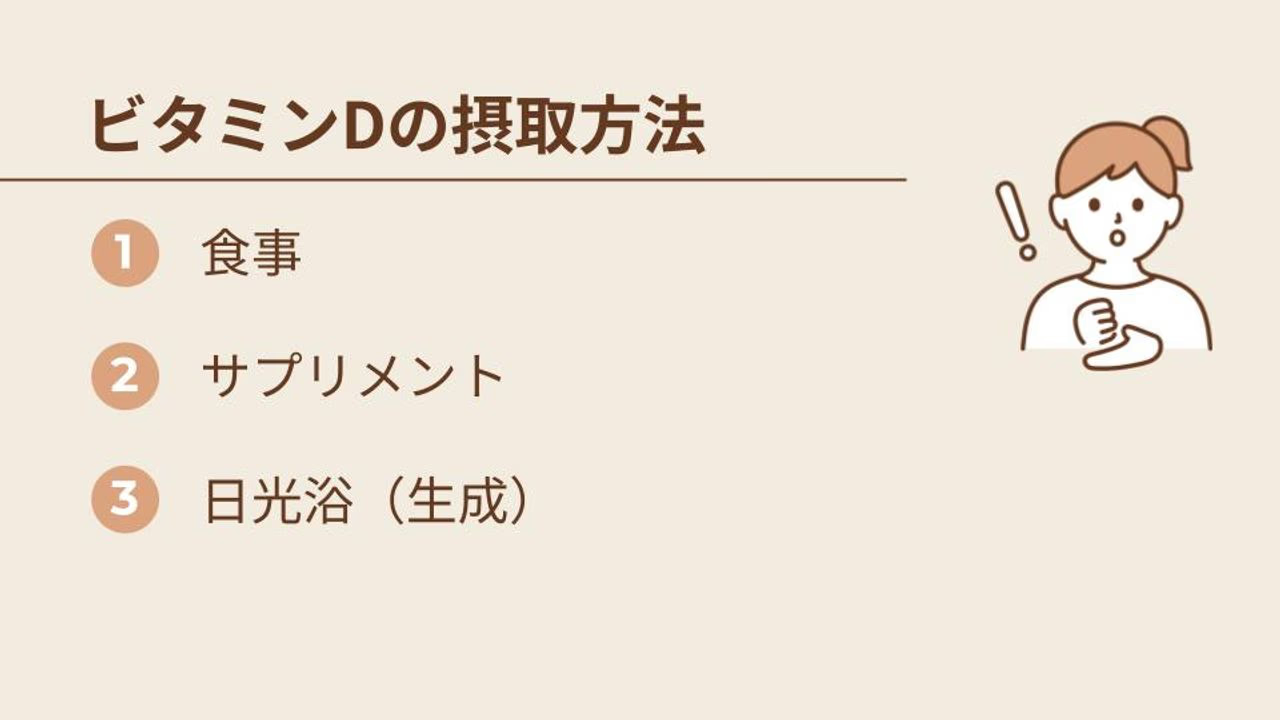
ビタミンDの摂取方法は3つあります。効果的に摂取するためのポイントも紹介していますので、ぜひ実践していきましょう。
食事
ビタミンDを食事から摂れるものは、魚類ときのこ類、卵です。
ビタミンDが多く含まれている食材には、以下が挙げられます。
Check
【魚類の食材】
イワシ丸干し、サンマ、しらす干し、カレイ、サケ、ブリ
これらは特にビタミンDを豊富に含んでいます。また、同時摂取がおすすめなカルシウムも豊富なため、積極的に取り入れていきましょう。
Check
【きのこ類の食材】
干し椎茸、キクラゲ
椎茸には、紫外線に当てるとビタミンDが増量する特徴があるため、天日干ししたものがおすすめです。
サプリメント
食事よりもより手っ取り早く摂取できる方法に、サプリメントが挙げられます。サプリメントであれば、きのこ類や魚類が苦手な方、日光アレルギーがある方でも、手軽にビタミンDが摂取可能です。
ただし、サプリメントはたくさんの量を摂取すればよいというものではありません。過剰摂取につながる可能性があるため、サプリメントごとの推奨摂取量を守ることが大切です。
袋パッケージやボトルに表記されている摂取目安量を、忘れずにチェックしましょう。
日光浴で生成することもできる
ビタミンDは、日光浴で皮膚に紫外線が当たることでも生成が可能です。生成させるためには、肌を出した状態でウォーキングや散歩で日光に当たる必要があります。
生成に必要な紫外線は「B波」と呼ばれるもので、ガラスや服でカットされる性質があります。そのため、窓辺での日光浴や日焼け止めの塗布、アームカバーなどで肌を覆うなどすると、生成できません。
とはいえ、紫外線のあたりすぎや日焼けは体に負担がかかるため、日焼けしない程度に短時間に留めておきましょう。
ビタミンDサプリが必要な理由

日光浴は、十分な量のビタミンDを生成するのは難しいうえに、紫外線による細胞ダメージや日焼けする可能性があります。
加えて、食事だけでビタミンDの必要量を摂取するのも容易ではありません。よって、十分な量を摂取するには、サプリメントの活用が効率的です。
ビタミンDの不足すると、以下のようなリスクが生じるおそれがあるといわれています。
- 1低カルシウム血症:骨粗鬆症のリスクを高める
- 2うつ病発症の可能性:セロトニンの合成力が低下し気持ちが不安定になる
- 32型糖尿病発症の可能性:ビタミンDの不足者は発症リスクが高いとの報告がある
また、更年期以降は骨密度を維持する女性ホルモンの分泌が低下することで、骨粗鬆症のリスクが高まるといわれています。
ホルモンバランスの乱れで精神バランスも乱れがちなため、骨の強化や精神安定に寄与するとされる、ビタミンDの摂取が欠かせません。
ビタミンDサプリと一緒に摂取したい栄養素
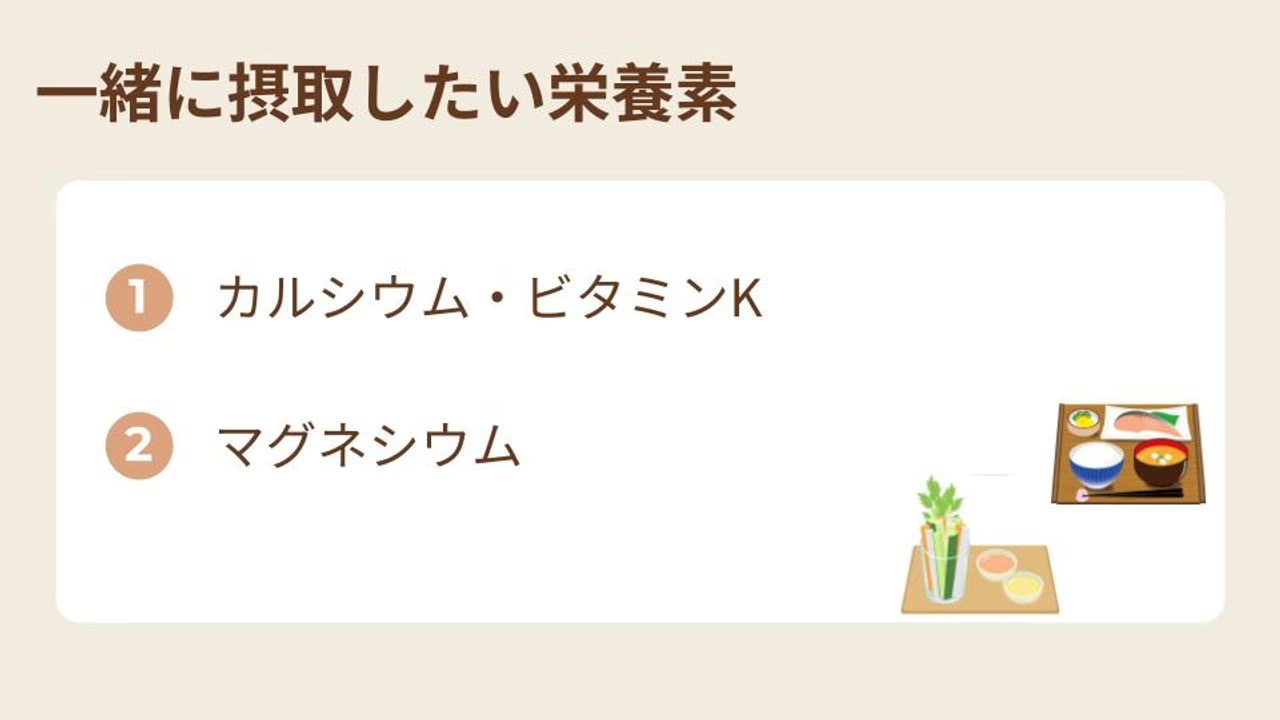
ビタミンDは、特定の栄養素と一緒に摂取することで、相乗効果が期待できる栄養素です。
ここでは、期待できる相乗効果と、同時に摂りたいおすすめの栄養素をお伝えします。
骨を強くする|カルシウム・ビタミンK

骨を強くしたい方は、ビタミンDサプリの摂取時にカルシウム・ビタミンKを摂りましょう。ビタミンDは、カルシウムやビタミンKの働きをサポートし、骨を強化します。
更年期以降は骨粗鬆症のリスクが上がるため、丈夫な骨を維持するためにも脂質・カルシウム・ビタミンKを含む食事とサプリを組み合わせるのがおすすめです。
もしくは、サポート成分としてカルシウム・ビタミンKが含まれるサプリメントを購入する方法もあります。
ビタミンDを腎臓で活性化|マグネシウム

マグネシウムとビタミンDは、一緒に摂取することで相互作用が期待できます。
<期待できる相互作用>
- 1マグネシウムは腎臓でビタミンDを活性化させる
- 2ビタミンDはマグネシウムの吸収を助ける
マグネシウムは、海藻類や魚介類に多く含まれます。
食事で海藻類や魚介類を取り入れるか、サポート成分でマグネシウムが配合されているサプリメントを活用して意識的に摂取していきましょう。
ビタミンDサプリの摂取目安量と過剰摂取のリスク

ビタミンDは1日の摂取目安量が設定されており、それに合わせた量を取ることがおすすめされています。
なぜ、目安量を超えるとよくないのか、ここでは過剰摂取のリスクと目安量について解説します。
1日の摂取目安量
1日の摂取目安量は、通常年齢や性別によって異なります。ビタミンDにおいては、年齢別に目安量に差があるものの、男女ともに同じ量が推奨されています。
| 年齢 | 男性・女性の目安量 |
|---|---|
| 1〜2歳 | 3.5 |
| 3〜5歳 | 4.5 |
| 6~7歳 | 5.5 |
| 8〜9歳 | 6.5 |
| 10~11歳 | 8.0 |
| 12~75歳以上 | 9.0 |
ビタミンDを過剰摂取するリスク

ビタミンDは脂溶性であり、水溶性のようにスムーズに排出はされません。そのため、摂取した分だけ体内に残りやすいのが特徴です。
ビタミンDを過剰摂取すると、高カルシウム血症やビタミンD中毒を引き起こす可能性があります。健康のためにビタミンDを摂取しているのにも関わらず、体調が悪くなっては本末転倒です。摂取目安量を守ってサプリメントを使用しましょう。
信頼できるビタミンDサプリの選び方

信頼できるビタミンDサプリを選ぶには、成分量だけでなく品質や製造背景もチェックすることが大切です。
ここでは、安心して使い続けられるサプリメント選びのポイントを紹介します。
医師・専門家の監修が入っている

医師や専門家の監修があるサプリメントは、栄養学や医学の知識に基づいて作られているため安心感があるでしょう。また、信頼できる監修者が関わっている商品は、誇張した表現や不正確な情報が少ない傾向です。
監修の有無を確認するため、パッケージや公式サイトに医師や管理栄養士など資格を持つ人物の名前が明記されているかどうかを見てみましょう。
サポート成分が入っている
ビタミンDは単独で摂るよりも、働きを助ける成分と一緒に摂った方が効率が高まるため、サポート成分が入ったものがおすすめです。
ビタミンDとの組み合わせで相互作用が起きるとされている栄養素として、以下が挙げられます。
- 1ビタミンD×カルシウム:骨や歯の形成に役立つ
- 2ビタミンD×マグネシウム:ビタミンDの働きが活性化される
- 3ビタミンD×ビタミンK2:カルシウムが骨に届きやすくなる
- 4ビタミンD×オメガ3脂肪酸:免疫のサポートや炎症対策にも役立つ
サポート成分が配合されているサプリメントは、相乗効果の恩恵だけでなく、不足しやすい栄養素もまとめて補える点が強みです。
自分が重視したい目的に応じて、どの成分が加わっているかをチェックするとよいでしょう。
GMP認証工場で製造されている

GMP認証工場とは、製造や品質管理を医薬品と同じレベルで行う基準を満たした工場のことです。このような厳しい管理の元で作られたサプリメントは、不純物や異物が混じるリスクを減らせるだけでなく、成分量のばらつきを防ぐことにもつながります。
パッケージや商品説明に「GMP認証工場製造」もしくは「GMPマーク」の記載があるかを確認しましょう。日本国内や国際的に認められた基準に沿っていると明記されていれば、より信頼できます。
添加物を使用していない
添加物とは、食品の品質を維持したり、見た目を整えたりするために使われるものです。化学成分を使用したものや自然由来のものがあり、自然由来の添加物は体の負担が少ないとされています。
添加物が多いと、体質によっては体調に不調を感じる可能性があります。気になるようであれば、原材料表示にて「保存料不使用」「着色料不使用」といった記載があるかチェックしてみてください。
ビタミンDを含むサプリなら「Rimenba(リメンバ)」がおすすめ!

Rimenbaは、脳神経内科医監修のもと、ビタミンDをはじめとする20種類以上の成分を配合したオールインワンサプリメントです。ビタミンDと相性がよい成分や、更年期以降になると不足しやすい成分も配合されています。

Rimenbaは、国内有数のGMP認定工場で製造されており、品質の安定性が期待できます。
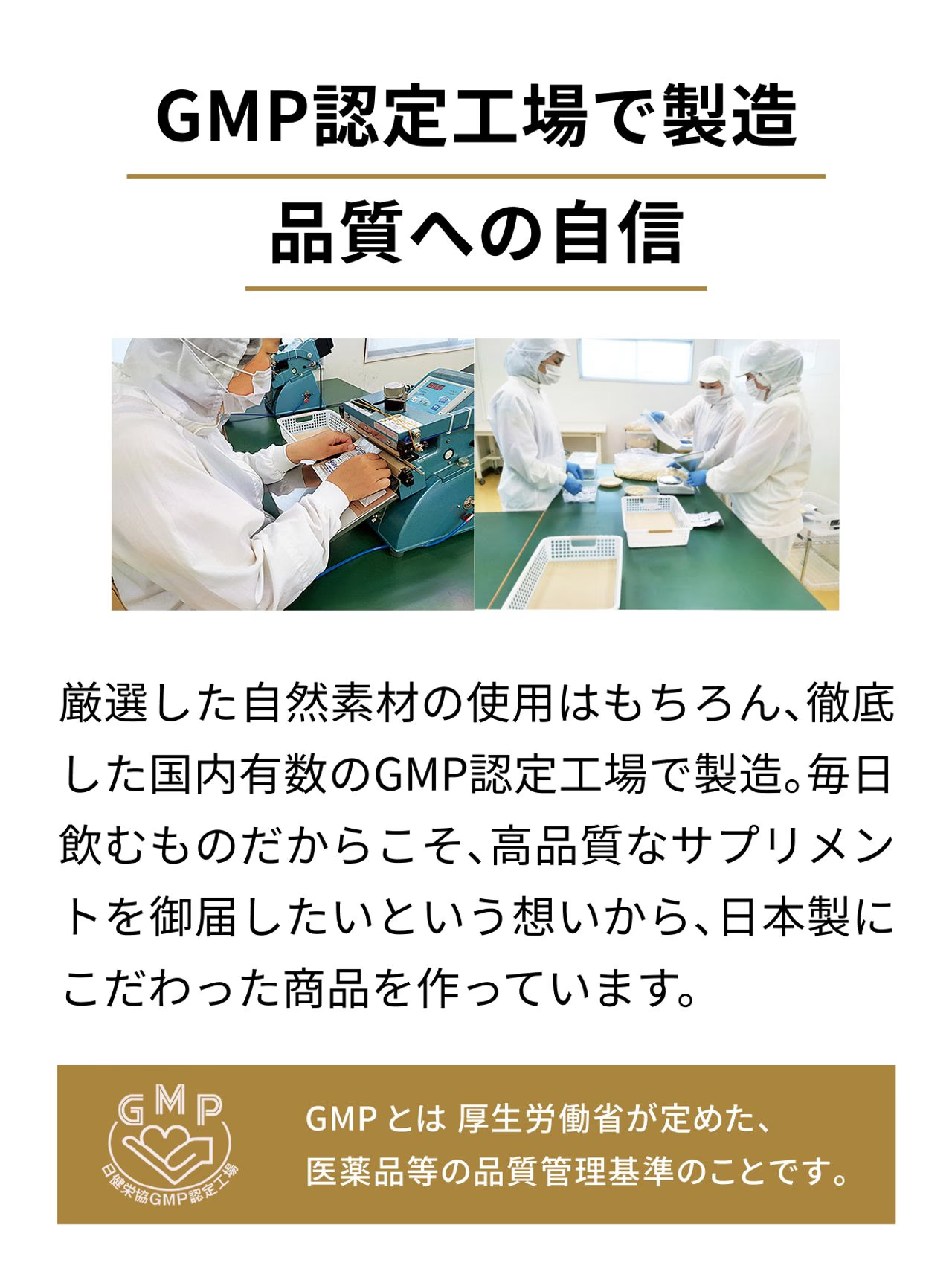
また、毎日使用することから体への負担を考慮し、余分な添加物は使用していません。

健康維持のため、ビタミンDサプリメントをお探しの方は、ぜひRimenbaをご検討ください。
初回は特別価格をご用意。定期便のため解約までお得な価格で購入を続けられ、送料も無料です。
配送日の10日前までであれば、いつでも解約可能。「定期便は購入回数の縛りでお試しが不安」という方も、安心してお試しいただけます。
ビタミンDサプリを活用して元気な毎日を目指そう

ビタミンDのサプリメントを摂取するおすすめタイミングは、脂質を含む食事中や食後です。朝・昼・夜など時間帯に決まりはないため、自分が続けやすいタイミングを見つけましょう。
ビタミンDは脂溶性ビタミンで、骨や歯の健康を守るだけでなく、筋肉や免疫機能にも関わる栄養素です。魚類やきのこ類、日光浴からも摂取できますが、必要量を満たすのは簡単ではありません。
特に、更年期以降の女性は骨粗鬆症やホルモンバランスの乱れが生じやすいため、ビタミンDの摂取が大切です。
信頼できるサプリメントを探している方は、ぜひRimenbaをお試しください。オールインワンタイプのため、1日4粒で20種類以上の栄養素を手軽に補えます。
うまくビタミンDサプリを活用して、元気な毎日を目指しましょう。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授
【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター
のん
- 薬膳調整士
- 漢方コーディネーター
- 化粧品3級
娘と保護猫4匹と一緒に暮らすママライター。 さまざまな健康トラブルから「健康」を意識するようになり、漢方や薬膳の資格を取得。 漢方・薬膳・メイク・車系・ペット系など資格や趣味を活かして幅広く執筆。
あなたへのおすすめ

知力健康
中性脂肪を下げる食べ物ランキング7選|おすすめのおつまみ・簡単レシピも紹介【管理栄養士監修】
「健康診断の結果で中性脂肪の数値が高かった」「お腹周りが気になってきた」というお悩...
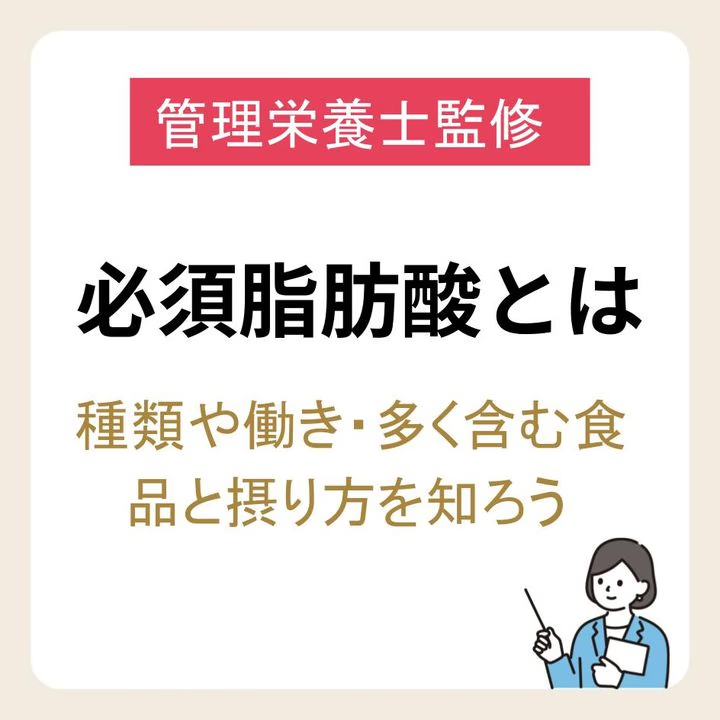
知力健康
【管理栄養士監修】必須脂肪酸とは?種類や働き・多く含む食品と摂取方法を知ろう
近年の健康意識への高まりとともに「必須脂肪酸」という言葉を耳にする機会も増えていま...
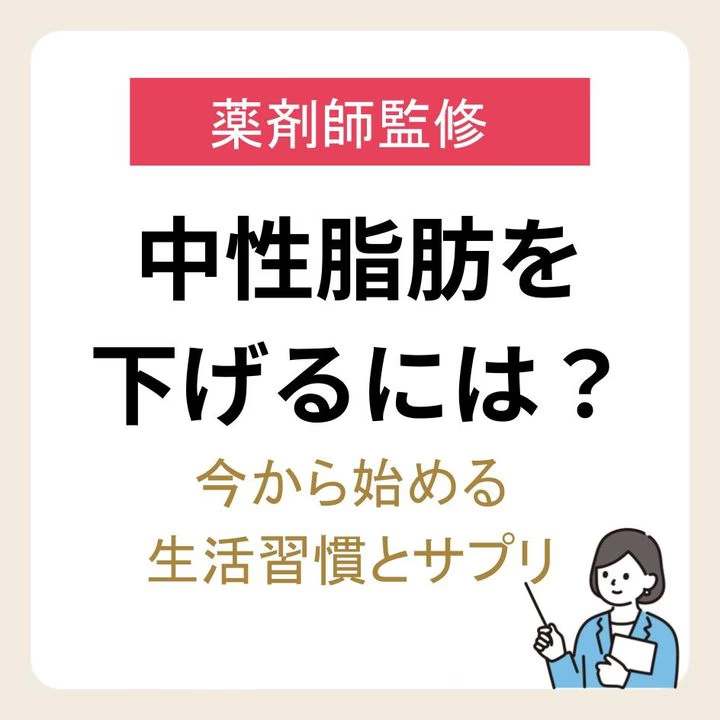
知力健康
【薬剤師監修】中性脂肪を下げるには?今から始める生活習慣とサプリ
健康診断で「中性脂肪がやや高め」と言われたものの、特に体調不良もなく、ついそのまま...











