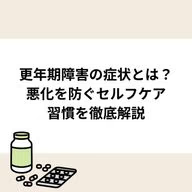2025-11-19
閉経は何歳から?平均年齢と更年期の「うっかり」に備える対策も紹介

「最近、生理の間隔がバラバラになってきた」「以前より疲れやすくなった気がする」
そんな変化を感じている方は、閉経が近づいているサインかもしれません。
閉経は、女性にとって人生の中でも大きな節目の1つです。月経が終わるという身体的な変化に加え、女性ホルモンのバランスが乱れることで、心身にさまざまな影響が現れることもあります。
のぼせや発汗、イライラ、集中力の低下、疲れやすさなど、その症状は人によって異なり、自分では気づきにくい場合も少なくありません。
そこで今回は、閉経の平均年齢や症状の個人差をはじめ、起こりやすい体と心の変化、そしてその対策まで、わかりやすく解説しています。「自分にも当てはまるかも?」と感じた方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
- 閉経は何歳から?平均年齢と個人差について
- 日本人女性の閉経の平均年齢は50歳前後
- 40代前半〜50代後半まで個人差がある
- 閉経の前兆で見られる体と心の変化
- 月経周期や経血量が乱れやすくなる
- 血管運動神経症状が現れやすくなる
- 精神的な不調を感じやすくなる
- デリケートゾーンの不快症状が増えてくる
- 疲労感や体のだるさが続くようになる
- 閉経後に起こる体の変化と注意点
- ホルモンバランスの乱れが続いていく
- 脂質や血圧の変化に注意が必要になる
- 骨や筋肉の衰えが加速しやすくなる
- 閉経と更年期の関係とは?女性の身体に起こる長期的な影響
- 更年期に起こる主な症状
- のぼせ・ほてり・発汗が起こりやすくなる
- 疲れやすさや頭痛など体の不調が増えてくる
- 気分の落ち込みやイライラを感じやすくなる
- 物忘れや集中力の低下が気になってくる
- 更年期の「うっかり」対策には「Rimenba」がおすすめ!
- 閉経による変化を正しく知って、これからの自分と向き合おう
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授

Webライター
岩城 裕大
閉経は何歳から?平均年齢と個人差について

閉経の時期は、多くの女性にとって気になるテーマの1つです。一般的には50歳前後といわれていますが、そのタイミングには個人差があります。
閉経の前後には、月経周期の乱れや体調の変化が現れることもあるため、自分の体のサインに目を向けることが大切です。ここでは、閉経の平均年齢や個人差について解説します。
日本人女性の閉経の平均年齢は50歳前後
日本人女性の閉経は、平均すると50歳前後に訪れるといわれています。医学的には「1年間、月経がまったく来ない状態」が続いたとき、閉経と判断されるのが一般的です。
閉経の前後には、ホルモンバランスの変化によって月経周期が乱れたり、経血量が増減したりすることがあります。
さらに、のぼせやほてり、イライラなどの「更年期症状」が現れる方も少なくありません。こうした体の変化は、閉経が近づいているサインでもあり、自分の心と体の状態を見直すタイミングともいえます。
40代前半〜50代後半まで個人差がある
閉経を迎える時期には個人差があり、早い方では40代前半、遅い方では50代後半になることもあります。この違いには、遺伝的な体質だけでなく、生活習慣やストレス、喫煙の有無など、さまざまな要因が関わっているといわれています。
そのため、「何歳で閉経するのか」を正確に予測するのは難しいものです。月経周期の乱れや、ほてり・イライラといった更年期のサインが見られたときは、体からのメッセージとして受け止め、日々の変化に目を向けることが大切です。
不安や気になる症状がある場合には、ひとりで抱え込まず、早めに医師に相談してみましょう。
閉経の前兆で見られる体と心の変化

閉経が近づくと、心や体にこれまでとは違う変化が現れはじめます。ここでは、閉経の前兆として見られる主な変化について詳しく解説します。
月経周期や経血量が乱れやすくなる
閉経が近づくと、最初に変化が現れやすいのが月経の周期や経血量です。
これまで規則正しくきていた月経が急に早まったり、逆に間隔が長くなったりと、リズムが崩れがちになります。さらに、経血量も少なくなったり、反対に多くなりすぎてナプキンでは対応しきれないほどになったりすることも。
こうした変化は、卵巣の機能が少しずつ衰え、女性ホルモンの分泌が不安定になることが主な原因です。なかには、数ヵ月間月経が止まり「閉経かな?」と思っていたら、再び月経が始まるケースもあります。
血管運動神経症状が現れやすくなる
閉経が近づくと、「血管運動神経症状」と呼ばれる体の変化も起こりやすくなります。代表的な症状には、のぼせやほてり、大量の発汗などがあり、日中はもちろん、寝ている間に寝汗をかいて眠りが浅くなることもあります。
これらは、女性ホルモンの分泌が減少することで、自律神経の働きが乱れ、体温調節がうまくできなくなるのが主な原因です。
「年齢のせいだから仕方ない」とつい我慢してしまう方も多いですが、症状がつらいときは早めに婦人科などで相談するのがおすすめです。
精神的な不調を感じやすくなる
閉経が近づくと、女性ホルモンの1つであるエストロゲンが急激に減少し、脳内の神経伝達物質にも影響を与えるといわれています。その結果、気分の浮き沈みや情緒不安定、不安感など、精神的な不調が現れやすくなるのです。
また、更年期は子どもの独立や親の介護といったライフイベントが重なる時期でもあります。これまで気にならなかったことが負担に感じられるなど、家庭や職場での人間関係にも影響を及ぼすケースも少なくありません。
デリケートゾーンの不快症状が増えてくる
「なんだか乾燥している気がする」「かゆみやニオイが気になるようになった」閉経が近づいてくると、デリケートゾーンにこうした不快な変化を感じる方は少なくありません。
その原因は、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が減少し、膣や外陰部の粘膜が薄くなってしまうこと。潤いを保ちにくくなった結果、刺激に弱くなり、ヒリヒリとした痛みやかぶれを引き起こすこともあります。
また、ホルモンの低下によって膣内の自浄作用も弱まり、環境バランスが崩れることで、違和感やトラブルが起きやすくなるのも特徴です。
「年齢のせいだから仕方ない」と放っておくと、症状が悪化して日常生活に支障をきたすケースもあるため要注意。気になる変化があれば、専用の保湿ケアを取り入れたり、婦人科に相談したりしましょう。
疲労感や体のだるさが続くようになる
閉経前の時期は、女性ホルモンの分泌が不安定になり、自律神経のバランスが乱れやすくなります。その結果、「しっかり寝ても疲れがとれない」「体が重だるい」といった慢性的な疲労感を感じる方が増えてきます。
このような「更年期疲労」は、ただの寝不足や疲れとは異なり、休息をとっても改善されにくいのが特徴です。免疫力も低下しやすく、風邪をひきやすくなったり、日常のちょっとした負荷でもぐったりしてしまうケースも少なくありません。
また、気力が湧かない・何となくやる気が出ないといった精神的な不調があらわれることもあり、心と体の両面に影響が出る可能性があります。
閉経後に起こる体の変化と注意点

閉経を迎えると、女性ホルモンの分泌が急激に減少し、心身にはさまざまな変化が現れるようになります。ここでは、閉経後に起こりやすい体の変化と、その注意点について詳しく解説します。
ホルモンバランスの乱れが続いていく
閉経後も女性ホルモンの分泌は低下したままで、ホルモンバランスの乱れはまだまだ続きます。
この変化に体がうまく順応できれば、少しずつ不調も落ち着いていきます。ただし、人によっては更年期特有の不定愁訴が長引くケースもあるため注意が必要です。
特に気をつけたいのが、女性ホルモン「エストロゲン」の急激な減少によって起こる心身の不調です。自律神経が乱れやすくなり、気分が落ち込みやすくなったり、冷えや疲れを感じたりといった変化が現れることがあります。
こうした体と心の変化は、加齢にともなう自然なものとはいえ、放置せずに向き合っていくことが大切です。生活習慣の見直しや、婦人科への相談など、自分に合ったケアを見つけることで、閉経後も健やかに過ごすためのサポートになります。
脂質や血圧の変化に注意が必要になる
閉経を迎えると、女性ホルモンの1つであるエストロゲンの分泌が急激に減少し、体のさまざまな機能に影響が出やすくなります。その1つが、脂質代謝や血圧のバランスです。
エストロゲンの減少により、悪玉コレステロール(LDL)が増えやすくなり、反対に善玉コレステロール(HDL)は減少。さらに中性脂肪も上昇しやすくなるため、脂質異常症や高血圧、動脈硬化などの生活習慣病リスクが高まってしまいます。
なかでも注意したいのが「動脈硬化」です。放っておくと心筋梗塞や脳卒中などの深刻な病気を引き起こすこともあり、自覚症状がないまま進行してしまうケースもあります。
骨や筋肉の衰えが加速しやすくなる
エストロゲンの減少により骨密度が下がりやすくなり、骨がもろくなることで、骨折や骨粗しょう症のリスクが高まります。特に、背骨や太ももの付け根などの骨折は、寝たきりにつながるおそれがあるため注意が必要です。
さらに、加齢によって筋肉量も減少しやすくなり、筋力が低下することで転倒のリスクも増えていきます。
こうした骨や筋肉の衰えを防ぐためには、カルシウムやビタミンDを意識してとること、ウォーキングやスクワットなどの適度な運動を習慣にすることが大切です。
閉経と更年期の関係とは?女性の身体に起こる長期的な影響

「閉経」とは、女性の月経が永久に止まることを指します。一般的には50歳前後に迎える方が多いとされていますが、閉経を挟んだ前後およそ10年間は「更年期」と呼ばれ、心や体にさまざまな変化が現れやすい時期でもあります。
この時期に注目したいのが、女性ホルモン「エストロゲン」の分泌の変化です。エストロゲンの量が急激に減少すると、自律神経のバランスが崩れ、のぼせ・ほてり・発汗・気分の浮き沈みなど、いわゆる「更年期症状」が現れることがあります。
こうした変化がいつ始まり、どのくらい続くのかには個人差が大きく、“ゆらぎ期”とも表現されることも。なかには、症状がほとんど出ない方もいれば、数年間悩まされる方もいらっしゃいます。
また、最近では閉経後も30年以上の人生が続くといわれており、更年期の過ごし方が、その後の健康状態や生活の質を左右すると考えられています。
更年期に起こる主な症状

更年期に入ると、ホルモンバランスの急激な変化によって、心や体にさまざまな不調が現れやすくなります。ここでは、更年期に見られる主な症状とその特徴について、具体的に解説します。
のぼせ・ほてり・発汗が起こりやすくなる
更年期を迎えると、多くの女性に現れやすいのが「のぼせ」や「ほてり」、「発汗」などの血管運動神経症状です。
症状は突然現れることが多く、顔が急に熱くなったり、上半身から汗が噴き出したりと、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。特に、人前での発汗や寝汗が続くと、精神的な負担や疲労感の蓄積につながることもあります。
こうした不快な変化には、通気性の良い服を選ぶ、携帯できる保冷グッズを活用するなど、身の回りの環境を工夫することで、ある程度の緩和が期待できます。さらに、深呼吸や腹式呼吸を取り入れることで、自律神経を整えるサポートにもつながります。
疲れやすさや頭痛など体の不調が増えてくる
更年期に差しかかると、しっかり眠ったはずなのに朝からだるさが抜けなかったり、日中も慢性的な疲労感が続いたりすることもあります。睡眠の質が低下しやすくなることで、回復力が落ちてしまうのです。
また、エストロゲンの減少は自律神経のバランスにも影響し、肩こりや頭痛、関節の痛みなどが現れやすくなるともいわれています。特に片頭痛や緊張型頭痛は、ホルモンバランスだけでなく、ストレスや血行不良、生活リズムの乱れなども関係していると考えられています。
こうした不調を軽くするためには、栄養バランスの良い食事やしっかりとした休息に加えて、ストレッチや入浴などで体をやさしくいたわることが大切です。
気分の落ち込みやイライラを感じやすくなる
更年期に入ると、エストロゲンの減少により脳内の神経伝達物質のバランスも崩れやすくなり、感情のコントロールが難しくなることがあります。
例えば、「些細なことでイライラする」「理由もなく気分が沈む」といった精神的な不調が続くことも少なくありません。さらに、睡眠の質が低下したり、疲れがとれにくくなったりすることで、気力ややる気が出ないと感じる方も多いです。
この時期は、仕事や家庭のことで忙しくなる年代と重なることもあり、ライフステージの変化が心の負担を強める原因になることもあります。
こうした変化に気づいたら、まずは心身を整える工夫を取り入れてみましょう。カウンセリングを活用したり、深呼吸やストレッチなどのリラクゼーションを取り入れることで、気持ちがラクになることもあります。
物忘れや集中力の低下が気になってくる
更年期に入ると、女性ホルモンの減少が脳の神経伝達物質や自律神経に影響を与えることで、記憶力や思考力の低下も起こりやすくなるといわれています。例えば、会話中に言葉が出てこなかったり、予定を忘れてしまったり、新しいことが覚えにくくなったりするケースも少なくありません。
また、不眠やストレスの蓄積も、集中力を下げる原因になります。
対策としては、脳の健康をサポートするDHAやイチョウ葉エキスなどの成分を意識的に摂取するのがおすすめです。最近では、これらの成分がバランス良く配合されたサプリメントもあるため、手軽に取り入れたい方は検討してみるとよいでしょう。
更年期の「うっかり」対策には「Rimenba」がおすすめ!

「会話中に言葉が出てこない」「予定をうっかり忘れてしまった」更年期に差しかかると、こうした物忘れや集中力の低下が気になる方も増えてきます。その背景には、女性ホルモンの減少にともなう脳内環境の変化が影響していると考えられています。
そこで注目されているのが、知的健康をサポートする成分をバランス良く配合したサプリメント「Rimenba(リメンバ)」です。
リメンバには、葉酸・DHA・プラズマローゲン・イチョウ葉エキスなど、記憶力や思考力の維持に役立つ栄養素が含まれています。これらの成分は、エイジングによって低下しやすい脳の機能をサポートしてくれる頼もしい存在です。
また、脳神経内科医の監修のもとで開発され、1日4粒を目安に手軽に続けられる仕様になっているのもポイント。さらに、製造はGMP認定工場で行われており、品質面でも安心です。
「最近うっかりが増えてきたかも……」と感じている方は、まずは栄養補給から見直してみませんか?生活の質を保ちつつ、更年期の“ゆらぎ”に備える選択肢として、「Rimenba」を取り入れてみるのもおすすめです。
閉経による変化を正しく知って、これからの自分と向き合おう

閉経は月経が終わるだけでなく、ホルモンバランスが大きく変わることで、心や体にさまざまな影響を与える大きなライフイベントの1つです。のぼせや発汗、気分の不安定さ、集中力の低下、さらには骨密度や代謝の変化など、その症状や現れ方には個人差があります。
「年齢のせい」と見過ごしてしまいがちですが、自分の体調や心の変化に目を向けることが、健やかな毎日への第一歩です。生活習慣を見直し、必要に応じて医師へ相談することで、更年期や閉経後の不調をやわらげることができます。
これからの人生を心地よく、自分らしく過ごしていくためにも、閉経による変化を前向きに受け止め、できることからケアを始めてみましょう。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授
【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター
岩城 裕大
SEO会社勤務を経て独立したWebライター。これまでに子育て・エンジニア・物流・EC運営など幅広いジャンルで、記事構成・執筆・運用を累計200本以上担当。実務に基づく確かな視点で、信頼性の高いコンテンツを届けることを大切にしています。
あなたへのおすすめ

知力健康
中性脂肪を下げる食べ物ランキング7選|おすすめのおつまみ・簡単レシピも紹介【管理栄養士監修】
「健康診断の結果で中性脂肪の数値が高かった」「お腹周りが気になってきた」というお悩...
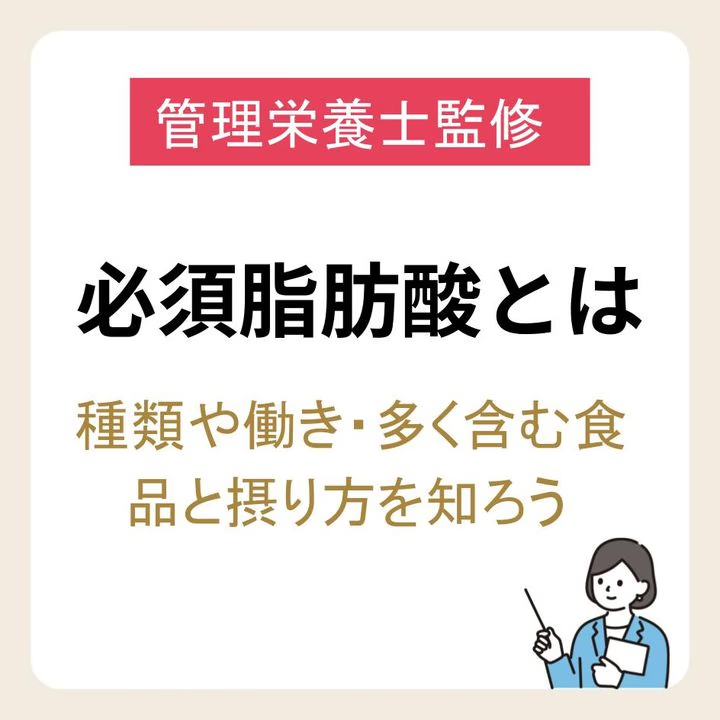
知力健康
【管理栄養士監修】必須脂肪酸とは?種類や働き・多く含む食品と摂取方法を知ろう
近年の健康意識への高まりとともに「必須脂肪酸」という言葉を耳にする機会も増えていま...
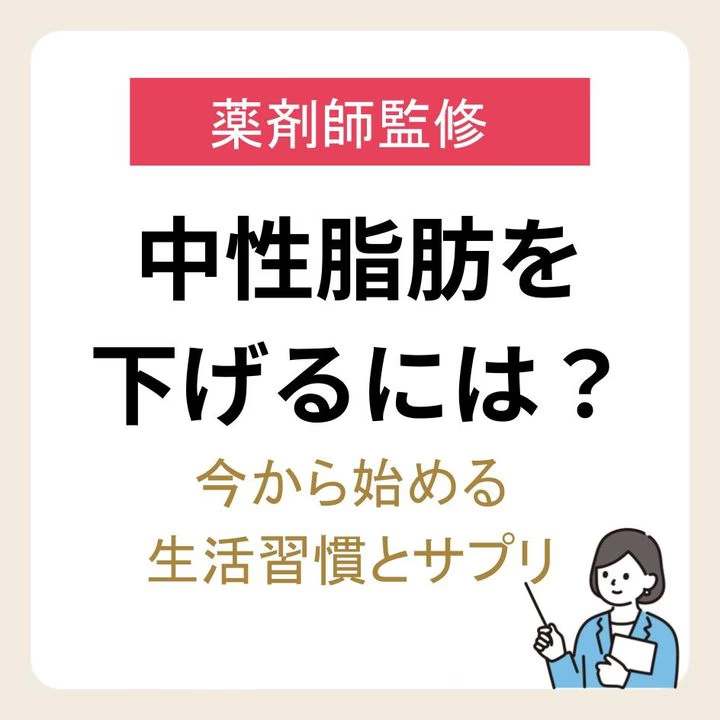
知力健康
【薬剤師監修】中性脂肪を下げるには?今から始める生活習慣とサプリ
健康診断で「中性脂肪がやや高め」と言われたものの、特に体調不良もなく、ついそのまま...