2025-11-19
まだら認知症とは?症状の特徴・原因・予防法をわかりやすく解説
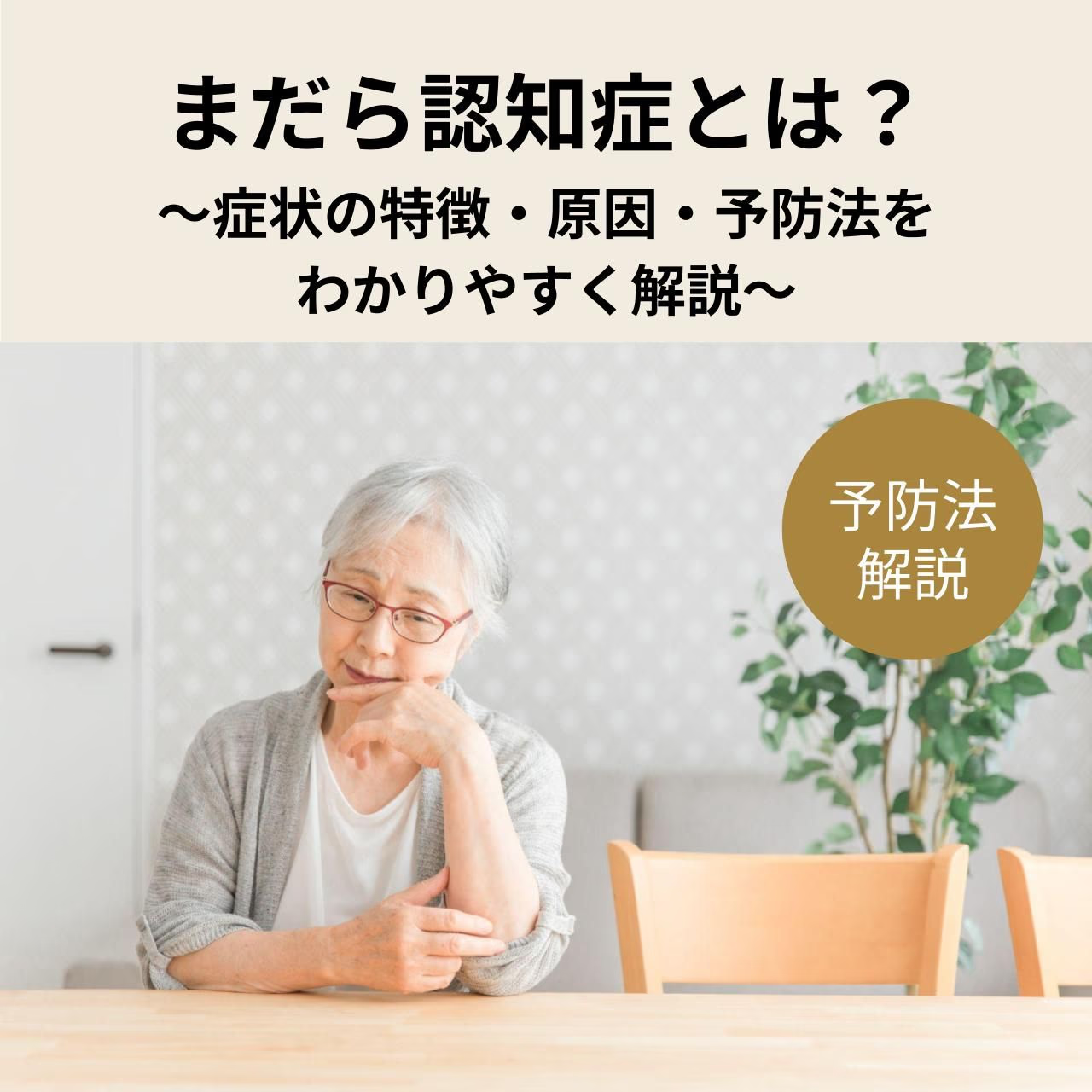
年齢を重ねるにつれて、「昨日できたことが今日はできない」といった変化に戸惑うことはありませんか。それは、脳血管性認知症にみられる「まだら認知症」の可能性があります。まだら認知症は、症状の現れ方にムラがあり、本人も家族も気づきにくいのが特徴です。
そこで今回は、まだら認知症の症状や原因、アルツハイマー型認知症との違いをわかりやすく解説します。早期対応に向けた予防策や治療法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授

Webライター
岩城 裕大
まだら認知症とは?

まだら認知症とは、日によって「できること」と「できないこと」にばらつきがみられる認知症を指します。正式な病名ではありませんが、脳血管性認知症の特徴的な傾向の1つです。
ここでは、まだら認知症の主な症状と、症状が一定でない原因について解説します。
まだら認知症の主な症状
まだら認知症は、症状にばらつきがみられるのが大きな特徴です。脳のどの部位が障害を受けたかによって現れる症状が異なり、意欲の低下や段取り力の低下(遂行機能障害)、感情のコントロールが難しくなるなどが代表例として挙げられます。
一方で、記憶力は衰えても、理解力や判断力が比較的保たれていることも珍しくありません。例えば、数分前に食事をしたことを忘れてしまう一方で、新聞を読んで内容をしっかり理解できる、といった矛盾するような行動がみられる場合もあります。
また、日や時間帯、体調によって「できること」と「できないこと」に大きな差が出るため、本人も家族も戸惑ってしまうこともあるでしょう。
まだら認知症の症状が一定でない原因
まだら認知症では、症状に大きな波がみられることがあります。その原因は、脳の損傷に偏りがあるためです。ダメージを受けた部分の働きが低下する一方で、別の機能は保たれることが多く、できることとできないことに差が出やすくなります。
加えて、脳の血流変化や自律神経の乱れも影響します。例えば、朝方や食後、体調が優れないときには血流が悪化し、症状が強まることがあります。さらに、便秘などの体調不良が重なると、一時的に認知機能が低下するケースもあります。
このように、脳の損傷だけでなく、血流や体調などさまざまな要因が絡み合うことで、日や時間帯によって症状の現れ方にばらつきが出るのが、まだら認知症の大きな特徴です。
まだら認知症の主な原因
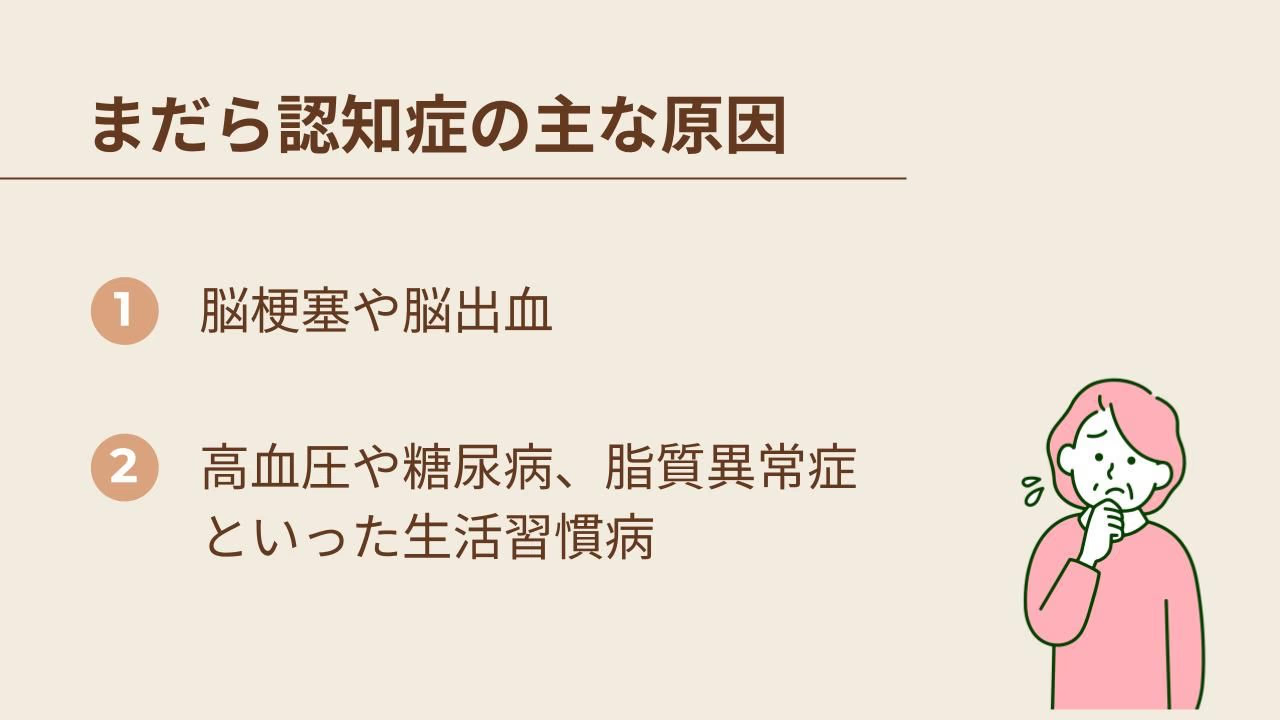
まだら認知症は、脳血管性認知症特有の症状の1つです。主な原因は、脳血管障害によって脳の機能が部分的に低下することにあります。脳梗塞や脳出血などによって、脳の特定の部位が損傷を受けると、損傷の場所に応じて認知機能にばらつきが生じるのです。
背景には、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病があり、血管を傷めることで脳の働きに影響を及ぼします。また、ラクナ梗塞と呼ばれる小さな脳梗塞も、まだら認知症を引き起こす要因の1つです。
まだら認知症とアルツハイマー型認知症の違い

まだら認知症とアルツハイマー型認知症には、症状の出方や進行の仕方にいくつかの違いがあります。
まだら認知症では、記憶力の低下はみられるものの、自分が病気であるという認識(病識)が残ることが多いといわれています。脳梗塞や脳出血などをきっかけに、症状が階段を上るように悪化する傾向があり、進行は比較的急激です。また、歩行や手足の動きといった運動機能にも障害が現れやすい点も特徴的です。
一方、アルツハイマー型認知症では、脳全体の機能がゆっくりと衰えていきます。本人に病気の自覚がないまま進行するケースが多く、症状の悪化も緩やかに進みます。記憶障害から始まり、やがて理解力や判断力にも影響が及ぶようになる点が、まだら認知症との大きな違いといえるでしょう。
まだら認知症の主な治療法2つ

まだら認知症の進行を抑え、生活の質を維持するためには、適切な治療が欠かせません。治療の基本は、脳血管障害の再発を防ぎながら、日常生活をできる限り自立して送るための支援にあります。ここでは、主に行われる2つの治療法についてご紹介します。
薬物療法
まだら認知症の治療では、脳血管障害の進行を防ぐことが重要な課題です。そのため、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病に対して、適切な薬物療法が行われます。脳梗塞や脳出血の再発を予防することが目的です。
また、意欲の低下や不安感、抑うつといった精神的な症状が現れることもあり、必要に応じて向精神薬や抗うつ薬が処方される場合もあります。薬物療法は、認知機能の低下を完全に止めることはできませんが、進行を遅らせ、生活の質を保つうえで大きな助けとなります。
ただし、薬には副作用のリスクも伴うため、医師と相談しながら慎重に使うことが欠かせません。薬を上手に取り入れることで、本人が落ち着いた日々を送れるようになることはもちろん、支える家族の負担軽減も期待できます。
リハビリテーション
まだら認知症におけるリハビリテーションは、身体機能や生活能力の維持を目指して行われます。例えば、脳血管障害によって片麻痺や言語障害が現れた場合には、専門的なリハビリを取り入れ、動作の回復や言語機能の維持を図ります。
リハビリ内容は、本人が得意とする活動や、もともと興味を持っていたことを活かして組み立てるのが効果的です。好きな作業を通じて自信を取り戻せれば、意欲の向上にもつながります。
ただし、リハビリを行う際は精神的に安定している時期を選び、無理に進めないことが大切です。焦らず本人のペースに寄り添うことで、心身への負担を軽減でき、結果として生活の質(QOL)を保ちやすくなります。
リハビリを通じて「できること」を伸ばし、少しずつでも日常生活を自立的に営めるよう支援していきましょう。
まだら認知症を予防する方法はある?
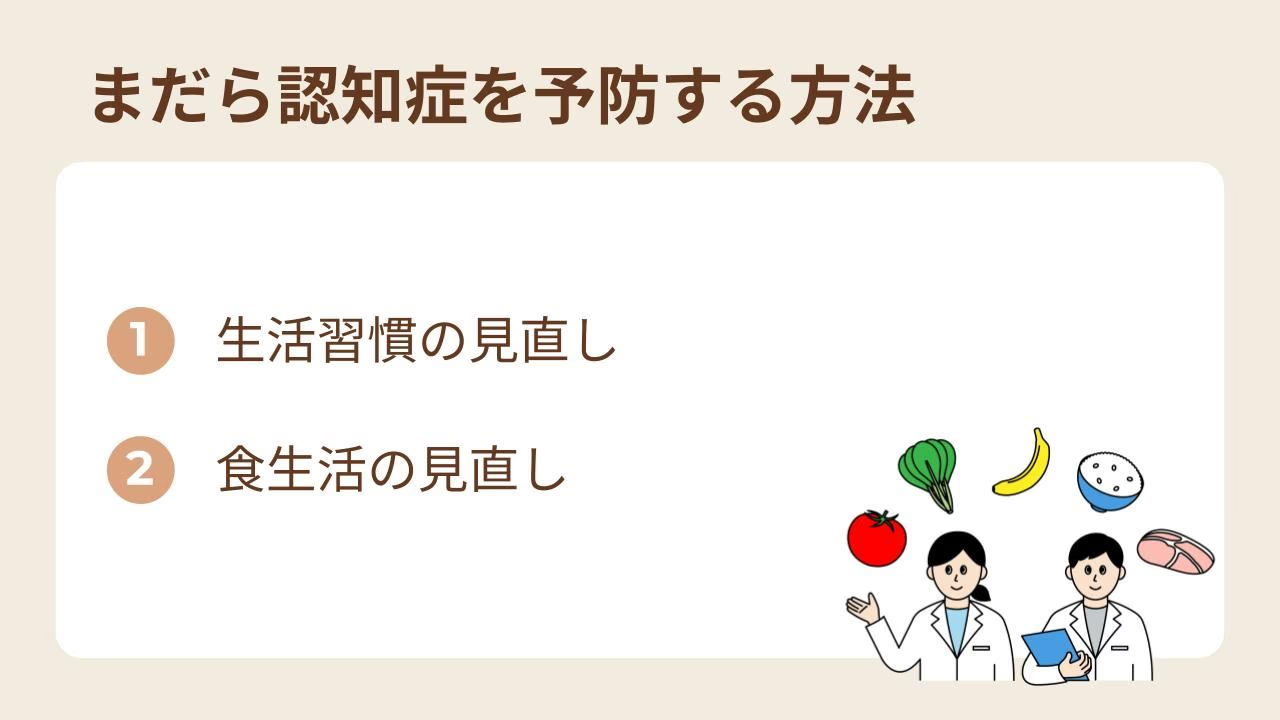
まだら認知症は一度発症すると完治が難しいため、日常生活の中でリスクを減らす取り組みが大切です。特に、脳血管障害の予防を意識した生活習慣の改善が重要とされています。ここでは、日々の生活に取り入れられる具体的な2つの対策をご紹介します。
生活習慣の見直し
まだら認知症を防ぐには、まず血管の健康を守る生活を心がけることが大切です。特に、高血圧や糖尿病、肥満といった生活習慣病は、脳の血流を悪化させる原因になりかねません。毎日の食事や運動を見直し、無理なく続けられる健康管理を意識しましょう。
また、タバコは血管を収縮させ、動脈硬化を進めるおそれがあるため、禁煙に取り組むだけでも脳血管への負担を減らせる可能性があります。飲酒についても、適量を守ることが重要です。ときには「休肝日」を設けるなど、メリハリのある飲酒習慣を心がけるとよいでしょう。
さらに、十分な睡眠や休養をとり、ストレスをため込みすぎない生活を意識することも、脳の健康維持には欠かせません。小さな積み重ねが、脳の血流を良好に保ち、まだら認知症のリスクを低下させることにつながります。
食生活の見直し
まだら認知症を予防するためには、日々の食生活から血管の健康を意識することも大切です。特に注意したいのは、塩分の摂りすぎです。塩分を控えめにし、代わりにカリウムを豊富に含む野菜や果物を積極的に取り入れると、体内のナトリウム排出が促され、血圧の上昇を防ぐ効果が期待できます。
また、カロリーや糖質の過剰な摂取は動脈硬化を進める原因となり、脳血管のダメージを招きやすくなります。和食中心の食事を心がけるほか、オリーブオイルや魚介類を多く取り入れた地中海式の食事スタイルもおすすめです。
あわせて、脳の健康維持を支える栄養素にも注目しましょう。例えば、ビタミンB群は神経機能の正常化を助け、DHA・EPAは脳の神経細胞を保護し、認知機能をサポートする働きがあります。魚やナッツ類、緑黄色野菜などから摂取できますが、食事だけで必要量をまかなうのが難しい場合は、サプリメントの活用も選択肢の1つです。
一度にすべてを変えるのは難しいかもしれませんが、できることから少しずつ取り入れていくことが、無理なく食生活を改善するコツです。
まだら認知症への理解を深め健康維持を目指そう

まだら認知症の予防には、日々の生活習慣と食生活の見直しが欠かせません。主な原因である脳血管障害を防ぐためには、血圧・血糖・脂質の適切な管理を意識し、バランスのとれた食事や適度な運動を心がけることが大切です。
また、高齢になると水分不足による血流悪化も起こりやすいため、こまめな水分補給も意識しましょう。こうした日常的な取り組みの積み重ねが、将来の認知機能を守ることにつながります。できることから少しずつ取り入れ、心身の健康維持を目指していきましょう。
不足しがちな栄養素を手軽に摂取するなら「Rimenba」がおすすめ

まだら認知症の予防には、生活習慣の見直しとともに、日々の栄養補給も大切です。しかし、食事だけでビタミンB群やDHA・EPAといった脳の健康を支える成分を十分に摂取するのは、なかなか難しいのが現実です。
「栄養不足が気になる」「いつまでもイキイキとした生活を送りたい」という方は、ぜひオールインワンサプリメント「Rimenba」をお試しください。
Rimenbaには、知的健康の維持に必要な栄養素が20種類以上含まれています。1日たったの4粒で、重要栄養素をすべてカバーし、不足しがちな栄養素も手軽にまとめて補うことができるのが魅力です。
また、専門医の監修を受けて設計されており、国内のGMP認定工場で製造されているため、品質管理体制にも配慮。特に、認知機能を少しでも維持したいと考えている方や、ご家族の健康維持を願う方におすすめです。
日常生活に無理なく取り入れ、将来のリスクに備えましょう。詳しくはRimenba公式サイトをご確認ください。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授
【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター
岩城 裕大
SEO会社勤務を経て独立したWebライター。これまでに子育て・エンジニア・物流・EC運営など幅広いジャンルで、記事構成・執筆・運用を累計200本以上担当。実務に基づく確かな視点で、信頼性の高いコンテンツを届けることを大切にしています。
あなたへのおすすめ

知力健康
中性脂肪を下げる食べ物ランキング7選|おすすめのおつまみ・簡単レシピも紹介【管理栄養士監修】
「健康診断の結果で中性脂肪の数値が高かった」「お腹周りが気になってきた」というお悩...
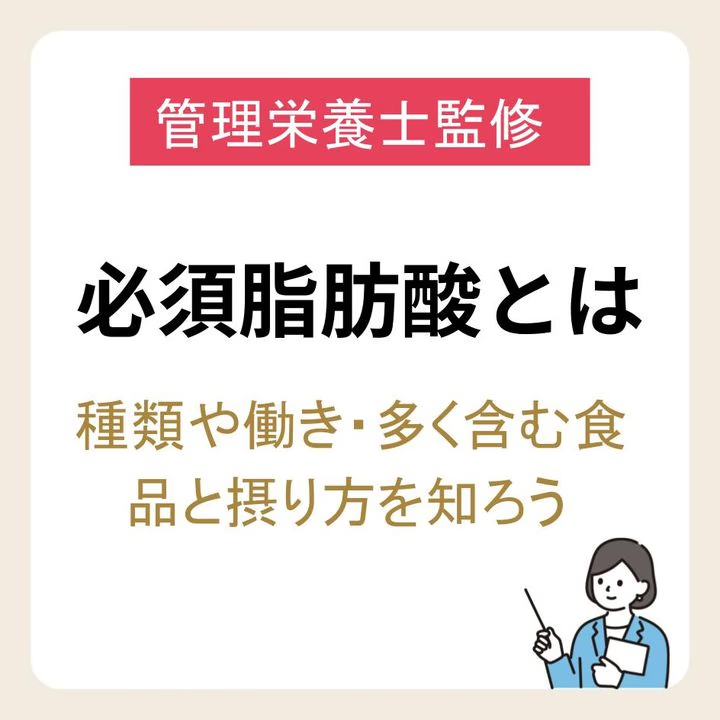
知力健康
【管理栄養士監修】必須脂肪酸とは?種類や働き・多く含む食品と摂取方法を知ろう
近年の健康意識への高まりとともに「必須脂肪酸」という言葉を耳にする機会も増えていま...
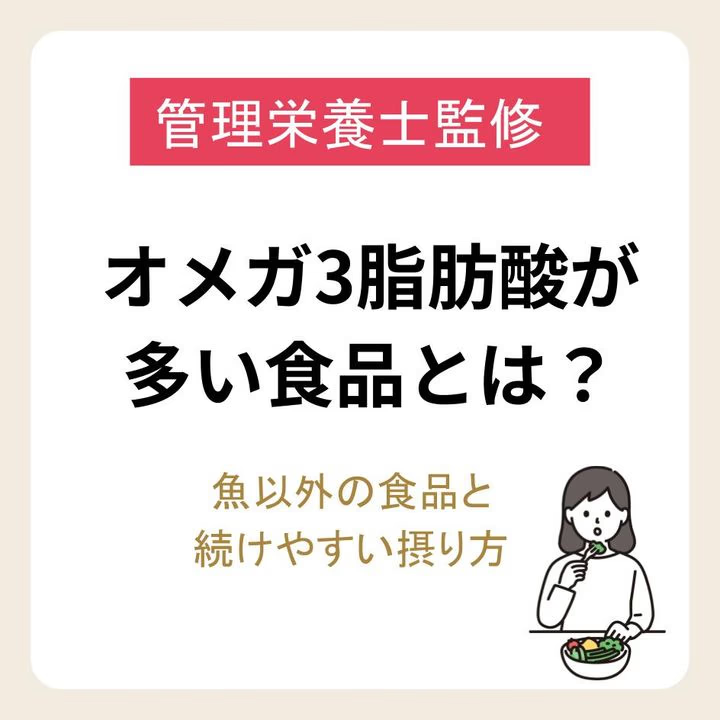
知力健康
【管理栄養士監修】オメガ3脂肪酸が多い食品とは?魚以外の食品や続けやすい摂り方を解説
「オメガ3脂肪酸が多い食品って、どんなものを選べばいいの?」「魚をあまり食べないけ...










