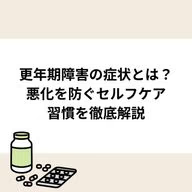2025-11-19
ホットフラッシュの原因・対処法とは?おすすめのサプリや選び方も紹介
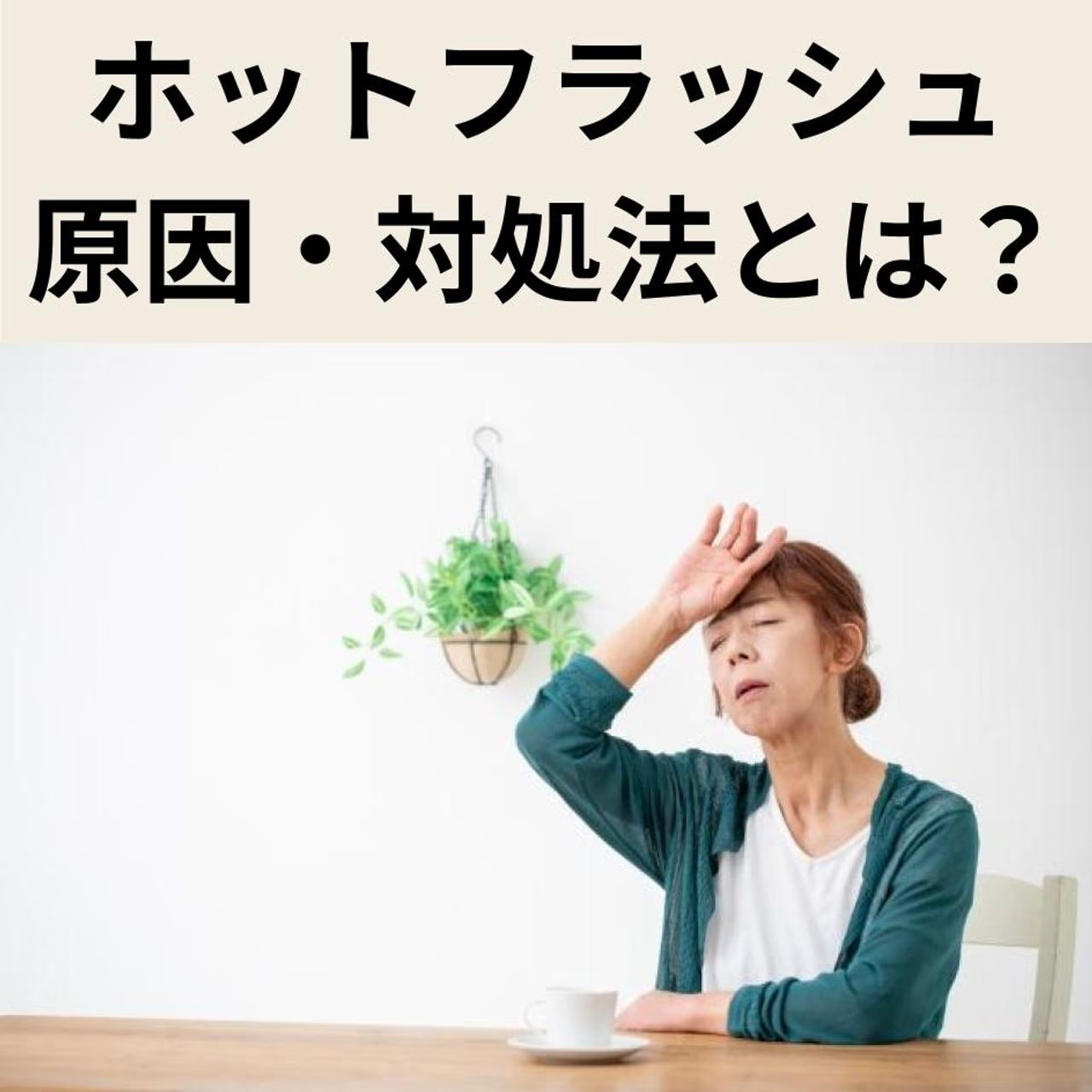
「ホットフラッシュの原因や治し方は何がある?」
「汗や暑さが急にきたときの対処法を知りたい」
このようなお悩みはありませんか?
突然顔がほてって汗が噴き出す「ホットフラッシュ」は、更年期障害に見られる症状のひとつです。「周りは涼しいのに、自分だけ暑くてつらい」と感じており、なんとか対策がしたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ホットフラッシュの症状や原因、実際にできる対処法をわかりやすく解説します。更年期の変化とうまく付き合い、少しでも快適に毎日を過ごしたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
- ホットフラッシュとは?
- 原因とメカニズム
- いつまで続く?ピークは?
- ホットフラッシュの他に見られる更年期症状
- ホットフラッシュがきたときの対処法
- 方法1:腹式呼吸をする
- 方法2:ツボ押しをする
- 方法3:アロマを焚く
- 方法4:要因を避ける
- 女性ホルモンや自律神経を整える方法
- 栄養バランスが整った食事を心がける
- 質のいい睡眠をとる
- 適度な運動でストレスを発散する
- アルコールや刺激物をなるべく控える
- 栄養素の摂取にはサプリメントの活用がおすすめ!
- サプリメントの選び方
- 医師・専門家の監修が入ったサプリを選ぶ
- 幅広いサポート成分が入ったサプリを選ぶ
- コスパがいいサプリを選ぶ
- GMP認定工場で製造されたサプリを選ぶ
- 更年期以降のお悩みのサポートにはオールインワンサプリ「Rimenba」
- 生活習慣を見直してホットフラッシュの緩和を目指そう
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授

Webライター
のん
- 薬膳調整士
- 漢方コーディネーター
- 化粧品3級
ホットフラッシュとは?

ホットフラッシュとは、更年期障害の代表的な症状のひとつです。閉経前の時期から症状を訴える方が多く、約6割の女性がホットフラッシュを経験するといわれています。また稀に、重度の症状がみられる場合があり、日常生活がままらないほどになる方もいます。
特徴的なのが、突然、身体全体のほてりや発汗、動悸の症状がみられる点です。環境の気温は関係なく、涼しい部屋であっても急に暑さやのぼせを感じます。
なお、一般的に症状の発現時間は2〜4分間と非常に短時間です。ただし個人差があり、中には30分程度経っても症状が治らない方もいます。
原因とメカニズム
ホットフラッシュは血管運動に異常をきたして現れます。血管運動に異常をきたす原因は「自律神経のバランスの乱れ」です。自律神経には血管の拡張や収縮をコントロールする役割があります。
女性ホルモンと自律神経には密接な関係があるのをご存知でしょうか。脳には「視床下部」と呼ばれる中枢神経があり、女性ホルモンと自律神経のコントロールを担っています。
その視床下部が、更年期になり女性ホルモンが急速に減少したことで混乱してしまい、自律神経の体温調節機能がうまく働かず、ホットフラッシュを起こすのです。
いつまで続く?ピークは?
更年期は、閉経前5年間と閉経後5年間と合わせた10年間のことを指します。更年期は女性ホルモンの分泌量が急激に下がるため、10年間ホットフラッシュが続くこともあります。
症状がピークに達するのは、閉経1年後です。1年経過してからは次第に発症する頻度がおさまっていきます。ただし、少数ではあるものの60~65歳になってもホットフラッシュが見られる方も。中等度以上の症状に悩まされ、治療を必要とする場合もあるため、様子を見る必要があります。
なお、ホットフラッシュの症状の出方は個人差が大きいため、一般的な発現時期に当てはまらないケースも少なくありません。一般的にいわれている発現時期やピークよりも長いと感じた場合は、医療機関に相談しましょう。
ホットフラッシュの他に見られる更年期症状

ホットフラッシュが疑われる場合は、その他に更年期症状があるか確認しましょう。その他の更年期症状がみられない場合、自律神経失調症や甲状腺疾患など、別に原因があるかもしれません。
【精神症状】
- 不安感
- イライラ
- 気分の落ち込み
【身体症状】
- 頭痛
- めまい
- 吐き気
- 冷え性
- 肩こり
- 関節痛
- 動悸
【睡眠障害】
- 夜間発汗
- 中途覚醒
このように、ホルモンバランスが乱れると、身体症状だけでなくメンタル面においても不調を感じることが多くなります。上記のような症状も併せてみられる場合は、更年期症状が原因である可能性があるため、これからお伝えする対処法を実践していきましょう。
ホットフラッシュがきたときの対処法

ここでは、ホットフラッシュがきたときの対処法を4つお伝えします。外出先でもできる対策もありますので、ぜひ参考にしてください。
方法1:腹式呼吸をする
ほてりや発汗がツラいときは、腹式呼吸をしてみましょう。腹式呼吸には副交感神経を優位にして血管を拡張させたり、心身をリラックスさせたりする効果があります。
【腹式呼吸の方法】
- 楽な姿勢で横になるか座る
- お腹の動きに集中できるようにお腹に手を当てる
- ゆっくりと鼻から息を吸いながらお腹を膨らませる
- 息を口から吐きながらお腹を徐々に凹ませる
- 3と4の動きをしばらく繰り返し、症状や心が落ち着いたのを感じたら止める
初めてする方は、仰向けの姿勢でするのがおすすめです。仰向けの姿勢は自ずと腹式呼吸になるため、やり方のコツを得られやすくなります。
方法2:ツボ押しをする
副交感神経を優位にしてホットフラッシュの症状を落ち着かせたい場合は、ツボ押しもおすすめです。身体の至るところに「ツボ」と呼ばれる、刺激すると健康効果をもたらすとされる箇所が存在しています。
ホットフラッシュに効果的だとされるツボは以下のとおりです。
- 中渚(チュウショ):手を握ったときに手の小指と薬指の間で凹む箇所
- 神門(シンモン):手首の内側にあるツボ。小指側にある手首のシワのすぐ上にある
- 合谷(コウゴク):親指と人差し指の骨が交わる、手の甲のくぼみにあるツボ
Check
【ツボ押しの方法】
ツボ押しは、指の腹で行うのが基本です。指の腹で押したり、押しながら円を描くようにマッサージしたりしましょう。
なお、ツボ押しは”力加減”が大切です。徐々に力を加えて「痛いけれど気持ちがいい」と感じる力加減で行いましょう。
方法3:アロマを焚く
アロマやお香といった、香りが好きな方はアロマを焚くのもおすすめです。アロマの香りには種類によってさまざまな効果があります。選ぶべきアロマの種類は、リラックス効果・鎮静効果があるものです。例えば、ラベンダー、ヒノキ、カモミール、サンダルウッド、フランキンセンスがあります。
アロマは精油と呼ばれるアイテムで販売されていることが多く、小さな瓶に入っているのが一般的です。入浴時に1滴程度垂らしたり、ディフューザーを使ったり、お香に火をつけたりといった方法で楽しめます。仕事やお買い物などの外出時には、アロマ垂らしたハンカチを持ち歩くのもおすすめです。
方法4:要因を避ける
ホットフラッシュの要因を避けることも、症状の軽減に役立ちます。方法は2つあります。
一つ目は、体温調節を行うための環境を整えることです。まずは、通気性のよいコットン生地の衣服や半袖・半ズボンで肌を出した服装に着替えます。エアコンのある部屋があれば、冷房をつけて涼みましょう。
二つ目は、体温の上昇や発汗の原因となる食べ物を避けます。カレーや唐辛子を使った激辛料理などの刺激物は、より体温を上げてホットフラッシュを助長させる要因とされるため、注意が必要です。
女性ホルモンや自律神経を整える方法

ホットフラッシュの緩和には、女性ホルモンや自律神経のバランスを整えることが欠かせません。これから4つの方法をお伝えするので、できることから始めてみましょう。
- 1栄養バランスが整った食事を心がける
- 2質のいい睡眠をとる
- 3適度な運動でストレスを発散する
- 4アルコールや刺激物をなるべく控える
栄養バランスが整った食事を心がける
栄養バランスの偏りは、ホルモンの分泌に関わる栄養素の不足や大きな体重の変動で、ホルモンバランスが崩れる要因です。五大栄養素を意識した食事を心がけましょう。
タンパク質
植物性タンパク質、動物性タンパク質をバランスよく摂りましょう。大豆食品や肉類を取り入れるほか、プロテインも活用するとよいでしょう。
脂質
魚類から得られる良質な脂質を選びましょう。良質な脂質は過剰なカロリー摂取を抑え、青魚に多く含まれるオメガ脂肪酸は認知症予防などの健康効果も期待できます。
炭水化物
白米から摂取しましょう。白米のでんぷんはアミラーゼによりブドウ糖に変換され、効率的に活動エネルギーを得られます。
ビタミン類
野菜類やフルーツ類から摂取可能です。食事にサラダを付け足したり、食後のデザートや間食にフルーツを取り入れたりしましょう。
ミネラル
海藻類や魚介類、野菜、乳製品などから摂取可能です。血液や唾液などの体液の調節を行ったり、骨や歯を作ったりするために欠かせない栄養素です。
質のいい睡眠をとる
質のいい睡眠は、ホルモンバランスや自律神経のバランスを整えます。
まずは、睡眠時間を確保しましょう。人によって必要な睡眠時間は異なりますが、一般的には6〜8時間以内が最適とされています。日中眠気を感じない、もしくは朝スッキリと目覚められる時間を知ることから始めましょう。
次に、睡眠の質を高めることを考えましょう。そのためには、寝室や寝具を快適と感じる状態に変え、就寝前に心身がリラックスモードに入るような過ごし方を意識することが大切です。
適度な運動でストレスを発散する
適度な運動は、ホルモンバランスや自律神経のバランスを整えるのに役立ちます。運動には、運動後に副交感神経を優位にさせたり、ストレスを発散させたりする作用があります。
おすすめの運動は、ウォーキングやヨガ、ストレッチなどの軽い運動です。ランニングや水泳といった激しい運動は、かえって交感神経を優位にさせます。
運動が苦手な方は、まず散歩からスタートしてみましょう。散歩であれば、運動に慣れていない方でも少ない身体への負担で運動できます。
また、運動には更年期症状の軽減だけでなく、心疾患リスクの低下などの健康効果も期待されています。日々の健康を維持するためにも、ぜひ運動習慣を作ってみましょう。
アルコールや刺激物をなるべく控える
ホットフラッシュに悩まされている方は、アルコールや刺激物を普段からなるべく控えるようにしましょう。アルコールや刺激物は、交感神経を優位にさせる作用があります。
刺激物に当たるのは以下のとおりです。
- コーヒー・紅茶といったカフェイン類
- 唐辛子に含まれるカプサイシン
- ショウガに含まれるジンガロール
- にんにくに含まれるアリシン など
血流を促すものや発汗を促す食べ物は、本来健康に良いものです。しかし、ホットフラッシュの症状がある場合には避けるのが無難です。
栄養素の摂取にはサプリメントの活用がおすすめ!

栄養バランスの整った食事は、ホルモンバランスを整えます。しかし中には「食事だけで栄養素を摂取するのは難しい」という方もいるでしょう。そのような方には、サプリメントの活用がおすすめです。メリットは主に2つあります。
一つ目は、手軽に栄養を補える点です。時間や場所を選ばず、いつでも不足しがちな栄養素を補えます。例えば、食事から摂りにくいビタミンやミネラル、特定の成分も簡単に取り入れることができます。
2つ目は、局所的もしくは幅広い健康サポートが可能な点です。例えば、更年期から減少する栄養素(カルシウム、ビタミンD、ビタミンB群、鉄分、亜鉛)を含むサプリや、女性ホルモンに似た作用の成分を含むサプリがあります。ピンポイントで必要な栄養素を摂取できるのは、サプリメントの強みです。
サプリメントの選び方

「サプリメントなら手軽に対策できていいかも?」と思っている方に向けて、サプリメントを選ぶコツをご紹介します。サプリメントは毎日飲むものですので、品質やコスパなどにこだわって選ぶことが大切です。
医師・専門家の監修が入ったサプリを選ぶ
医師や栄養の専門家が監修しているサプリメントは信頼性が高いといえます。専門的な知識に基づいた配合設計や成分がセレクトされているため、安心感があるでしょう。
確認方法としては、パッケージや公式サイトに「医師監修」「管理栄養士監修」などの表記があるかをチェックしましょう。監修者の氏名や経歴が明記されていると、より安心です。
健康にかかわるものだからこそ、専門家の視点が入った製品を選ぶようにしましょう。
幅広いサポート成分が入ったサプリを選ぶ
幅広いサポート成分が入っているサプリメントは、総合的な健康維持に役立ちます。単一成分だけでなく、複数の栄養素が組み合わされているものは、体内での吸収効率が考慮されていることもあります。
例えば、ビタミンCと鉄、ルテインとゼアキサンチンなど、相性の良い成分が一緒に含まれていると、相乗的なサポートが期待できます。疲労感・目の疲れ・肌荒れなど、複数の悩みがある方には特におすすめです。
気になる健康の内容に合わせて、複数の成分がバランスよく含まれたサプリメントを選びましょう。
コスパがいいサプリを選ぶ
サプリメントは毎日飲むものなので、無理なく続けられる価格かどうかも大切です。コスパがいいサプリメントとは、価格と内容量のバランスが取れているものを指します。
選ぶ際には、1日あたりのコストを計算してみましょう。例えば30日分で3,000円のサプリなら、1日あたり約100円です。加えて、1回に飲む量や1袋の中身も比較のポイントです。
ただし、安さだけに着目するのはおすすめしません。安かったとしても、成分の種類や含有量が少ないと複数のサプリを購入することになり、結果コストが高くなります。
長く続けるためにも、成分や含有量に納得できて価格にも無理がないサプリメントを選びましょう。
GMP認定工場で製造されたサプリを選ぶ
GMP認定工場とは「適正製造基準(Good Manufacturing Practice)」に基づいて製造管理や品質管理が行われている工場です。食品衛生や品質管理が徹底されており、一定以上の安全基準をクリアしています。
このような工場で製造されたサプリメントは、原料の受け入れから製造・出荷まで一貫した管理がされています。製品のばらつきが少なく、品質の安定性にもつながります。
信頼できる品質を求める方は、GMP認定を1つの基準にして選ぶとよいでしょう。GMP認定は、製品パッケージや公式サイトで確認できます。
更年期以降のお悩みのサポートにはオールインワンサプリ「Rimenba」

年齢を重ねると、肌・目・気分・疲れなど、一つだけでなく複数の不調を感じやすくなります。このような心身の変化に対し、個別のサプリメントを飲み分けるのは負担と感じる方もいるでしょう。更年期以降のお悩みを幅広くサポートできるサプリメントをお探しの方におすすめなのが「Rimenba」です。
Rimenbaは、医師監修のもと、40〜60代女性に多い「なんとなくの不調」を支えるオールインワンサプリメントです。成分の組み合わせにも工夫があり、単体で摂るよりも、複数の栄養素を一緒にとることで、相乗的にサポートする設計になっています。
以下は、Rimenbaに含まれる主な成分とその役割です。
| 栄養素 | 役割 |
|---|---|
| DHA・EPA | 脳の働きを助け、生活習慣病の予防に役立つ栄養素です。 |
| プラズマローゲン | 脳の疲れを防ぎ、軽減に寄与する重要な成分で、健やかな脳のために欠かせません。 |
| カルシウム | 骨や歯の健康を支えるだけでなく、更年期の女性の自律神経を整え、心の安定にもつながります。 |
| 鉄 | 体内で酵素の運搬や貯蔵に深く関係し、気分の落ち込みの緩和にも期待される栄養素です。 |
| 亜鉛 | 健康維持に必要な必須ミネラルの一つで、女性ホルモンの分泌を促進します。 |
| ビタミンE | ホルモンバランスの調整を助け、血液の流れを良くするため、更年期の女性に特に重要な成分です。 |
| ビタミンB群 | 自律神経の調整に関わり、単独ではなく複数の種類を一緒に摂ることで効果的に働きます。 |
| イチョウ葉エキス | 体の血行を整え、すっきりとした毎日を支えるサポート成分です。 |
| テアニン | 心を落ち着かせ、リラックスを促す効果が期待されています。 |
| 和漢素材 | ショウガや高麗人参などの和漢植物が、更年期を過ごす女性の健康的な生活を後押しします。 |
また、保存料・着色料・香料・酸味料・甘味料・増粘安定剤はすべて無添加です。毎日口にするものだからこそ、体へのやさしさを追求しています。また、国内のGMP認定工場で製造されており、品質や衛生面にも配慮されています。
このように、Rimenbaは複数の悩みに同時に取り組みたい方におすすめです。
生活習慣を見直してホットフラッシュの緩和を目指そう

ホットフラッシュは、女性ホルモンの減少によって起こる更年期の代表的な症状です。腹式呼吸やツボ押し、アロマなどの対処法に加え、栄養バランスの良い食事や質の良い睡眠、適度な運動が症状の緩和に役立ちます。必要に応じて、専門家監修のサプリメントを活用するのもおすすめです。
特に、複数の悩みに一度にアプローチできるオールインワンサプリ「Rimenba」は、40〜60代の女性に支持されています。毎日のセルフケアに取り入れて、より快適な毎日を目指しましょう。
Rimenbaについて詳しくはこちら
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授
【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター
のん
- 薬膳調整士
- 漢方コーディネーター
- 化粧品3級
娘と保護猫4匹と一緒に暮らすママライター。 さまざまな健康トラブルから「健康」を意識するようになり、漢方や薬膳の資格を取得。 漢方・薬膳・メイク・車系・ペット系など資格や趣味を活かして幅広く執筆。
あなたへのおすすめ

知力健康
中性脂肪を下げる食べ物ランキング7選|おすすめのおつまみ・簡単レシピも紹介【管理栄養士監修】
「健康診断の結果で中性脂肪の数値が高かった」「お腹周りが気になってきた」というお悩...
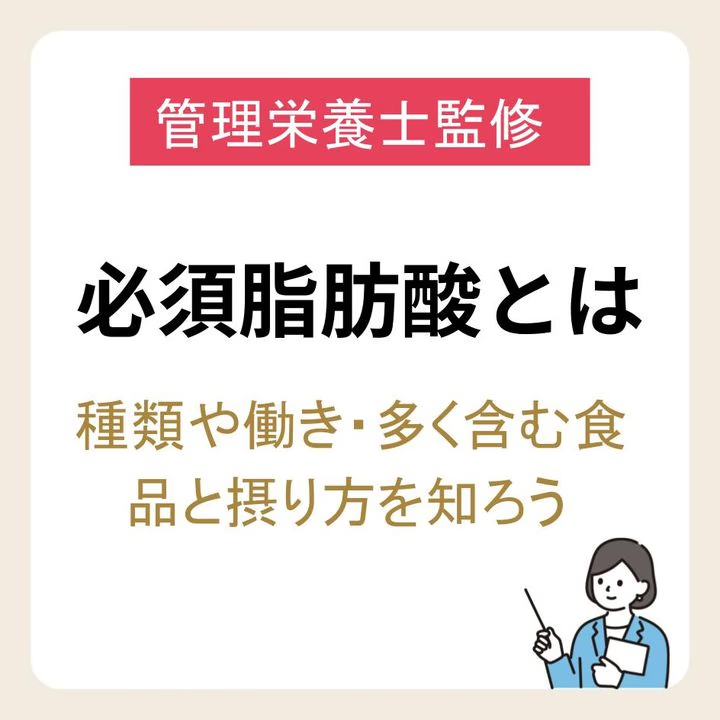
知力健康
【管理栄養士監修】必須脂肪酸とは?種類や働き・多く含む食品と摂取方法を知ろう
近年の健康意識への高まりとともに「必須脂肪酸」という言葉を耳にする機会も増えていま...
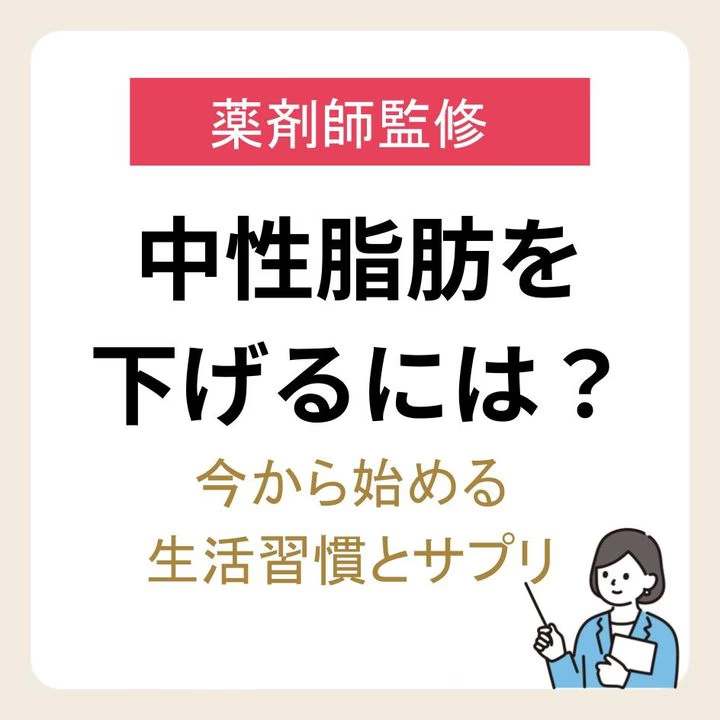
知力健康
【薬剤師監修】中性脂肪を下げるには?今から始める生活習慣とサプリ
健康診断で「中性脂肪がやや高め」と言われたものの、特に体調不良もなく、ついそのまま...