2025-11-21
【看護師監修】認知症の顔つきとは?特徴的な表情や初期の症状を解説
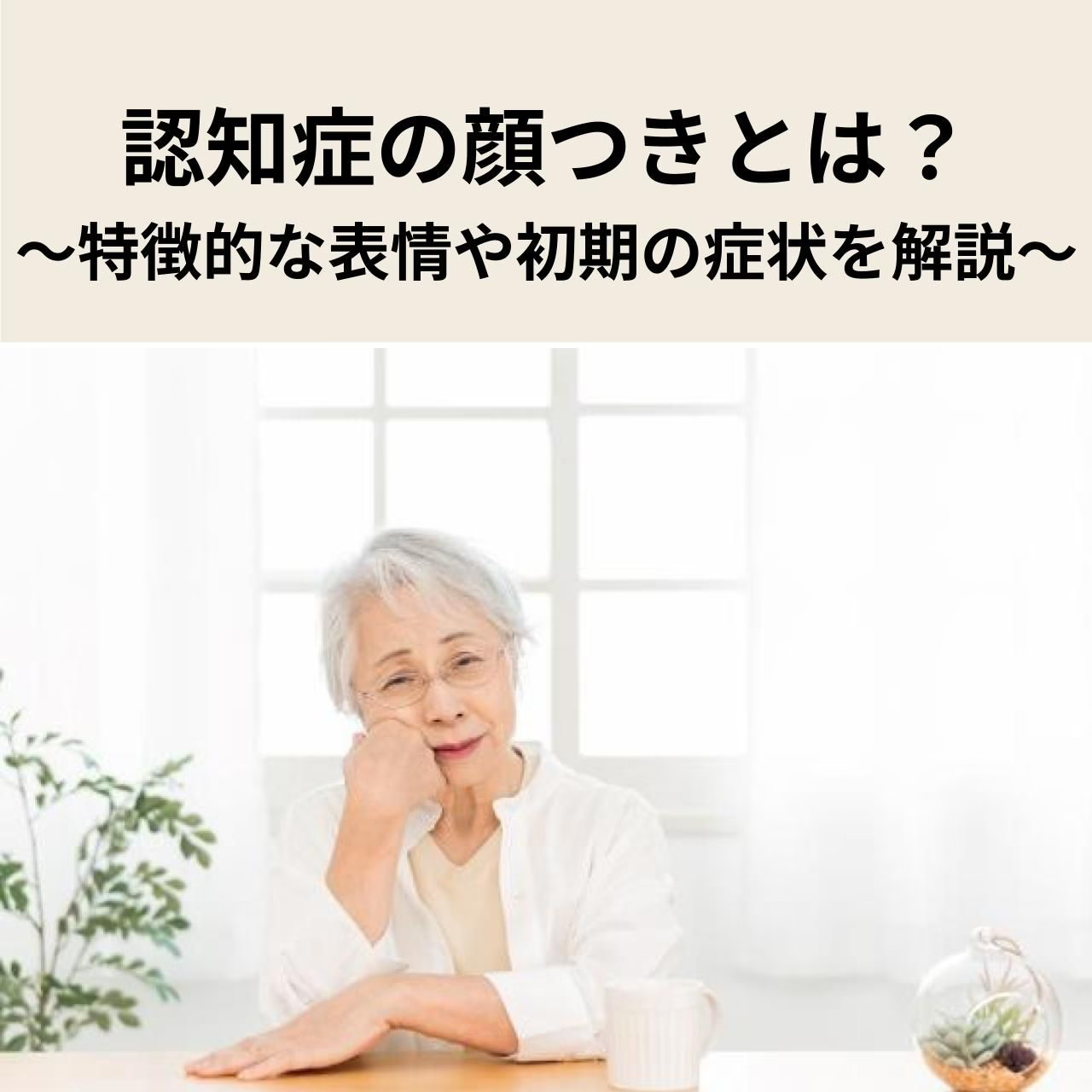
年齢を重ねたご家族をみて「最近、無表情なことが増えた」「険しい顔つきをしている」と感じることはないでしょうか。認知症の症状かもしれないと不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、認知症に特徴的な表情やその原因、対処方法について解説します。初期症状に気づけば、早期に対処することで、発症を予防したり、症状の進行を遅らせたりできる可能性があります。
表情以外にも、認知症初期に見られる症状や、認知症のリスクを軽減する方法について説明しています。ぜひ、家族の変化に気づき、長く健康で過ごすためにも参考にしてください。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授

看護師ライター
俵谷こころ
- 看護師
認知症の方にみられる顔つきや表情の特徴
 「顔つきの変化」は、認知症の初期から現れやすく、認知症を疑う重要なサインです。認知症と診断される前の軽度認知障害(MCI)でも見られることがあります。
「顔つきの変化」は、認知症の初期から現れやすく、認知症を疑う重要なサインです。認知症と診断される前の軽度認知障害(MCI)でも見られることがあります。
しかし、表情は急激に変化するものではなく、「年齢によるものかも」と見過ごされがちです。認知症の方に見られる顔つきや表情がどのようなものか、知っているだけでご家族が気づきやすくなるでしょう。
ここでは顔つきの変化や表情の特徴について解説しています。
ぼーっとしている、無表情など表情の変化がない
無表情で活気がなく、ぼーっとして表情を浮かべている場合、意欲や感情を司る脳の機能が低下しているかもしれません。
- 1テレビを見たり、家族と会話していたりしても反応が薄い
- 2冗談を言っても笑わない
- 3好きだったことに興味を示さない
- 4お孫さんが来ても以前のように喜ばない
このような様子が見られ、ご家族が違和感を覚える場合は、周囲への関心が薄くなっている可能性があります。
口角や眉が下がり悲しげな表情
認知症になると、判断能力や記憶能力が低下することで、今までできていたことができなくなり、日常生活での失敗が増えがちです。
「何をしたらいいかわからない」と口角や眉が下がった不安そうな顔つきがみられます。できなかったことに落ち込んで、悲しそうな表情になることがあります。
険しい目つきなど怒ったような表情
認知症になると怒りっぽくなるという話を聞いたことがある方も多いでしょう。これは、脳の機能が低下することで感情のコントロールが難しくなるためです。
状況を正しく理解できない、自身の考えや気持ちをうまく伝えられないなどでイライラしてしまうことが増えます。思い通りにならないことへの苛立ちなどで、目つきが険しくなり怒ったような表情に現れることもあります。
認知症によって顔つきが変わる原因とは?

認知症によって顔つきが変わる原因はさまざまで、脳の働きが低下するなどの身体的な変化だけではありません。落ち込みやすくなるなどの精神的な変化や刺激のない生活など環境的な影響もあります。
顔つきが変わる原因を理解することでより、認知症のリスクを軽減する対策や、症状への対処がしやすくなるでしょう。
脳の萎縮や筋肉のこわばりなどの身体的な変化
認知症では、脳の神経細胞が衰えることや脳そのものが萎縮することで、記憶障害、理解力や判断力の低下が生じます。
特に、感情を司る「前頭葉」や「側坐核(そくざかく)」が萎縮することで、快感を感じにくくなり、物事に対する関心が薄れることがあります。
側坐核は表情の制御にも関わる部位です。楽しいと感じても、表情筋を動かすための司令が伝わりにくくなることで、表情の変化が乏しくなるのです。
また、レビー小体型認知症やパーキンソン病を併発していると、筋肉が硬くなることで、表情筋が動かしにくく、無表情になりがちです。表情筋は使わないでいると、より衰えてしまいます。
アパシーや抑うつなどの精神的な変化
認知症になると、無関心・興味がなくなるなどのアパシーと呼ばれる状態になります。身体機能に問題がなくても、食事や着替えなどの日常生活の動作にさえ意欲がわかなくなることも。
アパシーがあると、1日中活動せずベッドで過ごすこともあり、体力の低下も懸念されます。
また、認知機能が低下することで、以前はできていたのにできなくなることや、日常生活で思い通りに行かないことが増えがちです。自信を失い落ち込むなど、二次的な症状として抑うつ状態(BPSD)に落ちいり、表情が変化することもあります。
単調な生活になるなどの環境による影響
脳への刺激が少ないと、神経細胞が減少して認知症が進行しやすくなります。高齢になると、仕事を退職したり、気力や体力の低下など身体的な制限から外出することが減ったりと、生活に変化が少なくなることもあるでしょう。
食事や入浴など日常生活を繰り返すだけになるとさらに脳への刺激が少なくなります。家族にしか会わない方や、独居で孤独感がある場合も、脳の機能が低下しやすくなる原因です。
顔つき以外の認知症の初期症状とは?

認知症の症状は顔つきだけではありません。話していることや行動からも認知症のサインを見つけることができます。
認知症と聞いて一番に思い浮かぶのは、記憶障害ではないでしょうか。認知症に限らず、誰しも年齢を重ねることで、どこに物を置いたかわからない、昨日の夕食を思い出せないといったことは起こり得ます。
ただし、常に探し物をしている、同じことを繰り返し話すといった物忘れの頻度が増えたときは注意が必要です。
加えて、認知症の初期症状には、以下のようなものもあります。
- 1テレビの内容が理解できない
- 2料理の手順がわからなくなる
- 3お金の管理ができなくなる
- 4慣れている道で迷う
また、認知症の進行により、衣服を着替えない、入浴しないなど自分の身の回りのことができなくなるケースもあります。
認知症のリスクを下げるための行動や対策は?

認知症が進行していると、病院を受診して治療を受ける必要があります。身の回りのことができなくなると介護サポートも必要です。
ただし、顔つきが気になるなど初期の段階の場合は、自宅で取り組める対策もあります。
ここでは、ご本人やご家族が始められる認知症を予防する、進行を遅らせるのにおすすめの方法をご紹介します。
表情筋のトレーニングを行う
認知機能の低下によって表情が乏しい場合は、顔を動かす表情のトレーニングを行ってみましょう。顔の筋肉を動かすことで血行が促進されてこわばった顔をほぐすだけでなく、顔面神経を刺激し、脳も活性化させる効果が期待されます。
顔を動かすだけでなく、声を出したり笑ったりすることで、ストレス軽減にもつながります。続けることで、筋肉が鍛えられ表情を作りやすくなり、表情が豊かになるでしょう。
手や指の体操などと組み合わせるとより効果的です。自宅でも簡単にできるので、動画などを参考にして家族と取り組むとよいでしょう。
社会的な交流を増やす

外出する機会が少なく自宅で過ごしていると、脳の刺激も少なくなります。地域の行事や自治会、ボランティアなど、外に出たり家族以外の人と交流できる場があるとよいでしょう。
音楽や囲碁などのゲーム、カラオケや散歩など、本人が楽しめるものを選ぶことで、脳も活性化されやすくなります。
他者と交流することでコミュニケーションの機会が増えるのもメリット。特に「笑う」「ほめる」といった行動は、ドーパミンが放出されて脳にもよいです。他者と交流すると、身だしなみにも気を使いやすくなります。
交流は、移動の面での負荷が少なく、足を運びやすいものがおすすめです。無理するのではなく、本人が取り組みやすいものや続けやすいものを探しましょう。
家族や周囲の人は本人の表情に合わせて接する

無表情で、何事にも関心が薄いようなら、あいさつなどでもよいのでこまめに声をかけるようにしましょう。認知症の方は、背後から話しかけられても気づかないことがあるので、目を見て話すようにします。過去の思い出や好きだったことを話すとより効果的です。
不安そうな表情のときは、穏やかな態度で本人が感じていることを受け入れて傾聴しましょう。
急かしたり、間違いを指摘したりすると自信をなくしてしまうこともあるので、本人のペースに合わせて、不安感を解消することが大事です。手を握るなどのスキンシップも効果的です。
怒っている表情が見られたときは、無理に接するよりも、なぜ怒っているのか不快に感じる理由などを冷静に聞くようにするとよいでしょう。
規則正しい生活を送る

認知症は進行すると体内時計の機能が低下して、昼夜逆転しやすくなります。
毎日同じ時間に起きて寝るなど規則正しい生活を送り、リズムを整えることが大切です。
出かけない日も洋服に着替え、午前中に日光を浴びて活動量を増やすとよいでしょう。適度に運動も取り入れると、全身の血流がよくなり、脳の酸素や血流不足を予防できます。
ただし、高齢者の運動はケガや事故のリスクもあるので、安全面での配慮が必要です。座ったままできるストレッチなど、手軽に始められるものから取り組みましょう。
バランスのよい食事を心がける
栄養素が欠如していると、認知症の原因となるアミロイドβの代謝や分解に影響することがあります。食事だけで、認知症を完全に防ぐことは難しいですが、必要な栄養素を補いリスクを下げることが大切です。
摂取カロリーを守り、塩分や糖質を摂りすぎないようにして、バランスのよい食事を心がけましょう。
脳や身体の細胞をつくるたんぱく質は、肉類から摂りすぎると脂質が過多になりやすいため、大豆製品や魚類を意識して摂取するのがおすすめです。
また、緑黄色野菜や果物に含まれるビタミンB群や、青魚に含まれるDHA・EPAなどの栄養素も脳の機能の維持に役立ちます。
食事で不足しがちな栄養素は、サプリメントを活用して補う方法もあります。
栄養サポートには「Rimenba(リメンバ)」がおすすめ

栄養サポートには、知的な健康の維持に役立つとされる栄養素が含まれているサプリメントを選ぶとよいでしょう。
おすすめしたいのは、脳神経内科医の監修したサプリメント「Rimenba(リメンバ)」です。

Rimenbaは、DHAやEPA、葉酸やテアニンなど、知的健康を維持する上で重要とされる栄養素が20種類以上含まれたオールインワンサプリメント。いくつもサプリメントを飲む必要がないので、忙しい方や高齢でたくさん飲むのが大変という方にもぴったりです。
また、品質面も考慮し、医薬品等の製造における品質管理基準を満たした、国内の有数のGMP認定工場で作られています。
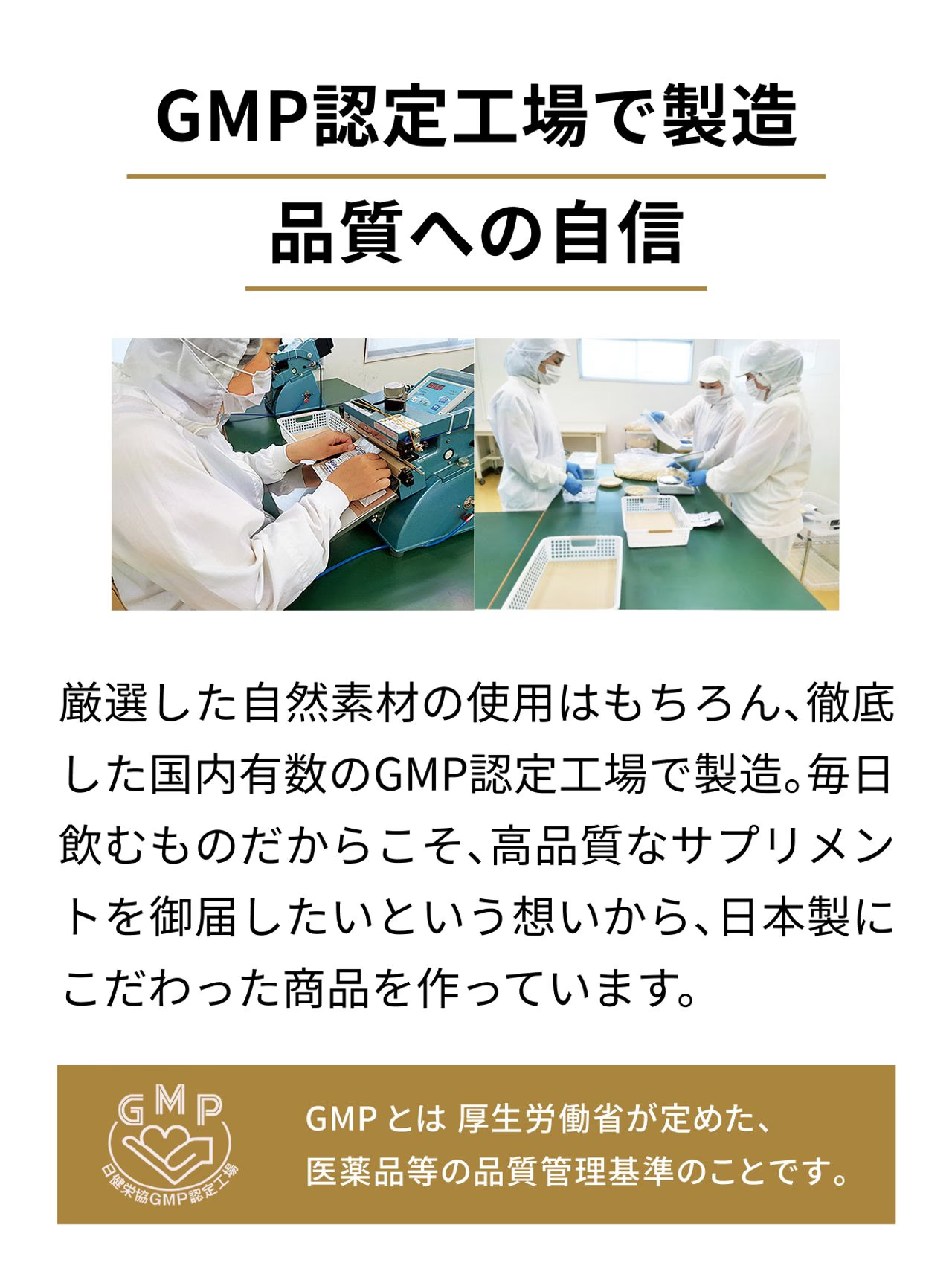
無理なく飲み続けられるように、お得な定期便がご利用いただけます。また、初回限定で特別価格をご用意していますので、ぜひこの機会にお試しください。
いつもと違うと感じたら早めの受診を

表情に変化が乏しい、険しい目つきをしているなど認知症かもしれないと思ったら、なるべく早く専門の病院を受診するようにしてください。脳神経内科・外科や精神科か、認知症の診断を専門的に行う「認知症外来」や「物忘れ外来」などを受診するとよいでしょう。
残念ながら認知症を完治する方法はありませんが、早めに気づいて適切に対処すると進行を遅らせることができるといわれています。
近年では、軽度の認知症の患者にも使用できる薬もあり、診断を受けることで利用できる介護なども広がります。
ただし、無理に受診しようとすると、「自分は認知症ではない」とご本人が尊厳を傷つけられたように感じられることもあるでしょう。かかりつけ医に相談したり、健康診断の受診を提案するのも一つの方法です。
健康的な生活を送り認知症のリスクを下げよう

認知症は、進行する前になるべく早く対策をするのが大切です。ご家族の顔つきや症状を見て、違和感を覚えるときはもちろん、全く症状がなくても若いうちから、知的な健康を維持できるように対策を行うとよいでしょう。
認知症の予防は40歳代から始めるとよいと言われています。睡眠、食事、運動などの生活を整えることで、認知症だけでなく、さまざまな病気のリスク低減を目指しましょう。
忙しい方は、日々の生活に取り入れやすいことから始めるのがおすすめです。サプリメントなら、ご家族と一緒に始められるため、ぜひこの機会にRimenbaをお試しください。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授
【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

看護師ライター
俵谷こころ
- 看護師
看護師として腎臓内科・呼吸器内科病棟勤務後、医薬品・医療機器関連のソリューション会社に勤務。2021年よりWEBライターとして活動。丁寧でわかりやすい記事の執筆を心掛けております。
あなたへのおすすめ

知力健康
中性脂肪を下げる食べ物ランキング7選|おすすめのおつまみ・簡単レシピも紹介【管理栄養士監修】
「健康診断の結果で中性脂肪の数値が高かった」「お腹周りが気になってきた」というお悩...
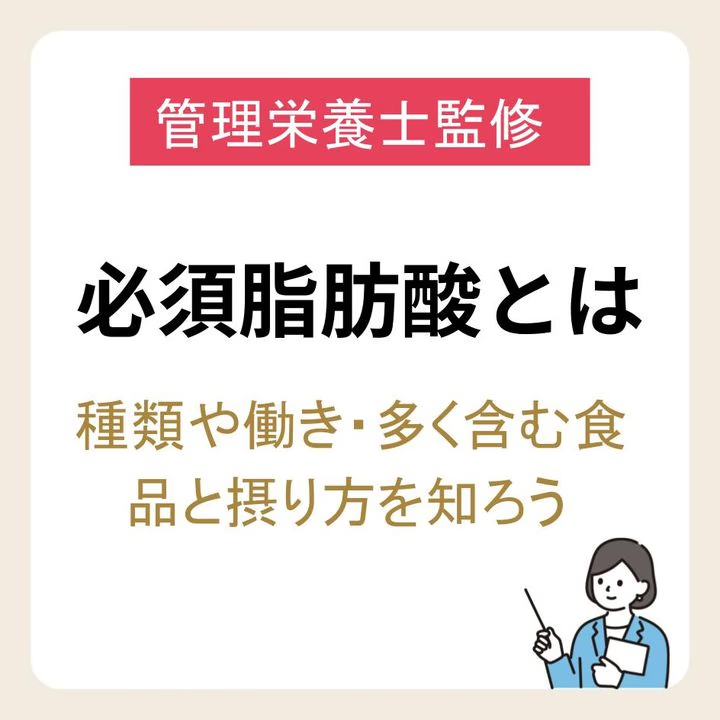
知力健康
【管理栄養士監修】必須脂肪酸とは?種類や働き・多く含む食品と摂取方法を知ろう
近年の健康意識への高まりとともに「必須脂肪酸」という言葉を耳にする機会も増えていま...
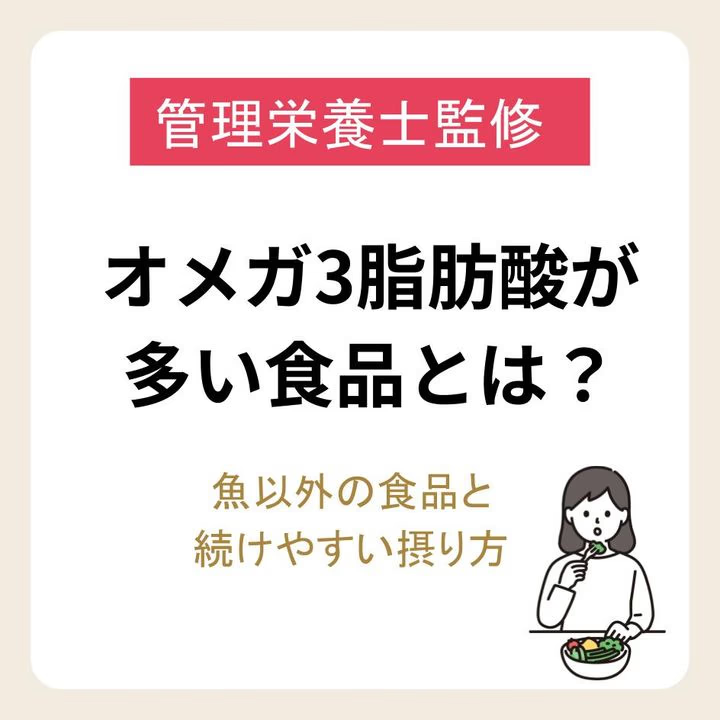
知力健康
【管理栄養士監修】オメガ3脂肪酸が多い食品とは?魚以外の食品や続けやすい摂り方を解説
「オメガ3脂肪酸が多い食品って、どんなものを選べばいいの?」「魚をあまり食べないけ...










