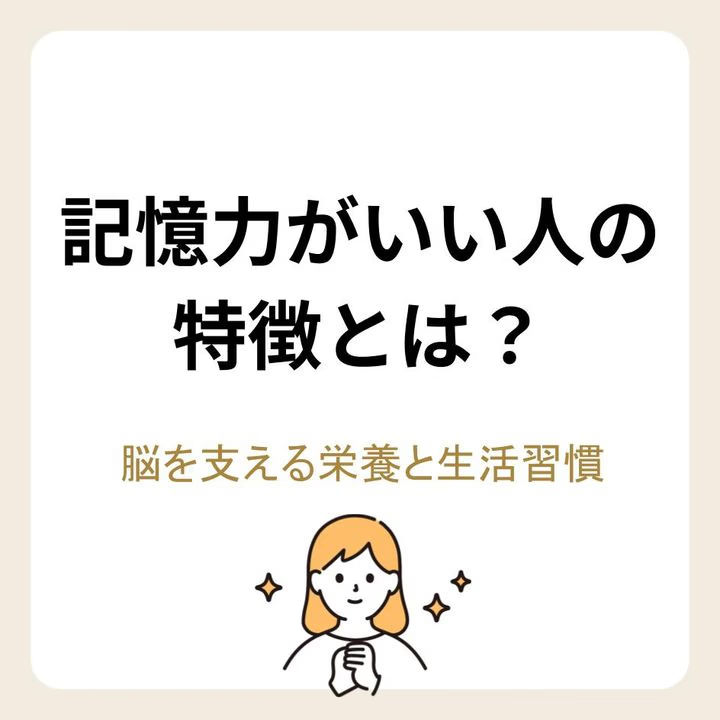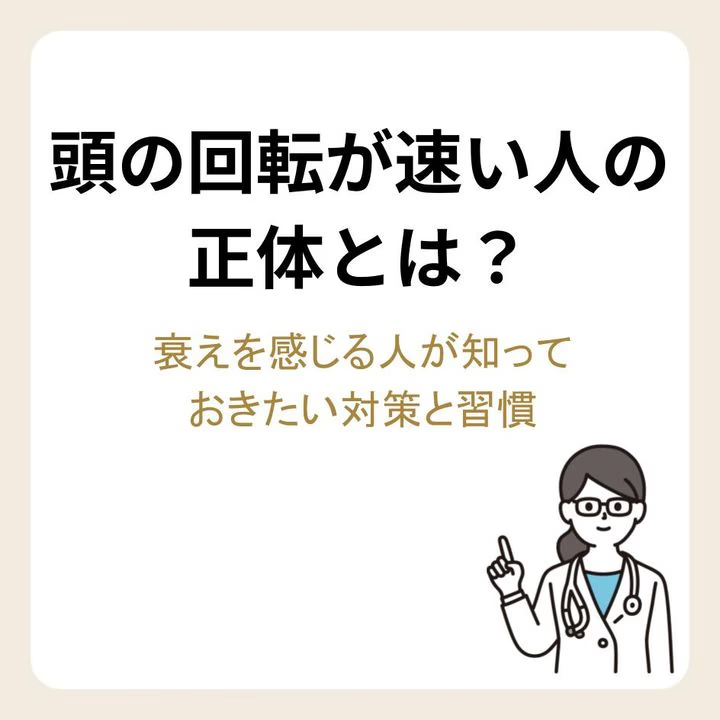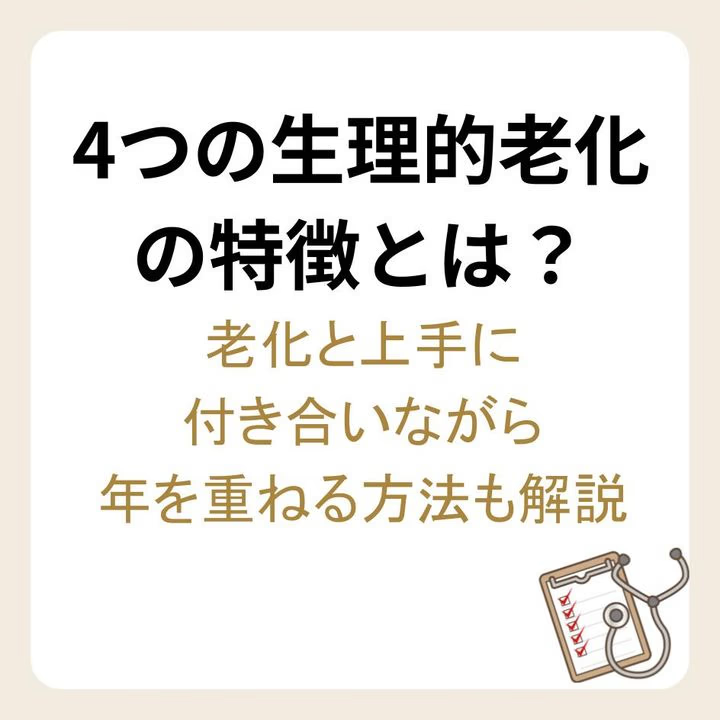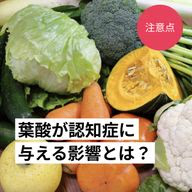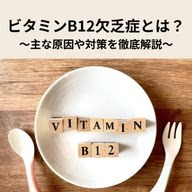2026-02-13
ビタミンBは取りすぎると体に悪い?取りすぎないための注意点を紹介
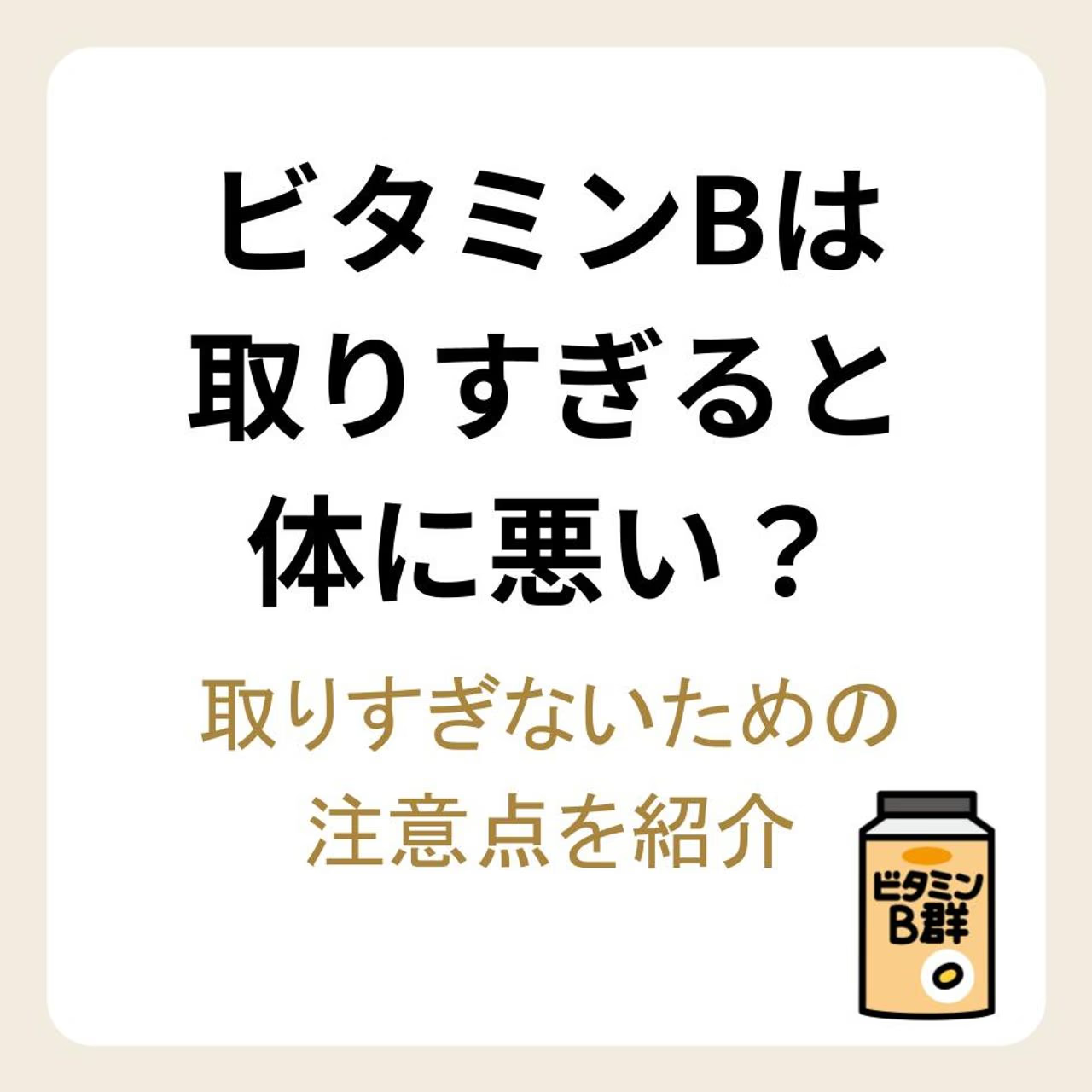
ビタミンBは、ビタミンB1、B2、B6、B12、ナイアシン、葉酸、ビオチン、パントテン酸の8種があり、いずれも健康・美容に重要な栄養素です。積極的に取りたい栄養素ではありますが、実はビタミンB1、B6、ナイアシン、葉酸、ビオチンは取りすぎると良くないことを知っていますか?
そこで、この記事では、ビタミンBを取りすぎると起こる症状を詳しく説明します。逆に不足しても、健康には良くありません。不足によって起こる症状や、過不足なくビタミンBを取るために注意すべき点も紹介します。
適切な量のビタミンBを取って、健康な毎日につなげていきましょう。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授

Webライター
木原かおる
- コスメ薬機法管理者
- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)
- 景品表示法・特定商取引法広告遵守個人認証(KTAA)
ビタミンBを取りすぎるとどうなる?どれぐらいで取りすぎになる?
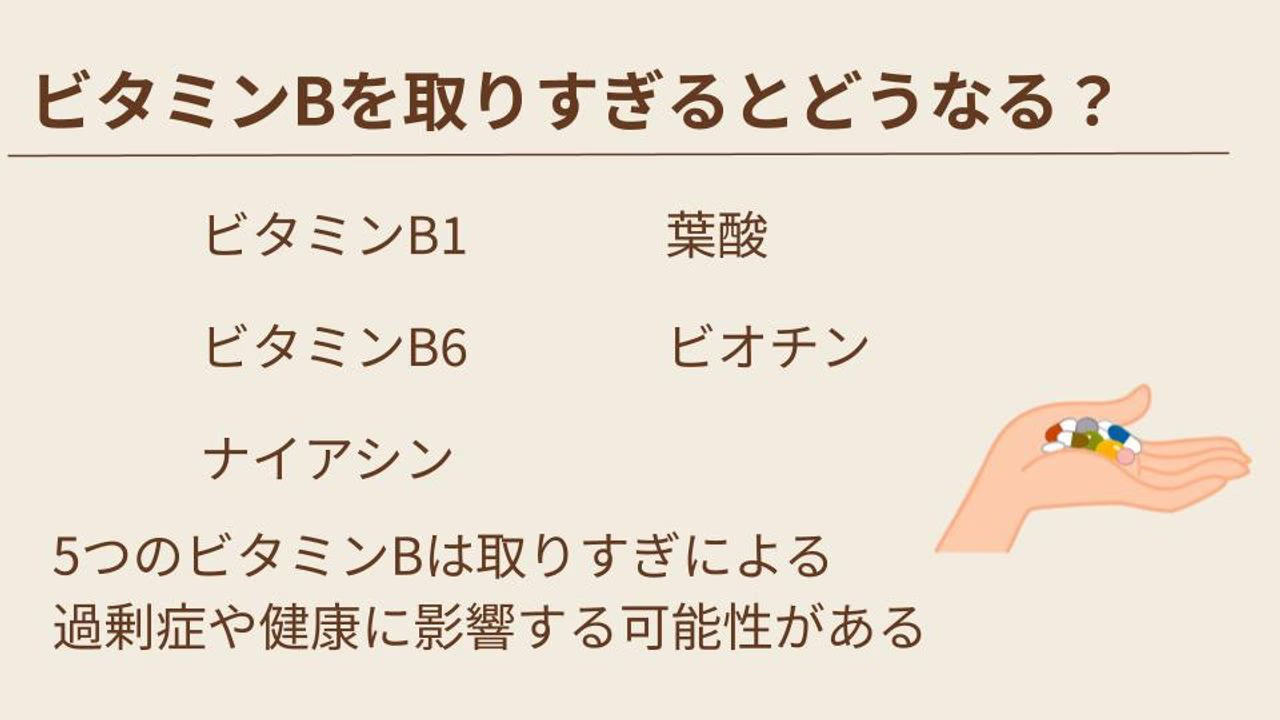 通常の食事でビタミンBを取りすぎることは滅多にありません。取りすぎのリスクがある5種類も含め、ビタミンBは全て水に溶けやすい性質を持っているので、たくさん取っても、尿として排出されてしまいます。また、通常の食品には取りすぎになるほどのビタミンBが含まれていないことがほとんどです。
通常の食事でビタミンBを取りすぎることは滅多にありません。取りすぎのリスクがある5種類も含め、ビタミンBは全て水に溶けやすい性質を持っているので、たくさん取っても、尿として排出されてしまいます。また、通常の食品には取りすぎになるほどのビタミンBが含まれていないことがほとんどです。
しかし、近年は健康維持のためにサプリメントやビタミン剤を取っている方が少なくありません。サプリメントやビタミン剤は、食品よりも高い濃度で作られているものもあり、誤った取り方をすると、取りすぎにつながるリスクがあるのです。
ビタミンB1、B6、ナイアシン、葉酸、ビオチンは取りすぎによる過剰症が起きたり、健康への影響が報告されていたりするので、注意しましょう。
また、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、一部のビタミンBに「耐容上限量」が設定されています。耐容上限量は、健康障害のリスクがないとみなされる習慣的な摂取量の上限のことです。
ビタミンB1
 ビタミンB1は炭水化物からエネルギーを作るときに欠かせない栄養素です。1941年の古いデータでは、10gのビタミンB1を2週間半、毎日飲み続けた結果、頭痛、いらだち、不眠、速脈、衰弱、易刺激性、かゆみが発生したが、中止すると2日で症状は消えたと報告されています。
ビタミンB1は炭水化物からエネルギーを作るときに欠かせない栄養素です。1941年の古いデータでは、10gのビタミンB1を2週間半、毎日飲み続けた結果、頭痛、いらだち、不眠、速脈、衰弱、易刺激性、かゆみが発生したが、中止すると2日で症状は消えたと報告されています。
一方で、ビタミンB1を1日に数百mg用いる治療が行われているものの、悪影響はないとのデータもあります。相反する両方の結果を考慮して、耐容上限量は設定されていません。過剰症や耐容上限量は明確ではないものの、取りすぎによる不調を招くリスクはあると考えられるので注意しましょう。
ナイアシン
ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。厳密にはニコチン酸とニコチン酸アミドの2つの物質を指します。ナイアシンの大量投与により、消化不良、重篤な下痢、便秘などの消化器の障害や肝臓に肝機能低下、劇症肝炎を生じたとの報告があります。
ナイアシンには耐容上限量が設定されています。しかし、実際の食品に含まれているナイアシンは多くないため、サプリメントなどに含まれるニコチン酸やニコチン酸アミドの耐容上限量として設定されています。
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 18~29歳 | 300 (80) | 250 (65) |
| 30~49歳 | 350 (85) | 250 (65) |
| 50~64歳 | 350 (85) | 250 (65) |
| 65~74歳 | 300 (80) | 250 (65) |
| 75歳以上 | 300 (75) | 250 (60) |
※ニコチン酸アミドの重量 (mg/日) 、( ) 内はニコチン酸の重量 (mg/日)
ビタミンB6
ビタミンB6はたんぱく質からエネルギーを作るときに欠かせない栄養素です。ビタミンB6を毎日数g、数か月続けて取ると、「感覚性ニューロパチー」を発症します。ニューロパチーは末梢神経が壊れ、その働きが悪くなっている状態で、感覚性ニューロパチーは、文字通り、感覚に異常を生じるものです。
ビタミンB6については、感覚性ニューロパチーを引き起こさないことを考慮した耐容上限量が設定されています。
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 18~29歳 | 55 | 45 |
| 30~49歳 | 60 | 45 |
| 50~64歳 | 55 | 45 |
| 65~74歳 | 50 | 40 |
| 75歳以上 | 50 | 40 |
※ピリドキシン (分子量=169.2) の重量として表示(mg/日)
また、過剰症ではありませんが、アメリカの閉経女性を対象とした2019年の研究では、ビタミンB6とビタミンB12を過剰に摂取すると、股関節骨折のリスクを高めることが報告されています。
葉酸
葉酸は妊娠している方が積極的に取りたいビタミンで、化学的にはプテロイルモノグルタミン酸という物質です。プテロイルモノグルタミン酸は自然界にほとんど存在しません。サプリメントなどに用いられるのは合成されたプテロイルモノグルタミン酸で、1日あたり5mg以上の摂取で神経症状が現れるリスクがあります。
また、ビタミンB12欠乏症の診断を難しくするリスクもあるため、プロテイルモノグルタミン酸については、耐容上限量が設定されています。
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 18~29歳 | 900 | 900 |
| 30~49歳 | 1000 | 1000 |
| 50~64歳 | 1000 | 1000 |
| 65~74歳 | 900 | 900 |
| 75歳以上 | 900 | 900 |
※プテロイルモノグルタミン酸 (分子量=441.40) の重量として表示(μg/日)
ビオチン
ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。ビオチンについては、日本人の食事摂取基準(2025年版)に過剰症の報告はなく、耐容上限量も設定されていません。
しかし、哺乳動物に関する研究で、妊娠中に多量のビオチンを投与すると、妊娠初期の胚死亡や胎盤、卵巣の委縮が起こったとの報告があります。リスクなどは明確ではありませんが、取りすぎには注意しましょう。
ビタミンBを取りすぎないために注意することは?
 食事のみでビタミンBを賄っている場合は、取りすぎの心配はありません。食品には取りすぎになるほどのビタミンBが含まれていないので、仮に食べすぎたとしても、尿として排出されます。しかし、サプリメントやビタミン剤を正しく利用しないと、ビタミンBの取りすぎになってしまいます。
食事のみでビタミンBを賄っている場合は、取りすぎの心配はありません。食品には取りすぎになるほどのビタミンBが含まれていないので、仮に食べすぎたとしても、尿として排出されます。しかし、サプリメントやビタミン剤を正しく利用しないと、ビタミンBの取りすぎになってしまいます。
取りすぎないためには、パッケージなどに書かれている量を守ることが大切です。また、ビタミンサプリと、疲労回復を目的としたビタミン剤を同時に取る場合は、配合量を見て、取りすぎにならないように注意しましょう。飲み合わせに不安がある場合は、かかりつけ医や薬剤師に相談するのがおすすめです。
ビタミンBが不足するとどうなる?
 取りすぎが怖いからと言って、ビタミンBが不足してしまうと、健康を害してしまいます。8種のビタミンBが不足すると、以下の症状を引き起こします。取りすぎも、不足も健康には良くないので、適切な量のビタミンBを取ることが大切です。
取りすぎが怖いからと言って、ビタミンBが不足してしまうと、健康を害してしまいます。8種のビタミンBが不足すると、以下の症状を引き起こします。取りすぎも、不足も健康には良くないので、適切な量のビタミンBを取ることが大切です。
| ビタミンBの種類 | 不足による影響 |
|---|---|
| ビタミンB1 | 脚気、ウェルニッケ脳症 |
| ビタミンB2 | 口角炎、舌炎、咽喉炎、皮膚炎 |
| ビタミンB6 | 湿疹、口角炎、舌炎、脂漏性皮膚炎、貧血、聴覚過敏、免疫力低下など |
| ビタミンB12 | 悪性貧血、神経障害、感覚異常、記憶障害、うつ病、慢性疲労など |
| ナイアシン | ペラグラによる皮膚炎、下痢、精神神経障害 |
| 葉酸 | 高ホモシステイン血症、巨赤芽球性貧血、神経障害、腸機能障害など |
| ビオチン | 食欲不振、吐き気、うつ症状、乾燥鱗片皮膚炎、筋肉痛、結膜炎、脱毛、運動失調、けいれん、皮膚の感染、知覚過敏など |
| パントテン酸 | 副腎傷害、手足のしびれ、頭痛、疲労、不眠、胃不快感を伴う食欲不振など |
ビタミンBを過不足なく取るには?
 健康を維持するためには、ビタミンBを過不足なく取る必要があります。そこで重要となるのは、ビタミンBを含む食材選び、ビタミンBをできるだけ失わない調理法、栄養素同士の組み合わせです。
健康を維持するためには、ビタミンBを過不足なく取る必要があります。そこで重要となるのは、ビタミンBを含む食材選び、ビタミンBをできるだけ失わない調理法、栄養素同士の組み合わせです。
また、食事をメインにして取るのが理想ですが、足りない場合はサプリメントを上手に使って補いましょう。
ビタミンBを豊富に含む食材を選ぶ
ビタミンBを食事からしっかり取るためには、まず食材選びが重要です。以下のビタミンBを含む食材を積極的に取り入れましょう。外食する場合も、不足しているビタミンBを補える食材を使ったメニューを選ぶのがおすすめです。
| ビタミンBの種類 | 多く含む食品 |
|---|---|
| ビタミンB1 | 豚肉、うなぎ、たらこ、玄米、子持ちかれい、紅鮭、ぶり |
| ビタミンB2 | 豚・牛・鶏レバー、うなぎ、卵、牛乳、納豆、ぶり、豚ヒレ肉 |
| ビタミンB6 | 豚ヒレ肉、鶏胸肉、牛ヒレ肉、まぐろ、かつお、さば、玄米、バナナ、じゃがいも |
| ビタミンB12 | 牛・鶏レバー、いわし、さば、さんま、鮭、しじみ、あさり、かき、海苔 |
| ナイアシン | 鶏胸肉(皮付き)、豚ヒレ肉、かつお、まぐろ、さば、ひらたけ、エリンギ |
| 葉酸 | 豚・鶏レバー、鶏ささみ・胸肉、たらこ、アボカド、納豆、子持ちかれい、玄米、牛ヒレ肉 |
| ビオチン | 牛・豚・鶏レバー、海苔、ブロッコリー、ほうれんそう、枝豆、トウモロコシ、アスパラガス |
| パントテン酸 | 豚・鶏レバー、かれい、あさり、ピーナッツ、卵、納豆、まいたけ |
調理方法も意識する
 せっかくビタミンBを含む食材を選んでも、調理のやり方次第では、ビタミンBが失われてしまいます。
せっかくビタミンBを含む食材を選んでも、調理のやり方次第では、ビタミンBが失われてしまいます。
特に注意すべきは、ビタミンBの流出です。ビタミンBは水溶性ビタミンの一種で、文字通り、水によく溶けます。そのため、食材を水洗いしたり、ゆでたりすると、ビタミンBが流れ出てしまうのです。また、ビタミンB1やB2は加熱調理によって失われることも示唆されています。
ビタミンBを意識する場合、食材を長時間、水洗いすることは避けましょう。煮たり、ゆでたりする場合は、スープや鍋にして溶け出たビタミンBを一緒に飲んでしまうのがおすすめです。
食材を大きめに切ることも流出を防ぐのに役立ちます。魚の場合は刺身で食べるのもおすすめです。
栄養素の組み合わせも重要
栄養素の中には一緒に取ることで、吸収効率がアップする組み合わせがあります。ビタミンBにも該当する組み合わせがいくつかあるので、料理をする際に意識してみましょう。
ビタミンB1はニンニクに含まれるアリシンと結合すると吸収されやすくなります。アリシンはニンニクを調理した時の食欲をそそるあの香りの元になる物質です。例えば、豚肉とニンニクを使った料理は、ベストな組み合わせと言えるでしょう。
また、京都大学、東京慈恵会医科大学、滋賀県立大学の研究チームが、ビタミンBの吸収と代謝に亜鉛が重要であることを2024年に発表しています。
さらにビタミンBは単独で働くわけではありません。例えば、タンパク質の代謝にはビタミンB2とB6、脂質の代謝にはビタミンB2、ナイアシン、パントテン酸のように、複数のビタミンBが関わります。1種類のビタミンBのみを意識するのではなく、8種類のビタミンB全てをバランス良く取りましょう。
不足するものはサプリメントで補う
全ての栄養素は食事から取るのがベストです。ビタミンBの取りすぎという観点でも普段の食事が重要ですが、毎食完璧な栄養バランスの食事を取ることは難しいでしょう。ビタミンBが不足しては本末転倒なので、足りない分を補うためにサプリメントを取り入れるのがおすすめです。
ビタミンB群のみのサプリメントでもよいですが、他にも不足している栄養素がある場合は、複数の栄養素を一緒に取れるものを選びましょう。足りない栄養素の数だけサプリメントを増やすと、面倒になって続けられなくなってしまいます。
また、サプリメントは定められた摂取目安量を守ることが重要です。ビタミンBが足りないからと、目安よりも多く取ることを続けると、取りすぎにつながってしまいます。サプリメントは文字通り「補う」目的で利用しましょう。
5つのビタミンBをバランスよく補えるオールインワンサプリ「Rimenba」
 ビタミンBの摂取には、5つのビタミンBを配合したサプリ「Rimenba」をおすすめします。ビタミンB1、B2、B6、B12、葉酸の他、ビタミンA、C、D、Eも配合し、ビタミンをバランスよく取れます。さらに鉄分、ビタミンBの代謝や吸収に欠かせない亜鉛もカバー。
ビタミンBの摂取には、5つのビタミンBを配合したサプリ「Rimenba」をおすすめします。ビタミンB1、B2、B6、B12、葉酸の他、ビタミンA、C、D、Eも配合し、ビタミンをバランスよく取れます。さらに鉄分、ビタミンBの代謝や吸収に欠かせない亜鉛もカバー。
脳神経内科医が監修しており、オメガ3脂肪酸のDHAとEPA、プラズマローゲン、ノビレチン、イチョウ葉エキスといった、頭を使う人に欠かせない注目成分も配合しています。
栄養は毎日取るものなので、使わない成分にもこだわり、香料、酸味料、着色料、保存料、甘味料、増粘安定剤の6つの添加物は不使用です。品質面も重視し、GMPに準拠する国内有数の工場で製造しています。
自分に合うか試してみたいという方には、定期購入がおすすめです。初回50%オフの送料無料で、縛りやキャンセル料もなく、15日間の返金保証もありますので、気軽に試せます。
初回で気に入れば、2回目以降も25%オフなので、毎日の栄養バランスのサポートにぴったりです。ビタミンBをバランスよく補いたい方は、ぜひ公式サイトもチェックしてみてください。
食事をメインにビタミンBを過不足なく取って健康に
 ビタミンBのうち、ビタミンB1、B6、ナイアシン、葉酸、ビオチンはとり過ぎると、体に悪影響を及ぼすリスクがあります。かと言って、ビタミンBが不足しても健康に悪影響を及ぼすので、過不足なくビタミンBを取ることが重要です。
ビタミンBのうち、ビタミンB1、B6、ナイアシン、葉酸、ビオチンはとり過ぎると、体に悪影響を及ぼすリスクがあります。かと言って、ビタミンBが不足しても健康に悪影響を及ぼすので、過不足なくビタミンBを取ることが重要です。
まず、普段の食事での栄養バランスに気を配りましょう。そして、普段の食事で不足する分をサプリメントで補い、ビタミンBを含め、全ての栄養素を過不足なく取ることが、健康な毎日につながります。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授
【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター
木原かおる
- コスメ薬機法管理者
- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)
- 景品表示法・特定商取引法広告遵守個人認証(KTAA)
国内化粧品メーカー、外資系消費財メーカーで、品質管理や薬機法業務に約15年従事した後にフリーライターに。薬機法や成分関連の知識をいかして、コスメやサプリのライティング、校正、記事監修などを手がける。