2025-11-27
夜盲症はビタミン不足が原因?ビタミンの取り方やおすすめのサプリを解説
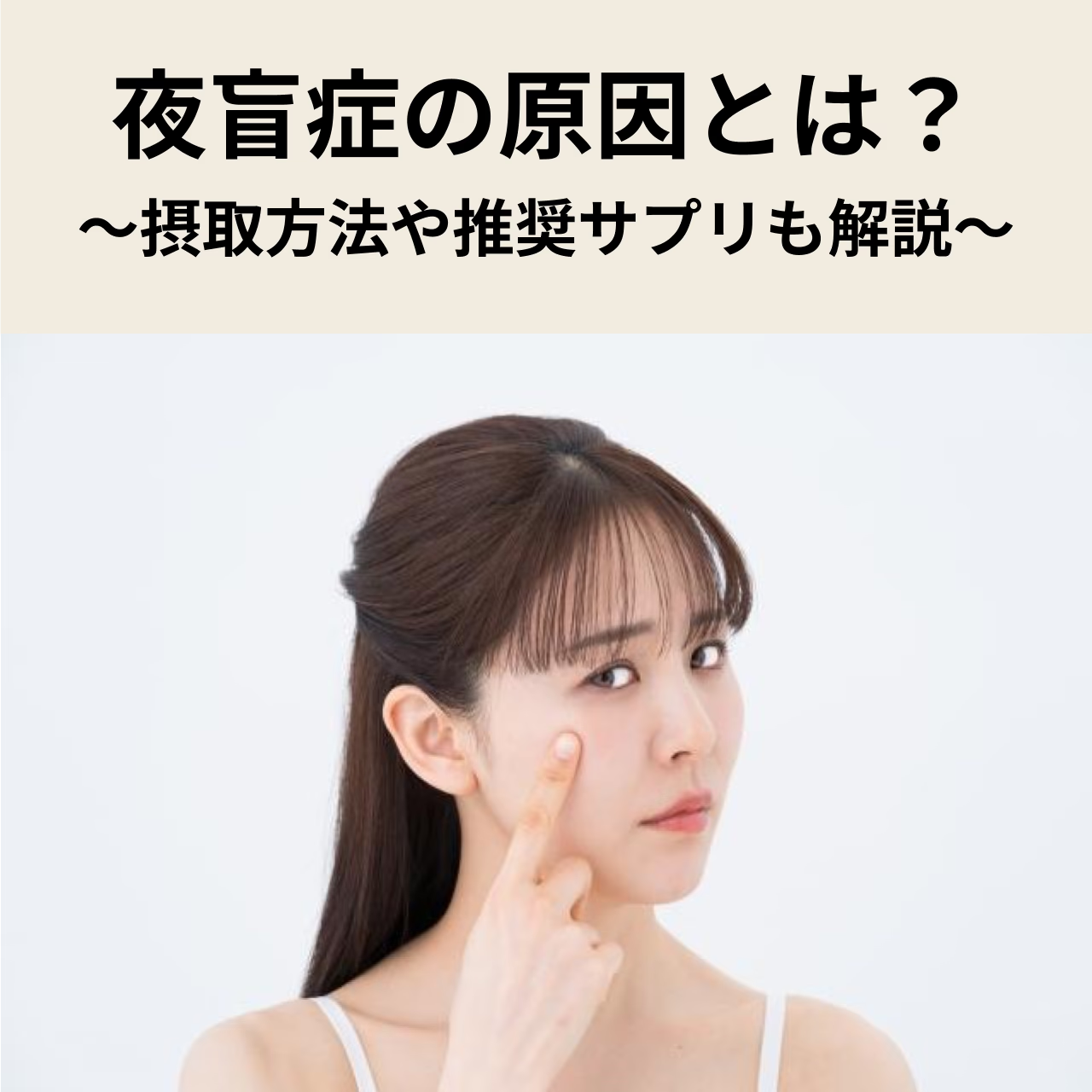
「夜に見えにくさを感じるのは夜盲症?」
「ビタミン不足で発症するのは本当?」
このような疑問はありませんか?
夜盲症はビタミン不足も原因にありますが、遺伝が関係していることもあります。そのため、ビタミンを摂取する前に、原因を知り正しく対処することが大切です。
そこで本記事では、夜盲症がどのようなものか、原因、ビタミン摂取が有効なケースなどを解説します。
また、ビタミン不足による夜盲症対策におすすめのサプリメント「Eyepa(アイーパ)」の特長もご紹介しますので、ぜひご覧ください。
この記事に登場する専門家

Webライター
のん
- 薬膳調整士
- 漢方コーディネーター
- 化粧品3級
夜盲症とは?

夜盲症とは、暗順応がスムーズにできず、暗い場所では視認性が低下する状態のことです。暗順応とは、明るいところから暗いところへ移動したときに、徐々に目が暗闇に慣れて見えるようになってくる生理現象です。光を取り込む量を調節して暗いところでも見えるような仕組みになっています。
夜盲症の方は、暗い場所で目が慣れるまでの時間が長く、夜間における視力低下も見られます。通常であれば10分〜30分で暗順応するところ、夜盲症の方は2〜3時間かかるのが特徴です。また、明るいところでは、光を強く感じて眩しく感じる方もいます。
夜盲症の原因は2つに分かれる

夜盲症を発症する原因は、大きく分けると先天性と後天性があります。それぞれの原因によって、症状や対処法、治療法が異なるため、早めに受診することが大切です。
ここでは、原因やビタミンとの関係性も解説します。
先天性(遺伝)のもの
夜盲症の発症原因の一つに、先天性の疾患が挙げられます。つまり、夜盲症は独立した病気ではなく、目にかかわる遺伝性疾患の症状の一つです。具体的には「網膜色素変性症」と呼ばれる指定難病、「白点状網膜症」の2つでよく見られます。
網膜色素変性症は、網膜に異常が起きる遺伝性の進行性疾患で、進行性の夜盲症が主な症状として見られるのが特徴です。
白点状網膜症は、網膜色素変性症に似た病気で、常染色体劣性遺伝の異常が原因です。進行性の夜盲症や視野が狭くなる症状などが見られます。
後天性のもの
後天性のものは、主にビタミンA欠乏症が挙げられます。ビタミンA欠乏症とは、食事の栄養バランスが偏り、ビタミンAが欠乏してさまざまな症状を引き起こす状態のことです。
ビタミンAは、網膜にある物質の合成に必要な栄養素です。ビタミンAは体内で合成ができないため、不足すると網膜に異常をきたし、夜盲症をはじめさまざまな症状があらわれることがあります。
夜盲症までいかずとも、ビタミンが不足することによる網膜の障害により、視力が低下する症状も見受けられます。健やかな目を維持するためには、ビタミンAをしっかりと摂取することが大切です。
ビタミン摂取が有効なのはビタミンA欠乏症が原因である場合

ビタミン摂取が有効なのは、ビタミンA欠乏症が原因であるケースです。遺伝性の疾患である場合は、ビタミンAを摂取しても改善は困難です。
網膜色素変性症は指定難病であり、2025年時点でまだ治療法は確立されていません。夜盲症と思われる症状がある場合は、まず医師の診断を受けることが大切です。
ここでは、ビタミンAの欠乏により夜盲症を発症している方に向けて、ビタミンAの概要や豊富な食材、過剰摂取のリスクを解説します。
ビタミンAとは?
ビタミンAは、レチノール、レチナール、レチノイン酸の総称です。皮膚粘膜の健康や抵抗力を保つ働きがあります。またレチノールは、光刺激反応に関与する網膜の物質を合成する材料であり、夜間の視力維持には欠かせません。
ビタミンAは、直接食事などから摂取する以外に、β-カロテンを摂取する方法もあります。β-カロテンは小腸に運ばれるとビタミンAに変換される性質を持ちます。ビタミンAの摂取量が不足していると感じている方は、β-カロテンを含む食材を取り入れることも意識するとよいでしょう。
ビタミンAが豊富な食材
ビタミンA・β-カロテンが豊富な食材は以下のようなものがあります。
| カテゴリー・栄養 | 食材 |
|---|---|
| 野菜類(β-カロテン) | ほうれん草・ニンジン・小松菜・しそ・モロヘイヤ・春菊・ブロッコリー・トマト |
| 魚介類(レチノール) | ウナギ・ぎんだら・ほたるいか・アナゴ |
| 副産物(レチノール・β-カロテン) | 牛乳・鶏卵 |
| その他(レチノール) | 無糖ヨーグルト・バター・プロセスチーズ |
夜盲症対策には、上記の食材を意識的に取り入れつつ、五大栄養素も考慮してバランスの良い食事を心がけましょう。
摂取量に注意!ビタミンAの過剰摂取のリスク
ビタミンAは脂溶性ビタミンのため排出されにくく、長時間体内に留まる性質があります。そのため、サプリメントの過剰摂取や、レバーを大量に食すとビタミンA中毒を発症する恐れがあります。
主な急性症状には、頭痛や吐き気、めまい、腹痛などが見られ、慢性化すると食欲不振や脱毛、体重減少、骨密度の減少などが見られます。このように、全身にわたるさまざまな不調を引き起こすため、1日の摂取量は守ることが大切です。
<1日の摂取基準量>
| 性別 | 1日の摂取基準量 | 耐容上限量 |
|---|---|---|
| 男性(㎍RAE) | 18~29歳:850 30~64歳:900 | 18~75歳以上:2,700 |
| 女性(㎍RAE) | 18~29歳:650 30~64歳:700 | 18~75歳以上:2,700 |
夜盲症対策ならビタミンAを効率的に摂取できるサプリメントがおすすめ

ビタミンAは食事で摂取するのが望ましいですが、食事だけで摂取量目安に達するのは困難な方もいるでしょう。このような方は、ビタミンAが含まれるサプリメントを使用するのもおすすめです。
毎日の食事に加えてサプリメントを飲む習慣をつけることで、ビタミンA欠乏症による夜盲症を対策しやすくなります。ここでは、サプリメントの選び方やおすすめのサプリメントをご紹介します。
サプリメントの選び方
サプリメントを探す際は、自分の体質に合うかや品質への安心感、飲みやすさを確認することが大切です。具体的に確認すべきポイントは以下の通りです。
- 成分表示でアレルギー成分が入っていないか
- GMP認定工場で製造されているか
- 飲みやすい形状・大きさか
- 医師監修されているか
<成分表示でアレルギー成分が入っていないか>
サプリメントに配合される成分は、食材から抽出しているものが多く存在しています。よって、えび・かに・キウイ・もも・ナッツなど、アレルゲンとなる食材を用いていることもあります。食物アレルギーがある方は、原材料やアレルギー表示をチェックしてから購入しましょう。
<GMP認定工場で製造されているか>
GMP認定工場は、厳しい安全基準・衛生基準を満たした工場です。有害物質の混入や成分量にばらつきが生じないよう厳しい環境下で管理されています。
<飲みやすい形状・大きさか>
サプリメントには、カプセル・ドリンク・粒状・粉末といった形状があります。ニオイが苦手な方はカプセル、錠剤やカプセルが飲み込みにくい方はドリンクといったように、ご自身に合ったものを選びましょう。
また、カプセルや粒状のものを使用する場合は、小さい粒のサプリメントを選ぶと飲みやすいでしょう。
<医師監修されているか>
医師監修のサプリメントは、医療分野の専門家である医師の知見を活かして製造されています。
たとえば、配合する成分の知識や、成分の配合量などを監修してもらうことで、目的に沿った成分を配合したサプリメントが作れます。
製造している側も購入側も安心感のある商品といえるため、医師監修のサプリメントを選ぶメリットは大きいでしょう。
おすすめのサプリメント「Eyepa」

ビタミンAのサプリメントをお探しの方は、ビタミンAに加えて10種類以上の栄養素が含まれている「Eyepa(アイーパ)」がおすすめです。「Eyepa(アイーパ)」には、以下のように目の健康を維持するのに役立つ栄養素がたくさん含まれています。
- ビタミンA・C・E
- アスタキサンチン
- ゼアキサンチン
- 亜鉛
このほかにも、目のうるおいを保つビルベリー、メグスリノキも配合。トータル的なサポートができるオールインワンサプリとなっています。
摂取量目安はたった2粒。高齢者の方も飲みやすい小粒タイプであるのも魅力的です。
また、安心して飲めるよう製法にもこだわり、国内のGMP認定工場ですべて製造しています。香料、着色料、保存料、酸味量、甘味料、増粘安定剤といった添加物も使用していません。原材料は眼科医監修であるのも、「Eyepa(アイーパ)」の大きなポイントです。
ビタミンAを補うサプリメントをお探しの方、目の健康をトータル的にサポートできるサプリメントをお探しの方は、一度「Eyepa(アイーパ)」を試してみてはいかがでしょうか。
サプリメントを使用する際の注意点
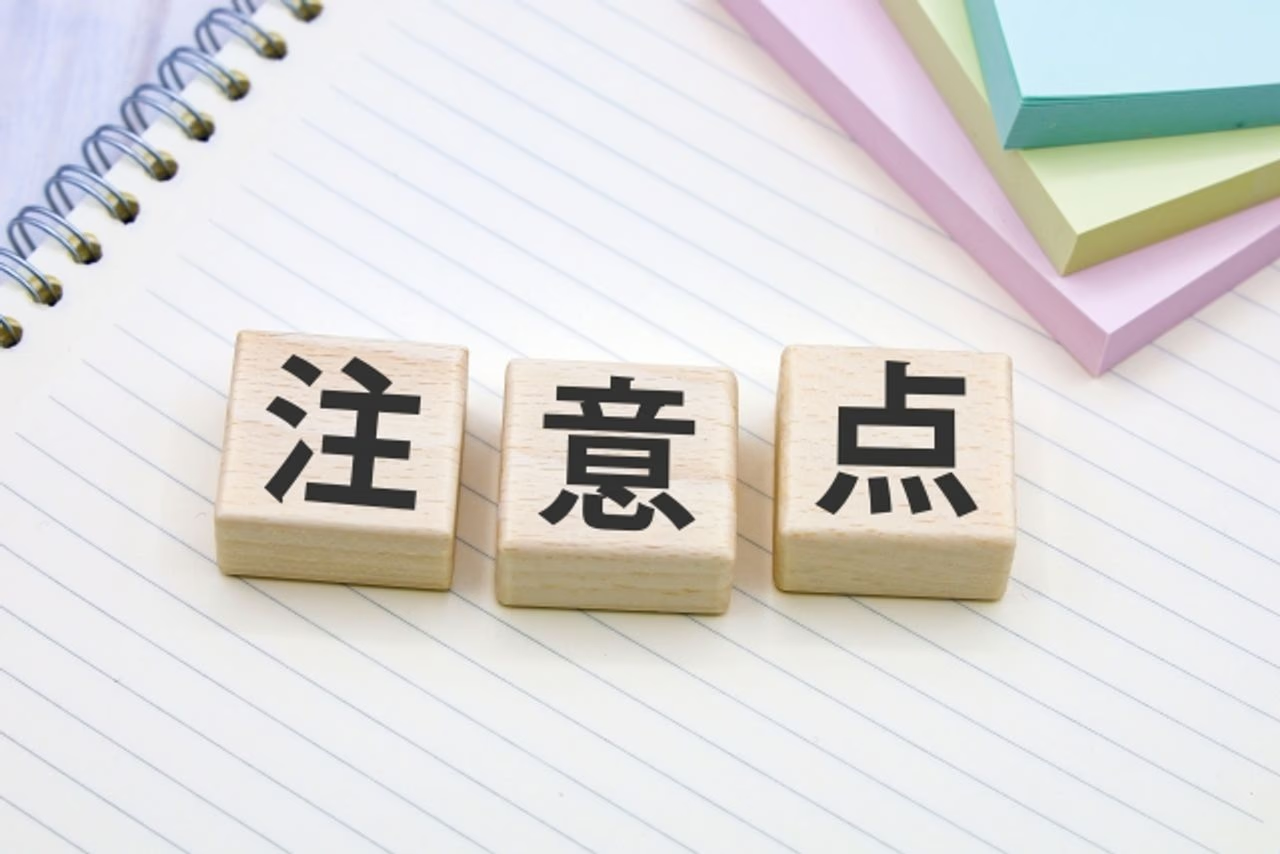
サプリメントを使用する際の注意点を3つお伝えします。
- 食事から栄養を摂取することが前提で使用する
- 持病・服薬中であれば医師に相談する
- 体調の異変を感じたら使用を中止して医師に相談する
上記は健康にも影響を与えるため、守りましょう。
食事から栄養を摂取することが前提で使用する
サプリメントはあくまで補助食品であり、サプリメントを中心に栄養素を摂ることはおすすめしません。
さまざまな野菜や魚介類などを取り入れ、栄養バランスを考えた献立を意識した上でサプリメントを使用しましょう。
持病・服薬中であれば医師に相談する
サプリメントの成分によっては、持病を悪化させたり、服薬中の薬の効果に影響をもたらしたりする可能性があります。そのため、持病がある・服薬中であるという方は、必ず購入する前に使用してもよいか医師に相談しましょう。
もし、気になっている商品があればその商品を伝えたり、配合成分を伝えたりすると医師も答えやすいでしょう。
体調の異変を感じたら使用を中止して医師に相談する
サプリメントを継続的に使用し、体調の異変を感じたら使用を控えてください。サプリメントの成分によっては、体質に合わず体調を崩す場合があります。
実際に、サプリメントによる肝機能低下を起こすこともあります。サプリメントを使用中は、どのような体調の変化があるのかを観察し、必要に応じて医師の診断や指示を仰ぎましょう。
ビタミン不足対策で夜盲症を予防しよう

ビタミンA不足が長期的に継続すると、ビタミンA欠乏症による夜盲症になる可能性があります。そのため、食事ではβ-カロテンやレチノールを含むさまざま食材を取り入れるほか、そのほかの栄養素もバランスよく摂取することが大切です。
もし、食事だけで摂取するのが難しい場合は「Eyepa(アイーパ)」のような、目にいい栄養素を豊富に含んだサプリメントを取り入れるのもおすすめです。自分に合った方法で、目の健康を維持しましょう。
この記事に登場する専門家

Webライター
のん
- 薬膳調整士
- 漢方コーディネーター
- 化粧品3級
娘と保護猫4匹と一緒に暮らすママライター。 さまざまな健康トラブルから「健康」を意識するようになり、漢方や薬膳の資格を取得。 漢方・薬膳・メイク・車系・ペット系など資格や趣味を活かして幅広く執筆。
あなたへのおすすめ
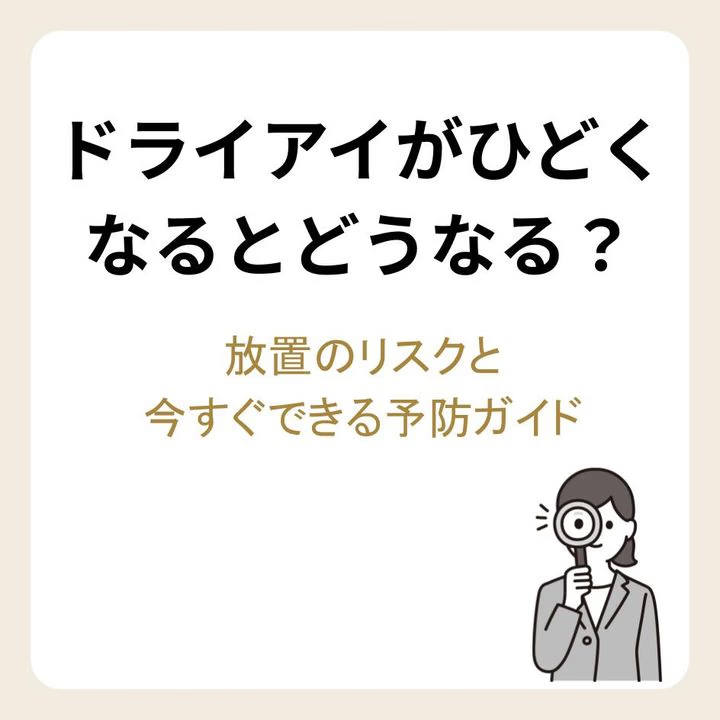
眼の健康
ドライアイがひどくなるとどうなる?放置のリスクと今すぐできる予防ガイド
「最近、どうも目がかすんでピントが合いにくい。これって年齢のせい?」「仕事でパソコ...
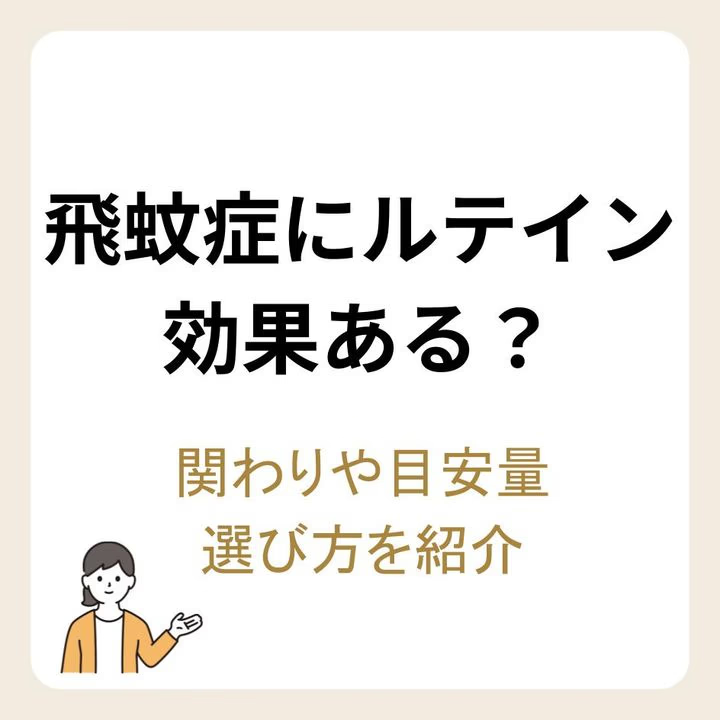
眼の健康
飛蚊症にルテインは効果がある?ルテインの関わりや目安量・選び方を紹介
「デスクワークや読書などで目を使う活動が多い」「視界に虫や糸くずのようなものが見え...
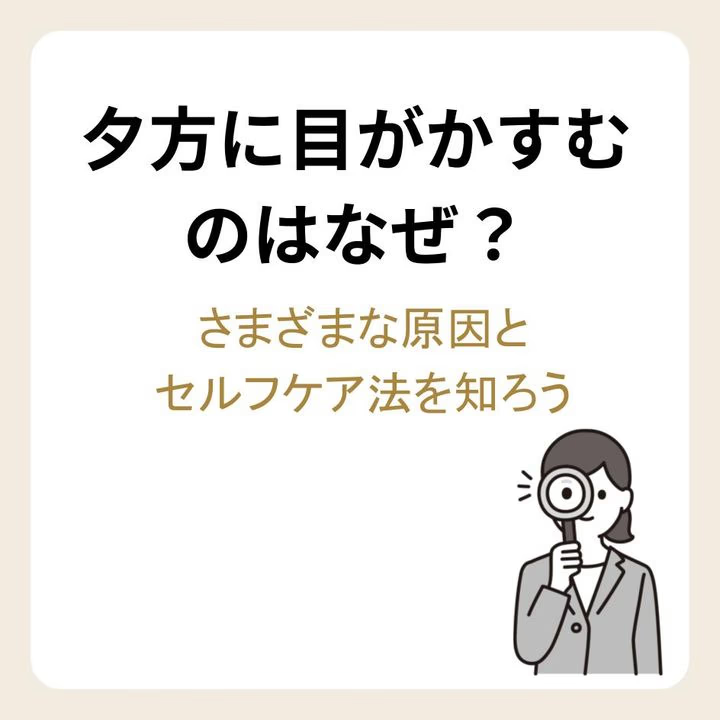
眼の健康
夕方に目がかすむのはなぜ?さまざまな原因とセルフケア法を知ろう
「最近、夕方になるとどうも目がかすむんだけど、これって年のせいなのかな?」「午前中...










