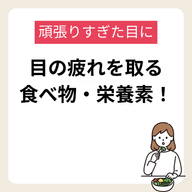2025-11-19
目の乾燥に悩まされる原因とは?自分でできる予防対策を解説!
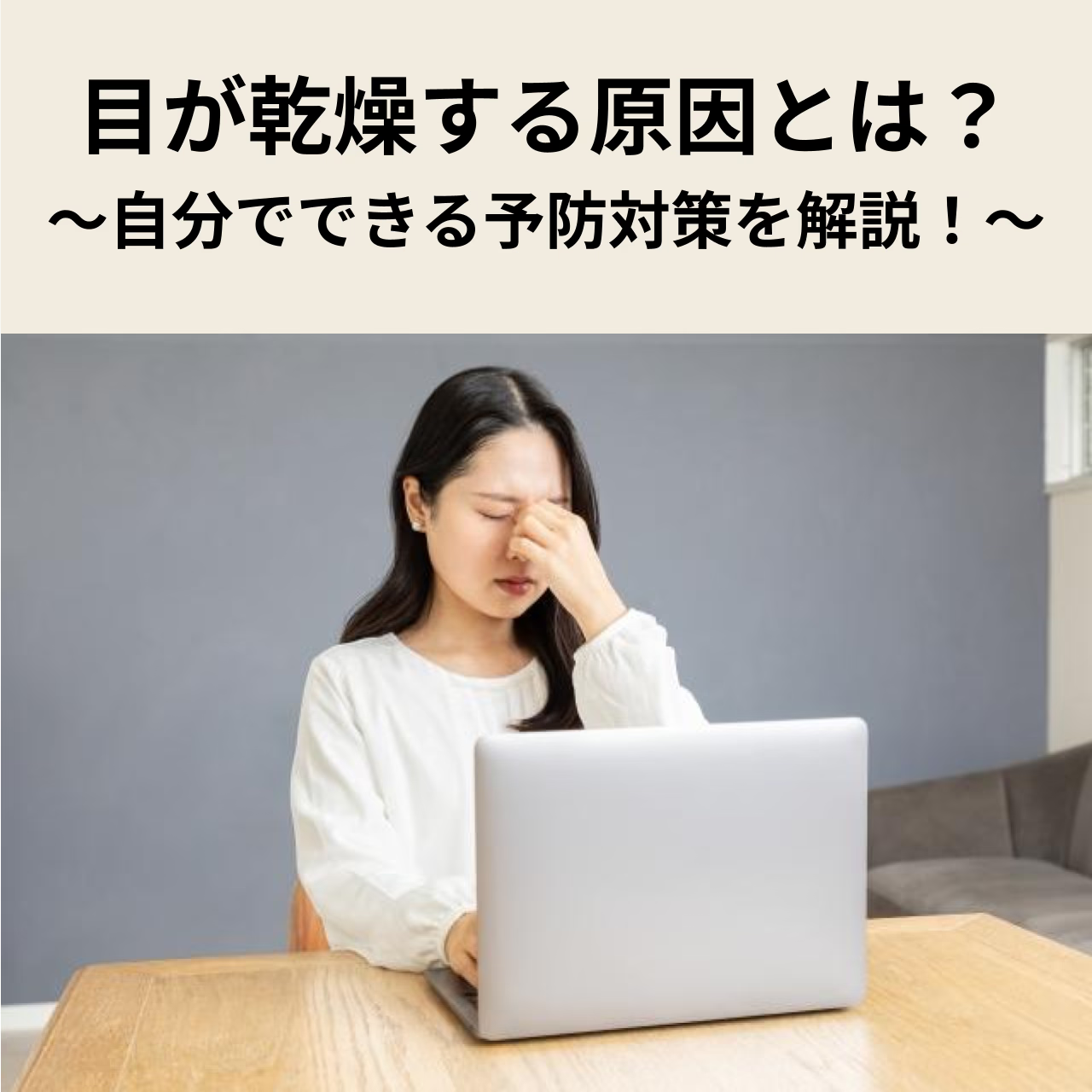
「目が乾いてまぶたを開けていられない」
「目が乾いてしょぼしょぼする」
「目が乾燥して痛い」
このような目の乾きは、放置せず速やかな対処・対策が大切です。
なぜなら、病気が隠れているリスクや放置して目が傷つくリスクがあるためです。
そこで本記事では、目が乾燥する原因や予防法や対策法をお伝えします。
本記事を読むことで、目の潤いをキープしやすくなりますので、ぜひ参考にしてください。
この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長
福永 ひろ美

Webライター
のん
- 薬膳調整士
- 漢方コーディネーター
- 化粧品3級
目が乾燥する8つの原因

ツラい目の乾燥を引き起こす原因を大きく分けると、環境や日常生活の習慣や動作、疾患によるものがあります。具体的には以下の8つです。
- ドライアイ
- 自律神経の乱れ
- 眼精疲労
- またばき回数の減少
- 長時間のコンタクト着用
- 年齢による涙量の減少
- 空気の乾燥
では、一つずつ解説します。
ドライアイ
ドライアイとは、なんらかの原因で涙液量が減少したり質が変わったりすることで起きる目の病気です。目の表面に涙液が行き渡らないことにより、目の乾燥や痛み、ごろつきなどの異常を感じます。
ドライアイには「涙液量が少ないタイプ」と「脂量が少ないタイプ」があります。涙液の蒸発による乾燥が主な原因として知られていますが、最近になり脂量の減少タイプがあることがわかりました。
マイボーム腺から分泌される脂は、涙液を蒸発させない役目があります。脂量が減少すると十分な量の涙液があるにもかかわらず、目の表面に留まらせることができません。その結果、涙液が蒸発して目の乾きを感じるのです。
また、シェーグレン症候群といった全身疾患が原因でドライアイになることがあります。シェーグレン症候群は、膠原病(こうげんびょう)の合併症です。膠原病の診断を受けている方は、一度かかりつけ医に相談し、シェーグレン症候群を併発していないか検査してもらいましょう。
自律神経の乱れ
目の乾燥には、自律神経の乱れが関係している場合があります。自律神経の一つである副交感神経は、涙の分泌をコントロールする機能があります。そのため、副交感神経がうまく働かないと涙の量が減少してしまうのです。
なお、自律神経の乱れは、過度なストレスや疲労の蓄積、ホルモンバランスの崩れや更年期などによって起きます。仕事に追われて疲れが溜まっている、40歳前後で急に目の乾燥が気になり出したという場合は、自律神経が原因かもしれません。
眼精疲労
眼精疲労とは、ストレスや筋肉の継続的な緊張により起きる目の疾患です。発症する主な原因は、長時間のパソコン・スマホ作業による目の酷使、疾患の影響、ストレスです。
眼精疲労の代表的な症状には、目の痛みや乾燥、頭痛や吐き気、充血などがあります。目の乾き以外に、頭痛や吐き気などの身体症状があれば眼精疲労の可能性がありますので、一度眼科にかかることをおすすめします。
またばき回数の減少
まばたきの回数が減少すると、物理的に目が乾きやすくなります。まばたきは、涙液を目の表面に広げて潤いを保つ役目があるためです。
まばたきが減少する要因には、ゲームやパソコン仕事への集中が挙げられます。画面に集中すると無意識にまばたきが減り、涙液を広げられず蒸発させてしまうため、注意しなければなりません。
長時間のコンタクト着用
長時間にわたってコンタクトを着用すると、目が乾燥しやすくなるため注意が必要です。ハードコンタクトレンズのほうが目が乾きやすくなるイメージを持っている方もいるかもしれません。しかし、目の乾きやすさはソフトコンタクトレンズも同様です。
ハードコンタクトレンズを装着すると、コンタクトレンズに触れている部分に涙液が集まる性質です。一方のソフトコンタクトレンズは、コンタクトレンズが涙を吸収する性質があります。これらの性質から、タイプを問わずコンタクトの長時間使用は目が乾きやすくなります。
年齢による涙量の減少
年齢を重ねることも、目が乾きやすくなる原因の一つです。年齢を重ねるとさまざまな機能が低下しますが、涙を作る器官も例外ではありません。機能が低下すると涙をたくさん作ることが難しくなるため、目が乾きやすくなるのです。
また、更年期に入り女性ホルモンの分泌が減少することも、涙の量が減る原因です。女性ホルモンのエストロゲンは、涙を分泌して潤いを保つ働きがあります。40歳前後から目の乾きが気になる方は、更年期が原因かもしれません。
空気の乾燥
空気が乾燥しているところに長くいると、目の乾燥が進みやすくなります。空気中の水分が少ないと、目の潤い成分が蒸発しやすいためです。
空気が乾燥する要因は、冷暖房や季節的なものがあります。冷暖房が効いた屋内で過ごす場合や乾燥しやすい冬の時期は、普段よりも意識的に湿度対策をするとよいでしょう。
また、直接冷暖房の風が顔に当たることも要因の一つですので、風向きを考えることも大切です。
起床後に目が乾く原因は?

起床後に目が乾くのは、就寝中は涙液が分泌されないことや、まぶたが閉じきっていないことが原因といわれています。
通常であれば、涙液が分泌されてまばたきによって目の潤いが保たれます。しかし、就寝中は涙液の分泌が止まるため、起床後に目を開けると乾きを感じやすくなります。
また、就寝中に完全にまぶたが閉じきらず、スキマが常に空気に触れて水分が蒸発しているのも要因の一つです。
目の乾燥を感じたら?自分でできる予防法や対策法

目の乾きを感じている方は、早めに予防法や対策法を実践することが大切です。
- 目にやさしい食べ物を取り入れる
- 目薬をさす
- コンタクトの使用時間・種類を見直す
- 意識的にまばたきをする
- 目をリラックスさせる時間を作る
- 湿度や冷暖房の風向きを調節する
- サプリメントを取り入れる
気軽に始められる方法ばかりですので、できることから始めてみましょう。
目にやさしい食べ物を取り入れる
ビルベリーに多く含まれるアントシアニンは、目を酷使して一時的に目の乾きを感じる方におすすめの成分です。目の潤い感をサポートする効果が期待されます。
また、健やかな目をキープするために必要な栄養素には、ルテインやビタミンA、B群、C、Eがあります。これらは、目のダメージ保護や疲労回復に効果があることで知られています。
| 栄養素 | 食材 |
|---|---|
| アントシアニン | ビルベリー |
| ルテイン | ほうれん草、ケール、モロヘイヤ、小松菜、とうもろこし、ブロッコリー |
| ビタミンA | うなぎ、ニンジン、ニラ、ほうれん草、ピーマン、鶏レバー、豚レバー、ほたるいかなど |
| ビタミンB1 | 豚ヒレ肉、うなぎ、たらこ など |
| ビタミンB2 | いわし、卵、牛乳 など |
| ビタミンB6 | マグロ、さんま、とりささみ肉 など |
| ビタミンC | ピーマン、パプリカ、レモン、イチゴ など |
| ビタミンE | アーモンド、ごま、アボカド、かぼちゃ など |
これらの栄養素や食材は、複数摂取することがおすすめです。目の疲労や直接的な原因といった、さまざまな視点から目の乾きにアプローチできます。
目薬をさす
目薬は手っ取り早く潤いを足せる方法です。市販の目薬を使用する場合は、ドライアイ専用の目薬や防腐剤無添加の人工涙液がおすすめです。防腐剤無添加の人工涙液は、目にかかる負担を少なくできます。
ただし、防腐剤無添加の人工涙液は、一度開封すると雑菌が湧くため数週間以内に使い切らなくてはなりません。商品によっては1週間程度と期限が短いものもあるため、取扱説明書を確認しましょう。
しっかりと効果を得たい方は、眼科で処方された目薬の使用がおすすめです。使用方法は眼科医や処方箋先の薬剤師からの案内に沿ってください。
コンタクトの使用時間・種類を見直す
コンタクトを普段から長く使用して乾燥が気になる方は、できるかぎりメガネをかける時間を作りましょう。コンタクトレンズの性質上、目の潤いが喪失しやすいためです。
たとえば、毎日のコンタクトレンズを週6に減らす、帰宅後すぐにメガネに替えて1日の装着時間を短縮するなど、工夫するとよいでしょう。
加えて、コンタクトレンズの潤いが持続しやすいものを探すことも大切です。たとえば、ソフトコンタクトレンズは「シリコーンハイドロゲル素材」を選ぶと乾燥しにくくなります。また、低含水コンタクトレンズを使用するのもおすすめです。
意識的にまばたきをする
デスクワークが多い方や、趣味でゲームをする方は、意識的にまばたきをするようにしましょう。回数に決まりはないため、意識的に増やすことを心がけるだけでも変わります。
また、まばたきを増やすため、画面は目線よりも下に設置しましょう。目線よりも高い位置に画面があると、またばきの回数が減りやすいためです。
どうしてもまばたきを意識的にするのが難しい方は、5分ごとや10分ごと、30分ごとなどにアラームをかけて、目を閉じたりまばたきしたりするのもよいでしょう。
目をリラックスさせる時間を作る
目の潤いをキープするためには、目をリラックスさせる時間を作ることも必要です。25〜30分に一度目の休憩時間を作り、遠くを見たりツボ押しやマッサージをしたりするとよいでしょう。オフィスなどの外で仕事する方は、休憩時間にホットアイマスクで目を温める方法だと取り入れやすいのでおすすめです。
目の周りの血行を良くすることで緊張した筋肉をほぐせるため、ドライアイの原因にもなる眼精疲労への対策が期待できます。また、目を温めることでマイボーム腺と呼ばれる、油分を分泌する器官の詰まりを解消できるため油分が分泌されるようになり、涙液の蒸発を防ぐことにもつながります。
湿度や冷暖房の風向きを調節する
乾燥した空気は目の乾燥につながるため、湿度や冷暖房の風向きの調整も大切です。
湿度のコントロールは、加湿器で行うのがおすすめです。卓上加湿器や、空気清浄機と加湿器が一緒になったものなど、さまざまな製品が販売されています。湿度は50%以上が最適です。
冷暖房の風向き設定は、左右・上下に常に動くようにして、一点化させないようにすると、風が自分に当たり続けることを防げます。
サプリメントを取り入れる
「食事だけでビタミンAやB群、C、Eを十分に摂取するのは正直難しい」と感じる方もいるでしょう。そのような方は、手っ取り早く不足しがちな栄養素を補うために、サプリメントを日々の習慣に取り入れるのも一つの手段です。
おすすめのサプリメントは、摂取しやすい量や形状のもの、GMP認定工場で製造されたものです。GMP認定工場とは、厳しい環境下と検査で管理・製造ができると認められた工場です。GMP認定工場で製造されたサプリメントを選択すれば、安心感があるでしょう。
たとえば、「Eyepa(アイーパ)」は、厚生労働省が定めた、医療品等の品質管理基準(GMP)に準拠する国内有数の工場で製造されています。
目を守るビルベリーやルテイン、目の細胞に蓄積されたストレスの緩和が期待できるペンタデシル、目の健康や疲労回復が期待できるビタミン A・C・E、亜鉛をたっぷりと配合。小粒サイズでたった1日2粒と続けられやすいのも魅力的です。
定期購入ですが回数に縛りがなく、体に合わない場合はすぐに解約できます。加えて、初回購入時は特別価格があるため、「まずは1回から気軽に試したい」という方にもおすすめです。
生活習慣の見直しとサプリメントで乾きにくい目を手に入れよう

目の乾燥対策には、普段の生活の中で意識して休憩をとったり、まばたきを増やしたり、目に必要な栄養を取ったりする方法があります。
しかし、これらを完璧に実践するのは難しいため、より簡単に対策したい方は「Eyepa(アイーパ)」のようなサプリメントを取り入れるのもおすすめです。
できることから実践して、健やかな目を目指しましょう。
この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長
福永 ひろ美
【ひとみケアサプリEyepa監修・眼科医】 日々の生活の中で、バランスよく必要な栄養素を摂取することも大切なのです。Eyepaは眼の潤いをサポートしてくれるビルベリーを始め、抗酸化成分であるルテインやアスタキサンチン、その他多様な成分がオールインワンに含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。

Webライター
のん
- 薬膳調整士
- 漢方コーディネーター
- 化粧品3級
娘と保護猫4匹と一緒に暮らすママライター。 さまざまな健康トラブルから「健康」を意識するようになり、漢方や薬膳の資格を取得。 漢方・薬膳・メイク・車系・ペット系など資格や趣味を活かして幅広く執筆。
あなたへのおすすめ
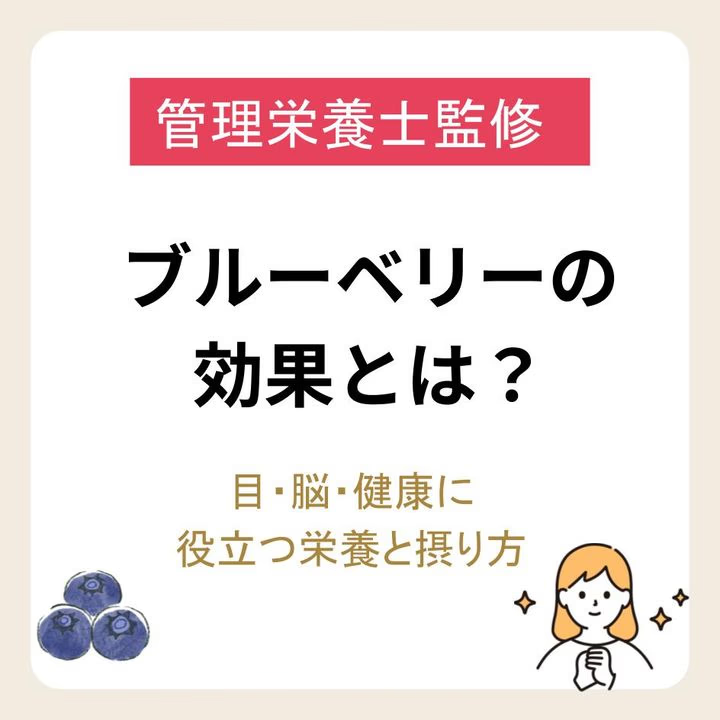
眼の健康
【管理栄養士監修】ブルーベリーの効果とは?目・脳・健康に役立つ栄養と上手な取り入れ方
現代では、スマートフォンやパソコンの長時間使用により「目の疲れ」や「かすみ」を感じ...
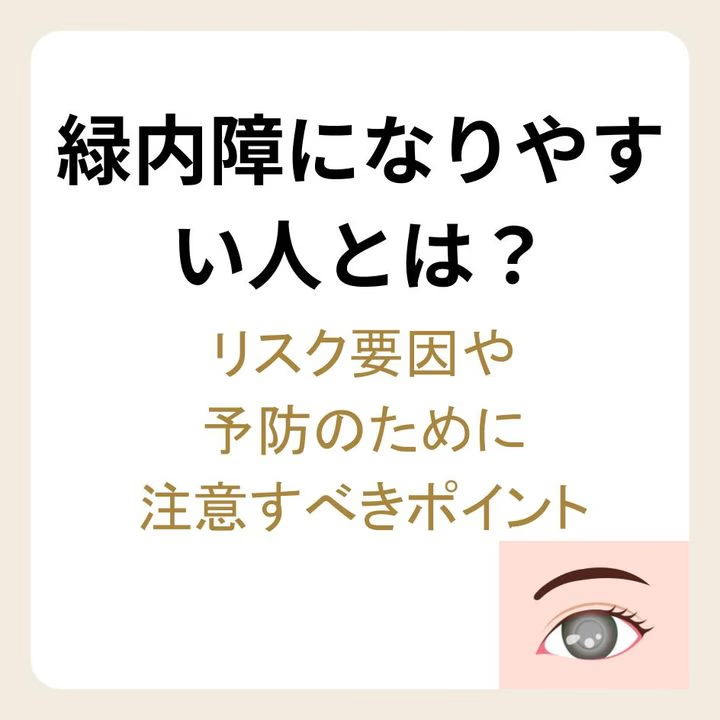
眼の健康
緑内障になりやすい人とは?リスク要因や予防のために注意すべきポイントを解説
加齢に伴う代表的な目の病気として緑内障が挙げられます。特に40代以降の方は要注意の...
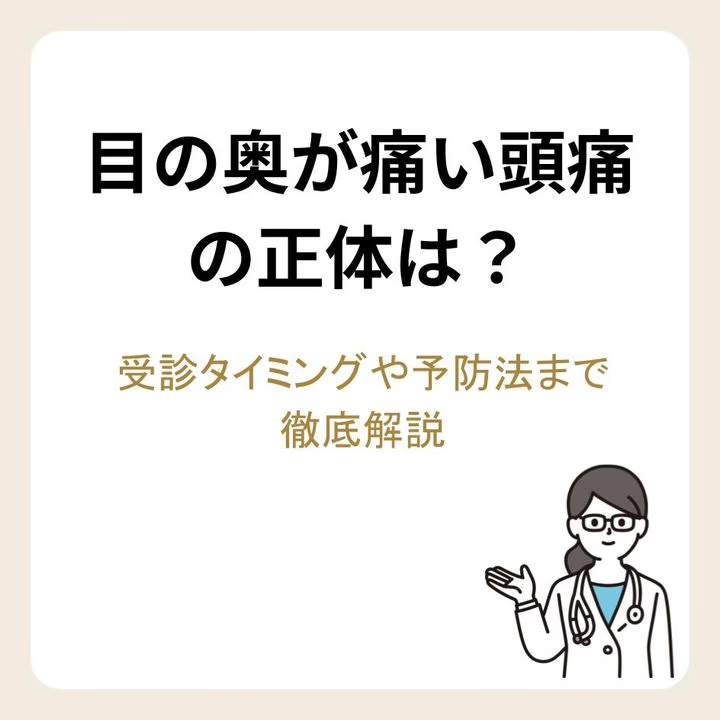
眼の健康
目の奥が痛い頭痛の正体は?受診タイミングや予防法まで徹底解説
「最近、パソコン仕事をしていると目の奥が痛いし、頭痛までしてくる。これって単なる疲...