2026-02-13
あなたは大丈夫?閉経が早い人の特徴と対策方法〜手軽にできる更年期対策〜
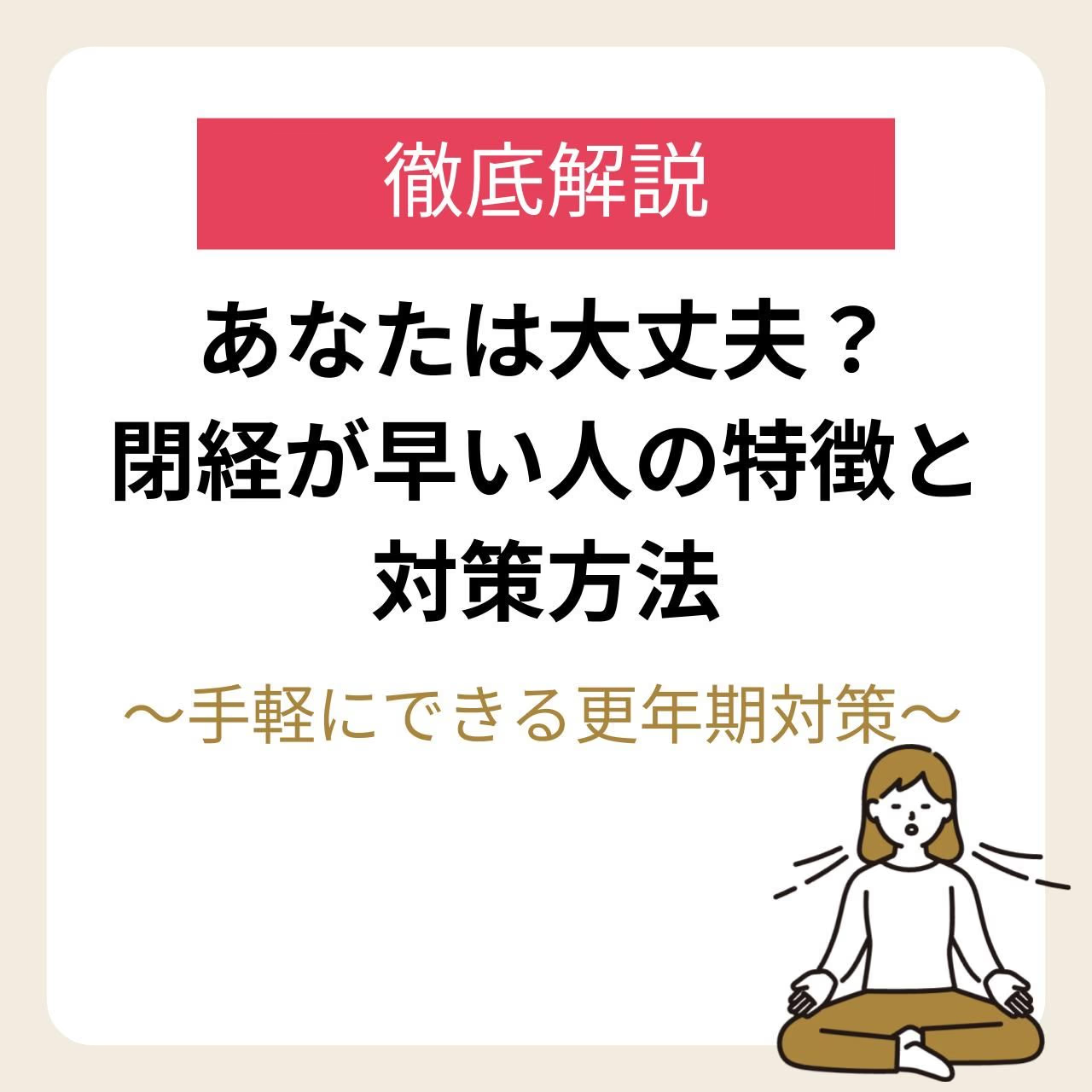
閉経とは、卵巣の機能低下により生理が完全に停止することを指します。日本人の平均的な閉経時期は50歳前後です。
しかし中には、40歳前に閉経を迎える方もおり、その場合は「早期閉経」と呼ばれます。早期閉経はただ早く月経が停止するだけではなく、健康リスクを伴うため注意が必要です。
本記事では、閉経が早い人の特徴や閉経が始まるサイン、閉経に関連する更年期症状への対策について解説します。
「閉経がいつ始まるか不安」「もし早期閉経ならどんなことに注意すればいいの?」「更年期への対策を知りたい」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
- 閉経とは?体に現れるサインを知ろう
- 閉経の仕組みを知ろう!何が起こっているの?
- これって閉経の始まり?体に現れるサイン
- 閉経が早い人の特徴|共通する生活習慣や早期閉経のリスク
- 40歳前に閉経?早発閉経の定義や原因
- 早めの閉経が体に与える影響とは?知っておきたい健康リスク
- あなたも更年期かも?症状セルフチェックリスト
- 突然のほてりや発汗
- めまい・動悸・肩こり
- 気分の浮き沈みやイライラ
- 毎日をラクに過ごす!更年期を乗り切るためのケア方法
- 食生活を整える
- 運動を習慣付ける
- ホルモン補充療法を行う
- サプリメントを摂取する
- 更年期対策におすすめのサプリメント「Rimenba(リメンバ)」
- 健康を支える栄養素をオールインワンで配合
- 医師監修&GMP認定工場での国内生産
- 閉経が早い人の特徴が気になる方は早めに対策を始めよう
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授
閉経とは?体に現れるサインを知ろう

閉経は女性の体に起こる自然な生理現象です。この過程は、女性の体に多くの変化をもたらします。まずは、閉経が具体的にどのようにして起こるのか、そしてその変化が始まる初期段階で現れる体のサインについて、解説しています。
閉経の仕組みを知ろう!何が起こっているの?
閉経とは、「月経が永久に停止し、妊よう性がなくなること」とされています。女性の一生の中で自然に訪れる変化で、卵巣の活動が徐々に低下することで排卵がなくなり、最終的には生理(月経)がこなくなる状態です。
この変化は突然起こるのではなく、さまざまな前兆が続いたのち、12カ月以上月経がこない状態が続くと「閉経」と判断されます。閉経前後の5年間を「更年期」と呼び、女性ホルモンの低下によってさまざまな症状が現れるでしょう。
日本産科婦人科学会によると、閉経の一般的な年齢は50歳前後であり、45歳から55歳の間で閉経を迎える女性が多いとされています。
これって閉経の始まり?体に現れるサイン
閉経が近づくと、体にいくつかの変化が現れ始めます。最も一般的なサインは、生理周期の変化です。周期が不規則になったり、生理の間隔が長くなったり短くなったりすることがあります。また、生理の量が以前と比べて少なくなったり、逆に多くなったりすることもあるでしょう。
また、閉経期には、おりものの量や質に変化が見られることもあります。これらの変化は、女性ホルモンのエストロゲンが減少することによるものです。
閉経前後には、ホルモンの変動が原因でさまざまな更年期症状が現れます。例えば、急なほてりや夜間の発汗、情緒不安定や睡眠障害などです。これらの症状は、「更年期障害」として知られ、閉経のサインともいわれています。
もしもこれらのサインが見られた場合は、専門の医療機関での相談をおすすめします。閉経は自然な現象ですが、健康を守るためには、そのサインを理解し、適切に対応することが重要です。
閉経が早い人の特徴|共通する生活習慣や早期閉経のリスク

閉経は通常50歳前後に訪れますが、40歳未満で閉経を迎えることを「早発閉経」と呼びます。ここでは、早発閉経の原因を探り、どのように体に影響を与えるかをチェックしていきましょう。早発閉経がもたらす健康リスクについても深掘りします。
40歳前に閉経?早発閉経の定義や原因
早発閉経は、40歳未満で閉経が起こる状態です。一般的に、女性の閉経は平均で50歳前後に見られるため、40歳前の閉経は非常に早いとされます。早期閉経が起こる主な原因は以下の通りです。
- 遺伝的要因: 染色体異常が早発閉経に関連していることがあります。
- 自己免疫疾患: 体の免疫システムが誤って卵巣を攻撃し、その結果引き起こされるのが機能低下です。
- 治療: 化学療法や放射線療法など、がん治療が卵巣の機能に影響を及ぼすことがあります。
- 生活習慣: 喫煙やストレス、不規則な食生活といった生活習慣が、ホルモンバランスに影響を与えて生じることがあります。
ただし、早期閉経の原因ははっきりしておらず、個人差もあります。上記に当てはまるからといって、必ずしも早期閉経につながるとは限りません。
早めの閉経が体に与える影響とは?知っておきたい健康リスク
早期閉経はただ月経が停止するだけではなく、いくつかの健康リスクが伴います。ここで、早発閉経がもたらす恐れのある健康リスクについて見てみましょう。
- 殖機能への影響: 早期閉経は不妊の原因となります。卵巣の機能が停止すると、自然な妊娠が困難または不可能です。
- 骨密度の低下: エストロゲンの量が減少すると、骨密度が低下し、骨粗しょう症や骨折の危険性が増します。
- 心理的・情緒的な影響: 閉経はホルモンの変動を伴い、これが情緒不安定やうつ症状を引き起こすことがあります。
- 心血管疾患のリスクの増加: 心血管系の保護も助けるエストロゲンの早期減少は、心血管疾患のリスクを上昇させる可能性があります。
- 呼吸器疾患での死亡率が増加:女性ホルモンが急減することで気道上皮のムチン産生が低下し、気道保護機能が弱まり、呼吸器疾患になりやすくなるといわれています。
早発閉経に直面する可能性がある女性にとって、早発閉経の影響を理解し、対策を行うことが重要です。
あなたも更年期かも?症状セルフチェックリスト

閉経の前後5年間の期間が「更年期」です。ここでは、閉経のサインを見逃さないために、更年期症状が始まっていないかのセルフチェックリストを紹介します。最近、体に違和感を覚えていたり、「もしかして更年期?」と不安に感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
突然のほてりや発汗
更年期の代表的な症状は次の通りです。
- ホットフラッシュ:ホットフラッシュは、体全体が急激に熱くなり汗がふきでる症状のことです。ほてり・のぼせなどが昼夜を問わずに発生し得るため、生活に大きな影響を与えることがあります。
- 発汗:更年期における発汗は、特に夜間に顕著になることがあります。この過剰な発汗はしばしば睡眠を妨げ、日中の活動にも影響を及ぼす可能性があります。
めまい・動悸・肩こり
ホルモンの変動により、めまい・動悸・肩こりといった身体症状が現れる恐れがあります。。
- めまい: ふらつきや立ちくらみが突然現れます。
- 動悸: 心が急に激しく打つ感じが起こります。
- 肩こり: 首から肩にかけての持続的な痛みや硬直を感じることがあります。
- 胸の圧迫: 突然胸に圧迫感や痛みが生じます。
- 腰や背中の痛み: 長時間同じ姿勢を取ったり、重い物を持ち上げた後に痛みを感じます。
- 冷え: 特に夜間、手足が冷たくなることがあります。
- 頭痛: 片頭痛が起こりやすく、ズキンズキンと脈打つような痛みが発生することがあります。
- 関節痛: 手足の関節に痛みや腫れを経験することがあります。
- しびれ: 手足にピリピリ感や痺れが生じることがあります。
- 疲れやすさ: 普段の活動で異常に疲れます。
気分の浮き沈みやイライラ
精神的な健康への影響は、更年期の間に特に無視できない問題です。更年期には、以下のような精神症状が現れることがあります。
- 抑うつ症状: 憂鬱感や無気力があり、日常生活の活動に対する興味が失われます。
- 食欲低下: 普段の食事への関心が著しく減少し、体重減少につながります。
- イライラ: 小さな刺激で怒りやすくなり、家族や友人との関係に影響を及ぼします。
- 睡眠障害: 睡眠の質が低下し、夜間に何度も目を覚ます中途覚醒を経験します。
これらの症状を感じた際には、対策を考えることが重要です。場合によっては、専門的な医療機関の受診をおすすめします。
毎日をラクに過ごす!更年期を乗り切るためのケア方法

実際に更年期が来たらどうすればいいの?と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。食生活の見直し、運動の習慣付け、ホルモン補充療法、そしてサプリメントの摂取を組み合わせることにより、更年期症状の軽減または全体的な健康維持が期待できます。
より快適な毎日を送るために、具体的なケア方法について見ていきましょう。
食生活を整える
食生活の見直しは、更年期症状への対策の一つとして知られています。特に、エストロゲンと似た働きをする大豆イソフラボンや、ホルモンバランスを調整するビタミンE、骨粗しょう症の予防に欠かせないカルシウム、そしてカルシウムの吸収を助けるビタミンDの摂取が重要です。
これらの成分を多く含む食品としては、豆腐や納豆、アーモンド、ほうれん草、鮭やサバなどがあります。これらの食材を日常の食事に取り入れることで、体調を整え、更年期症状の軽減が期待できます。
また、上記の栄養だけでなく、栄養バランスの取れた食事を心がけること、1日3食規則正しく食事を取ることも大切です。
運動を習慣付ける
定期的な運動は、更年期に伴う多くの身体的・精神的症状の緩和に役立ちます。特に、ランニングやウォーキングといった有酸素運動は骨密度を維持し、体力・持久力の向上につながります。
また、スクワットや腕立て伏せなどの筋トレは、骨機能の向上、血中脂質の低下に効果があるといわれています。運動はストレスの解消、リラックス効果、睡眠の質の改善にもつながるため、習慣付けるのがおすすめです。
ホルモン補充療法を行う
女性ホルモンの減少が更年期の症状を引き起こすため、ホルモン補充療法(HRT)が有効とされています。この治療は、エストロゲンを必要最低量補給し、分泌低下によって引き起こされるさまざまな症状を緩やかにするというものです。
ホルモン補充は、錠剤、皮膚に貼るパッチ、皮膚に塗るジェルといった形で行われ、適切に管理される限り、安全性が高い治療方法といわれています。
ただし、乳がんなどのリスクも指摘されているため、治療は医師の指導のもとで慎重に行う必要があります。
サプリメントを摂取する
ホルモン補充療法が適さない場合や、自然療法を好む方には、サプリメントの活用がおすすめです。更年期対策としてサプリメントを摂取する際には、以下のような成分が含まれているかを確認しましょう。
・プラセンタ
・エクオール
・ローヤルゼリー
・オメガ3脂肪酸(DHA・EPA)
・葉酸
・イチョウ葉
・ノビレチン
サプリメントは、更年期症状だけでなく、他の健康問題にも注意しながら、医師と相談の上で摂取することが大切です。毎日の小さな積み重ねが、長期的な健康を支える鍵となるでしょう。
更年期対策におすすめのサプリメント「Rimenba(リメンバ)」

サプリメントで更年期への対策を行いたいという方におすすめなのが「Rimenba(リメンバ)」です。ここでは、Rimenbaの特徴やおすすめする理由について紹介します。
健康を支える栄養素をオールインワンで配合
「Rimenba(リメンバ)」サプリメントは、更年期以降の女性の健康をサポートする栄養素が20種類以上配合されたオールインワンサプリメントです。
例えば、オメガ3脂肪酸(DHA・EPA)、葉酸、イチョウ葉、ノビレチンなどが該当します。特に、オメガ3脂肪酸(DHA・EPA)の配合量は業界トップクラス。
これらの栄養素は、一つ一つが重要な役割を持ちながらも、同時に摂取することで相乗効果を発揮し、ホルモンバランスの調整、記憶力維持、睡眠改善、ネガティブな気分の抑制など、更年期の健康維持を広範囲にわたってサポートします。
医師監修&GMP認定工場での国内生産
Rimenbaは、厳格な品質管理の下、日本国内のGMP(適正製造規範)認定工場で製造されています。GMP認定とは、厚生労働省が定めた、医薬品等の品質管理基準(GMP)に準拠する工場に与えられる認定です。
また、Rimenbaは医師の監修のもと、科学的根拠に基づいて開発されています。そのため、サプリメントの服用や効果に不安がある方にもおすすめです。
更年期の女性が直面する多くの課題に対して、サプリメントを利用することは一つの有効な手段です。特に「Rimenba(リメンバ)」のような、医師の監修のもとで製造され、複数の栄養素がバランス良く配合されているサプリメントは、日々の食生活だけでは不足しがちな栄養素を補い、更年期の健康管理を助ける重要な役割を担います。
更年期における身体的、精神的な変化に対処し、活力ある毎日を送りたい方は、ぜひRimenbaのようなサプリメントの定期摂取を検討してみてください。
閉経が早い人の特徴が気になる方は早めに対策を始めよう

閉経が早い人の特徴として、遺伝的要因や自己免疫疾患があること、生活習慣が乱れていることなどが挙げられます。
閉経自体は女性が経験する自然現象ではあるものの、早期閉経による健康リスクや、閉経前後の更年期症状に対しては、早めの対策が重要です。
更年期を乗り切るためのケア方法には、栄養バランスの取れた食生活の維持、定期的な運動、ホルモン補充療法、適切なサプリメントの摂取があります。
更年期対策としてサプリメントの活用を検討している方は、ぜひ医師監修のもと、GMP認定工場で製造されているRimenbaをお試しください。
Rimenbaなら、1日4粒で更年期以降に必要な栄養素が20種類以上摂取できる上、複数栄養素の同時摂取による相乗効果も期待できます。
定期購入は、縛り・キャンセル料なしで、初回は割引価格で購入いただけます。送料無料&15日間の返金保証もついているため、「まずは気軽に試してみたい」という方にもおすすめです。
ご自身の悩みに適したサプリメントを活用して、より快適で健やかな日々を実現しましょう。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授
【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。
あなたへのおすすめ
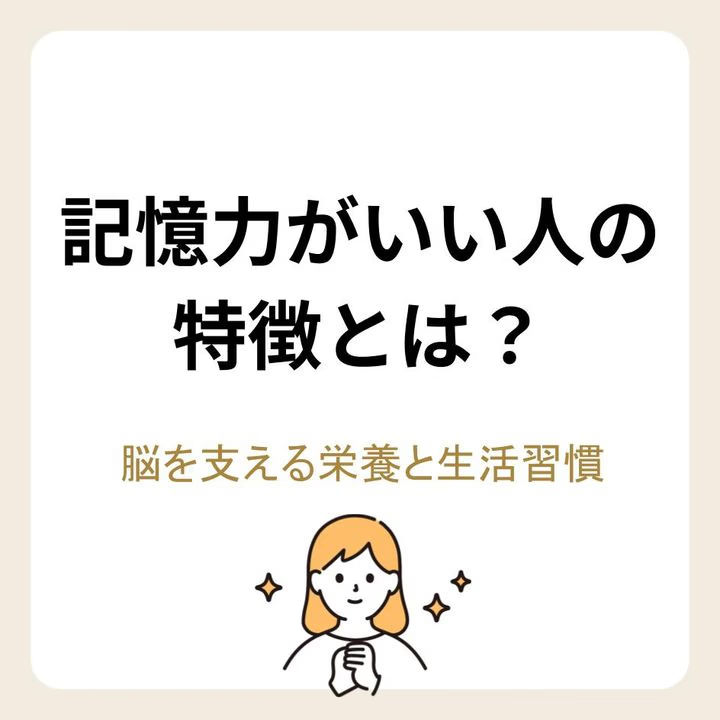
知力健康
記憶力がいい人の特徴とは?脳を支える栄養と生活習慣
「記憶力がいい人は生まれつき」と思っていませんか。しかし記憶力は、脳の使い方や日々...
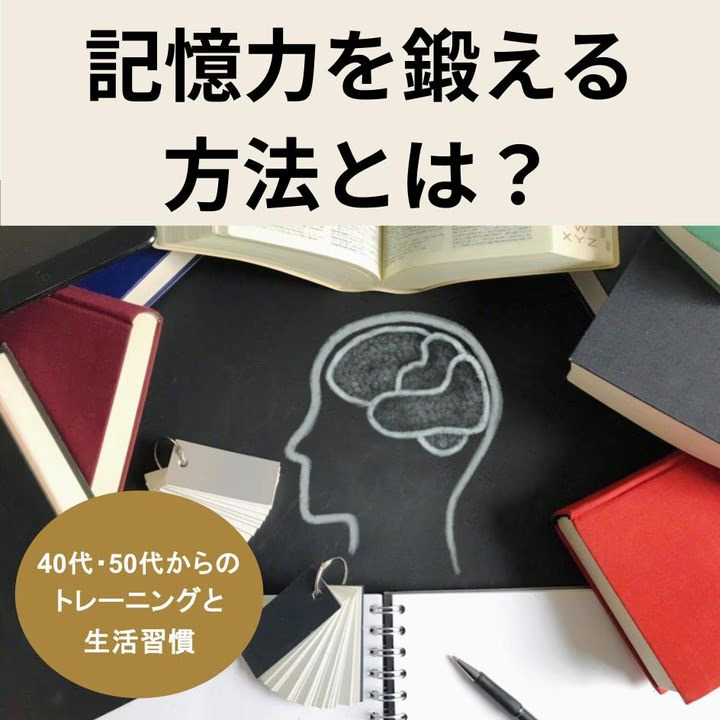
知力健康
記憶力を鍛える方法とは?40代・50代から始めるトレーニングと生活習慣
「最近、物忘れが増えた気がするけれど、何かできることはある?」「年齢のせいだと思う...
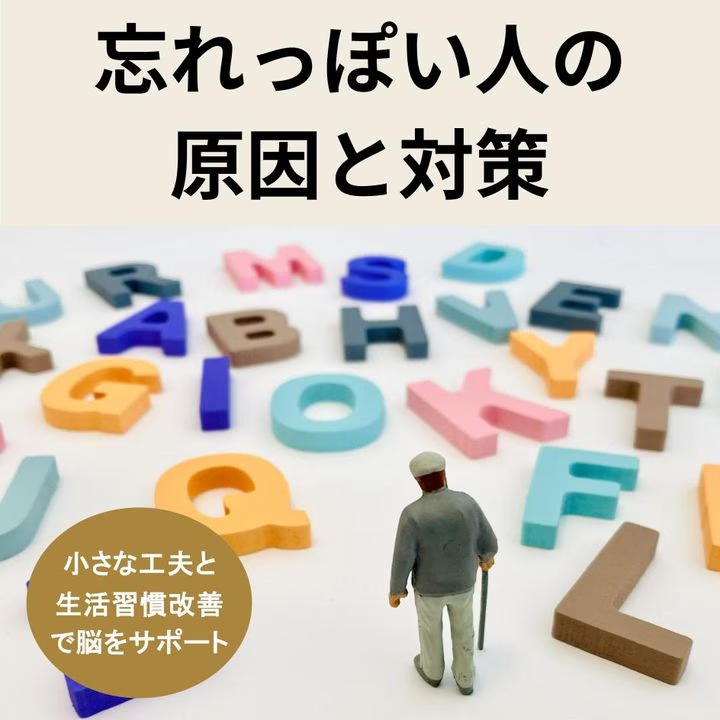
知力健康
忘れっぽい人の原因と対策|小さな工夫と生活習慣改善で脳をサポート
「最近、忘れっぽくなった気がする」「約束や用事をうっかり忘れてしまう。年齢のせい?...









