2026-02-13
記憶障害は認知症の症状の一つ|記憶障害の原因や対策を解説
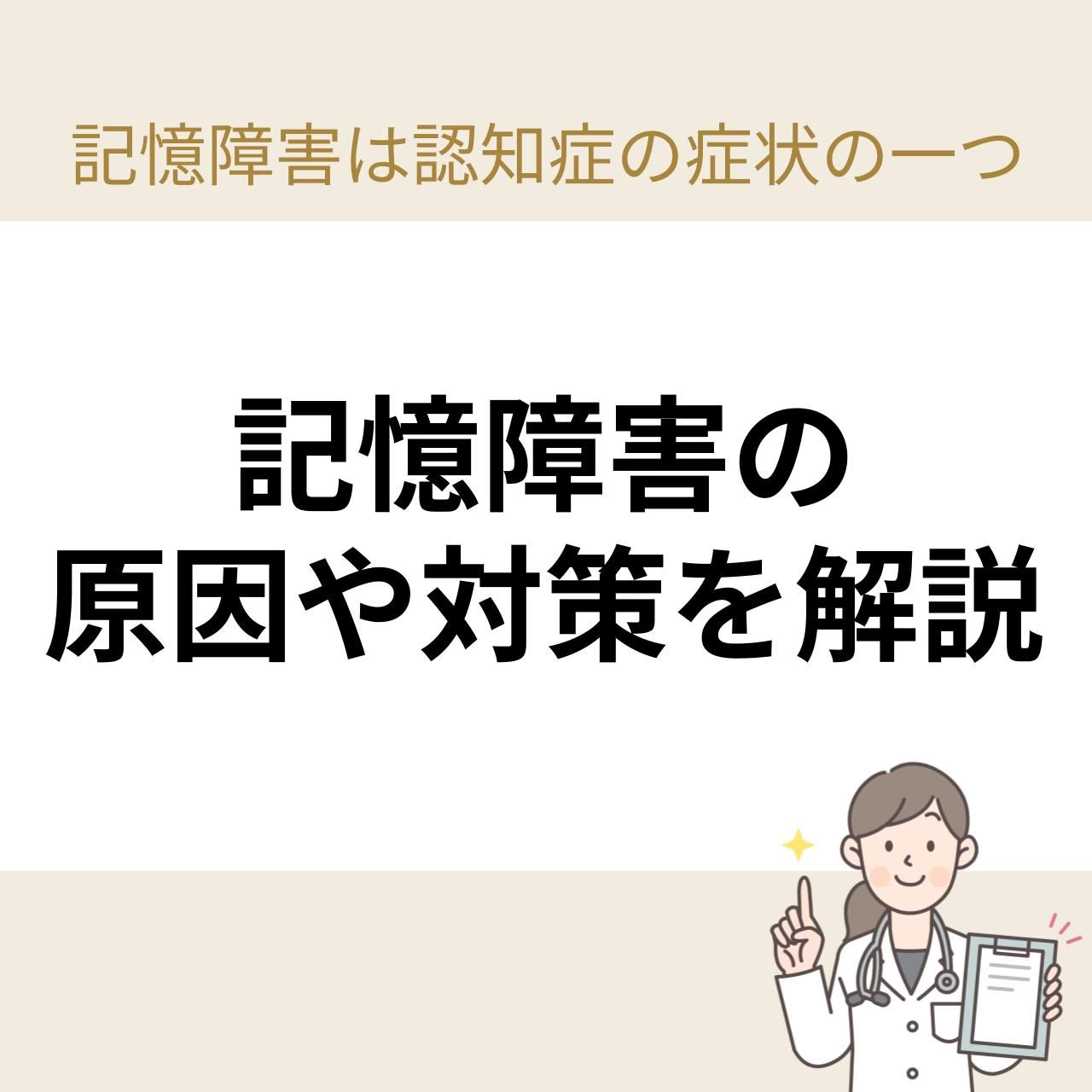
年齢を重ねていくうちに記憶力の低下を実感する方も増えてきます。
記憶力が低下すると、記憶障害あるいは認知症ではないかと不安を抱える方も少なくありません。
記憶障害は放っておくとどんどん進行するため、早めの対策が必要です。
本記事では、記憶障害とは何か、予防する方法はあるのかについて詳しく解説します。日常生活で取り入れられる記憶障害の対策についてもお伝えするため、ぜひ参考にしてみてください。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授
記憶障害とは?記憶の仕組みや物忘れとの違い

記憶障害が何かを知るためには、記憶の仕組みや物忘れとの違いを理解することが必要です。
しかし、記憶の仕組みについてはまだ研究段階であり、大脳辺縁系が関係していることは分かっているもののまだ十分に解明されていません。
ここでは、現在解明されていることを元に記憶障害とは何か、記憶のメカニズムについて詳しく解説します。
記憶障害とは?
記憶障害は脳の機能不全による症状の一つで、情報を覚える、記憶する、思い出すという記憶のメカニズムのいずれかあるいは全てに支障が生じる状態です。
記憶障害を知るためにまずは記憶の仕組みを解説します。
1.記憶の最初の段階である情報を覚えることを記銘といいます。目や耳から入ってきた新しい情報を脳が覚え込むフェーズです。新しく入ってきた情報はこのときに脳の海馬という部分で覚え込まれます。
2.次に記銘で覚えた情報を一定期間覚え続けることを保持といいます。日々の生活の中で脳はたくさんの情報がインプットされていますが、全てを覚え込み続けることは困難です。
そのため記憶の保持のタイミングで、海馬では記銘で入ってきた情報を取捨選択し、自分が生きていく上で必要な情報のみを残し、この情報を大脳皮質という脳の部分に移動させて保存します。
3.大脳皮質で保持した情報を必要なときに取り出す作業を再生といいます。想起・再認とも呼ばれるものです。病気ではなく、加齢によって記憶障害が起こっている場合は、この再生の機能が弱まることで生じていると考えられています。
物忘れとの違い
記憶障害と物忘れの最大の違いは「自覚」があるかどうかです。物忘れの場合は、再生の機能が弱まることで起こるため、何かを経験した事実については覚えています。また、自分がその経験について思い出せないという自覚もあります。
しかし、記憶障害になると多くの場合は、自分が記憶障害になっていることの自覚がなく、経験したことすら覚えていません。
記憶障害なのか物忘れなのかを知りたいという場合には、この自覚の部分にフォーカスを当ててチェックしてみるとよいでしょう。
記憶障害の種類と症状

記憶障害とは一言でいってもいろいろな種類があります。そして種類によって症状が異なるため、記憶障害の種類を知っておくことは非常に重要です。
ここからは、記憶障害の種類を4つ解説します。自分や家族に当てはまる症状がないかどうかをチェックしてみましょう。
短期記憶障害
短期記憶障害とは数十秒から数分といった短い時間に起こった出来事が思い出せなくなる記憶障害です。具体的に短期記憶障害では次の記憶が障害されます。
- 日付
- 時間
- 今日の行動
- 数秒までにしていた行動
短期記憶の保持時間は15秒程度とされていますが、必要と判断された情報は繰り返し覚え込むことで長期記憶へと移行します。
短期記憶障害では、短い間の出来事をすぐに忘れてしまうため長期記憶への移行ができず、何度も同じことを繰り返し聞くという状態に陥るのです。
例えばコンロに火をつけたことを忘れて出かけてしまう、買い物をしたことを忘れてもう一度同じ商品を買ってしまうという状態は短期記憶障害によって起こっているものです。
短期記憶の障害は、海馬の機能が低下しているために起こっていると考えられています。
長期記憶障害
長期記憶障害とは、短期記憶障害とは逆に、数分から数カ月単位の近い過去や年単位で覚えてきた記憶が障害される状態です。睡眠をとって起きた後、あるいは何かに熱中した後でも覚えている情報は長期記憶によって記憶されています。
以下は、長期記憶障害で忘れられる記憶の一例です。
- これまで通った学校
- 会社名
- 職業
- 家族の名前や顔
長期記憶障害では、結婚したことや、会社の人・友人を忘れたりすることがあります。また、話を聞いているときにはすごく理解しているように見えるのに、話した内容を一つも覚えていないというのも長期記憶障害の特徴です。
エピソード記憶障害
エピソード記憶障害とは、自分の過去の経験や体験を忘れる障害です。旅行で起こった出来事や学校・仕事での出来事を忘れるなど、楽しい・辛いにかかわらず思い出を忘れている場合には、エピソード記憶障害に該当します。
エピソード記憶障害は、間脳、内側側頭葉(海馬)、前脳基底部の障害による発生が多く報告されていますが、障害されている部位によって記憶障害の程度も異なります。
例えば、個々の出来事はある程度覚えているけれど時系列が分からない、自分で思い出すことはできないが人からいわれるとなんとなく思い出せるなどです。
意味記憶障害
意味記憶障害とは、いわゆる知識に該当する記憶が思い出せないことをいいます。
数学の公式や歴史の年号、言葉の意味や植物の名前、漢字や語句などを忘れてしまうため、会話が成立しにくく、「あれ」「それ」など指示語での会話が増えるのが特徴です。
ただの物忘れと捉える方もいますが、意味記憶障害も記憶障害の一部なので、軽視せずに対策をすることが重要です。
記憶障害が起こる原因

記憶障害が起こる主な原因には、以下のようなものがあります。
- 加齢
- 軽度認知障害
- 認知症
- 抑うつ
- その他
これらは一つのみでなく、複合的に起こっているため、それぞれの原因について理解をしておくことが重要です。ここでは、記憶障害が起こる原因を詳しく解説します。
加齢
年齢を重ねることで脳の血流や脳の神経細胞機能が衰えるため、その結果として記憶力の低下を引き起こします。
加齢による記憶障害は、基本的に日常生活を送る能力や思考力は維持されるため、日常生活に大きな影響は起こりません。また、何月何日という日時の見当識も残っています。
さらに、加齢による記憶障害の場合は自分に記憶障害があることを自覚しているケースが多く、記憶力が低下していくペースも非常に緩やかな傾向にあります。
軽度認知障害
軽度認知障害は、MCI(Mild Cognitive Impairment)と呼ばれ、約400万人の高齢者がこの状態にあるといわれています。
認知機能は低下するものの日常生活への影響はほとんどないのが特徴です。
軽度認知障害では最近の会話を思い出せなかったり、大事な約束や行事を忘れたりすることがありますが、過去のことは覚えているため、物忘れと捉えられて軽視されることが多いです。
しかし、軽度認知障害の方はそのまま放置すると1年で約5~15%の人が認知症に移行するとされています。
その一方で、1年で約16~41%の人は健常な状態になることも分かっているため、放置せずに対策に講じることが大切です。
参考:国立長寿医療研究センター あたまとからだを元気にするMCIハンドブック
認知症
脳の神経細胞の働きが加齢によって徐々に変化した結果、記憶力や判断力などの認知機能が低下し、社会生活にさまざまな影響を及ぼす状態です。
65歳以上の高齢者の約12%が認知症を発症していると考えられています。
認知症には主に次のような種類があります。
- アルツハイマー型認知症
- 血管性認知症
- レビー小体型認知症
- 前頭側頭型認知症
それぞれの認知症によって症状が異なるのが特徴です。
記憶障害のみの場合もあれば、感情の抑制が効かず人格が変わったり、判断力が低下したり、幻覚や幻聴が出現したりします。
認知症は症状の進行を遅らせることはできますが完治はできません。
- 物忘れがひどくなった
- これまでできていたことができなくなった
- 時間や曜日が分からなくなった
- 物事に対する意欲ややる気が無くなった
といった場合には認知症を疑ってもよいでしょう。
抑うつ
抑うつ状態になると、動作がゆっくりとなったり考えに集中できなくなったりするため、記憶障害が起こることがあります。
抑うつによる記憶障害は記銘に影響を及ぼすことが多く、新しいことを覚えられなくなる傾向にあります。
認知症と似ている状態になるケースもあるため、認知症と混同されやすいです。
しかし、抑うつによる記憶障害では、自分が記憶障害になっていることを自覚しているケースが多くなります。
また、新しいことは覚えられないものの、自分にとって大切な情報については比較的しっかりと覚えている方が多いのも特徴です。
その他
記憶障害の原因としてメジャーではないものの、以下の理由から記憶障害を発症するケースもあります。
- 甲状腺機能低下症
- 正常圧水頭症
- 硬膜下血腫
- ビタミンB12欠乏症
- 異常に長いけいれん発作
- 心停止
- アルコールや薬物の乱用
ほかにも感染症発症後や交通事故にあって頭を強く打った後にも記憶障害を発症することがあります。病気の内容や程度によって記憶障害の程度も異なります。
記憶障害は一般的に治療での完治不可

認知症を原因とする記憶障害は、残念ながら現在の医療をもってしても完治は見込めません。
治療をすることで、記憶障害の進行を緩やかにはできますが、完治させたり進行を防いだりはできません。そのため、記憶障害は一度発症したら生涯付き合っていくことが必要な病気といえます。
ただし、先ほど解説した抑うつ、甲状腺機能低下、ビタミン不足による記憶障害、アルコールの依存症などは、原因となっている病気を治療すれば改善が見込めることもあります。
これらの病気によって記憶障害を発症している可能性が高い方は、一度かかりつけ医に相談しましょう。
記憶障害の対策

認知症を原因とする記憶障害は、治療で根治はできませんが、進行予防は可能です。しかし、治療をするほどの記憶障害なのか悩んでいたり、医療機関に行く余裕がなかったり、本人が記憶障害を認めないから医療機関へ行けなかったりする方もいるかもしれません。
記憶障害は、日常生活の中で対策が可能です。
ここからは、認知症を原因とする記憶障害の対策について解説します。
生活しやすいように環境を整える
記憶障害を発症している方が生活しやすいように環境を整えるだけでも記憶障害の進行予防につながります。
生活しやすい環境を整えるために重要なのが、物理的環境、生活環境、コミュニケーションの環境を整えることです。
- 物理環境を整える場合:収納している場所に何があるのかラベルを貼る、行動の順序をチェックリストにして貼ってできたらチェックを入れる
- 生活環境:毎日同じ生活スタイルを送る、予定の変更を最小限にとどめる
- コミュニケーションの環境:自分のことを説明してから話しかける、大切なことは繰り返し伝える、説明をしながら紙にも書く
また、新しいことに挑戦し知的好奇心を刺激したり、手指を動かして神経やシナプスのつながりを強化したりするのも効果的であると考えられています。
生活習慣を整える
生活習慣を整えることは、現在因果関係は不明とされているものの記憶障害の対策において効果的であることが分かっています。
早寝早起きをする、食事を3食摂る、適度な運動をするなど、規則正しい生活を送りましょう。
血圧、コレステロール値、血糖値のコントロールと一緒に行い、心血管障害を予防することで認知症発症を防ぐことにもつながります。
サプリメントを活用する
記憶障害の予防のためには、サプリメントを活用することも効果的と考えられています。
記憶力維持には、EPAやDHAなどのオメガ3脂肪酸、葉酸、ビタミンA、C、E、ミネラル、レチシンなどの成分が効果的です。
これらの栄養は、食べ物から毎食しっかりと摂ることが理想的です。しかし、日常生活の中で毎日これらの栄養を含み、バランスの整った食事をすることは非常に難しいといえます。
そのため、不足しがちな栄養をサプリメントで補うことで、記憶障害の予防へつながるとされているのです。
記憶力維持をサポート!おすすめサプリ「Rimenba」

サプリメントを活用して記憶障害の予防を検討しているが、どのようなサプリメントを選べばよいか分からないという方に活用いただきたいのが、Rimenbaです。
Rimenbaは20種類以上の栄養素を配合したオールインワンサプリメントです。1日4粒の服用で知力健康へアプローチが可能で、食事のみでは不足しがちな栄養素を補えます。
また、完全無添加な上に、国内有数のGMP認定工場で製造しており、医師監修であるため、サプリメントに安心感を求める方にもおすすめです。
累計出荷数が720,000食を突破し、多くの方にご利用いただいております。
サプリメントを活用して記憶力をサポートしよう

記憶障害にはさまざまな種類、原因がありますが、一部の病気によって起こった記憶障害以外は、医療の力をもってしても完治は見込めません。
また、記憶障害と物忘れは異なるため、物忘れなのか記憶障害なのかを適切に判断することも重要です。記憶障害かもしれないと考えたら、早めに日常生活でできる対策を始めましょう。
20種類以上の栄養素を含んだRimenbaは、知力健康をサポートするオールインワンサプリです。
記憶障害かどうか気になる、自宅での予防から始めたいという方は、多くの方にご利用いただいているRimenbaをぜひご活用ください。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授
【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。
あなたへのおすすめ
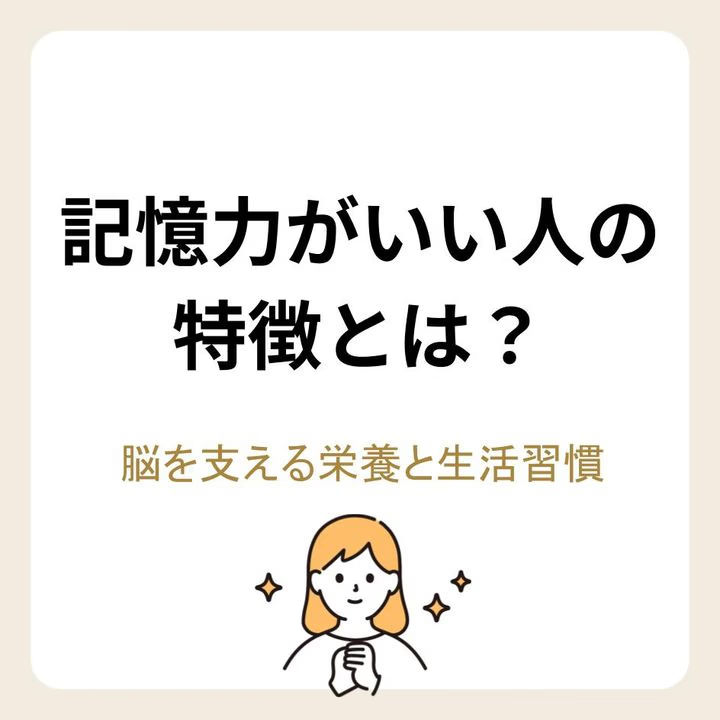
知力健康
記憶力がいい人の特徴とは?脳を支える栄養と生活習慣
「記憶力がいい人は生まれつき」と思っていませんか。しかし記憶力は、脳の使い方や日々...
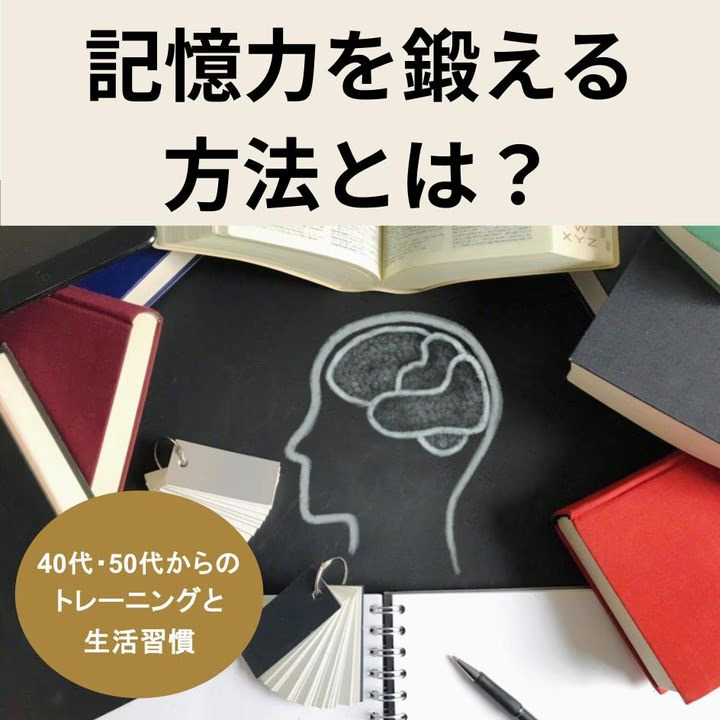
知力健康
記憶力を鍛える方法とは?40代・50代から始めるトレーニングと生活習慣
「最近、物忘れが増えた気がするけれど、何かできることはある?」「年齢のせいだと思う...
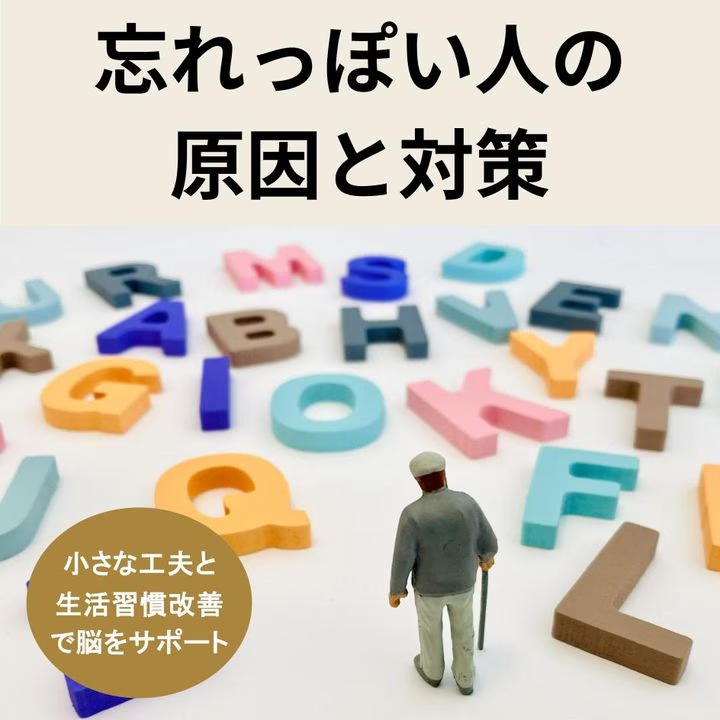
知力健康
忘れっぽい人の原因と対策|小さな工夫と生活習慣改善で脳をサポート
「最近、忘れっぽくなった気がする」「約束や用事をうっかり忘れてしまう。年齢のせい?...








