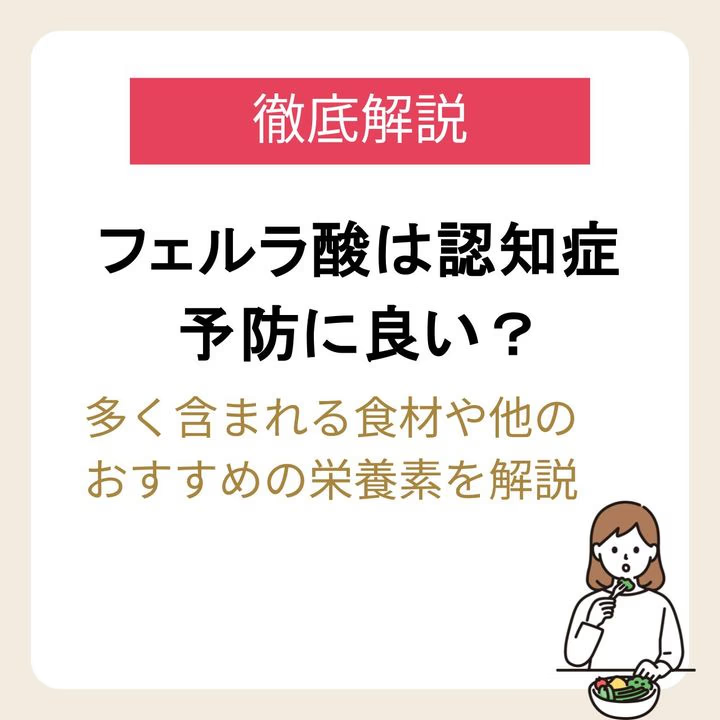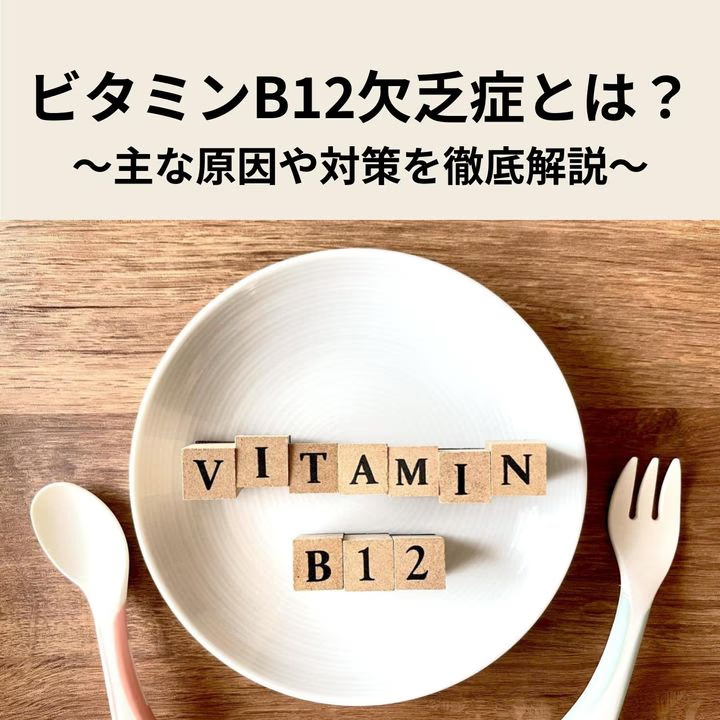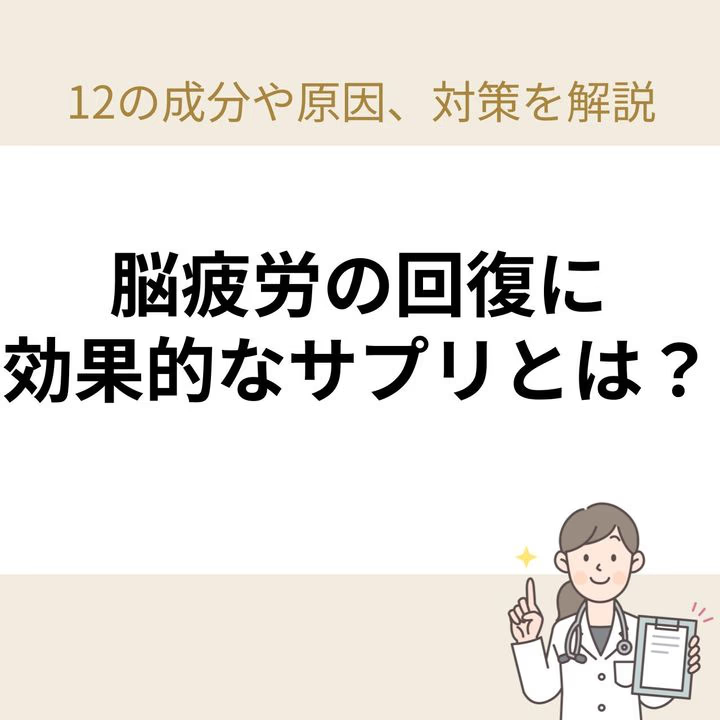2025-05-21
ビタミンB12欠乏症とは?認知症にもつながる?主な原因や対策を徹底解説
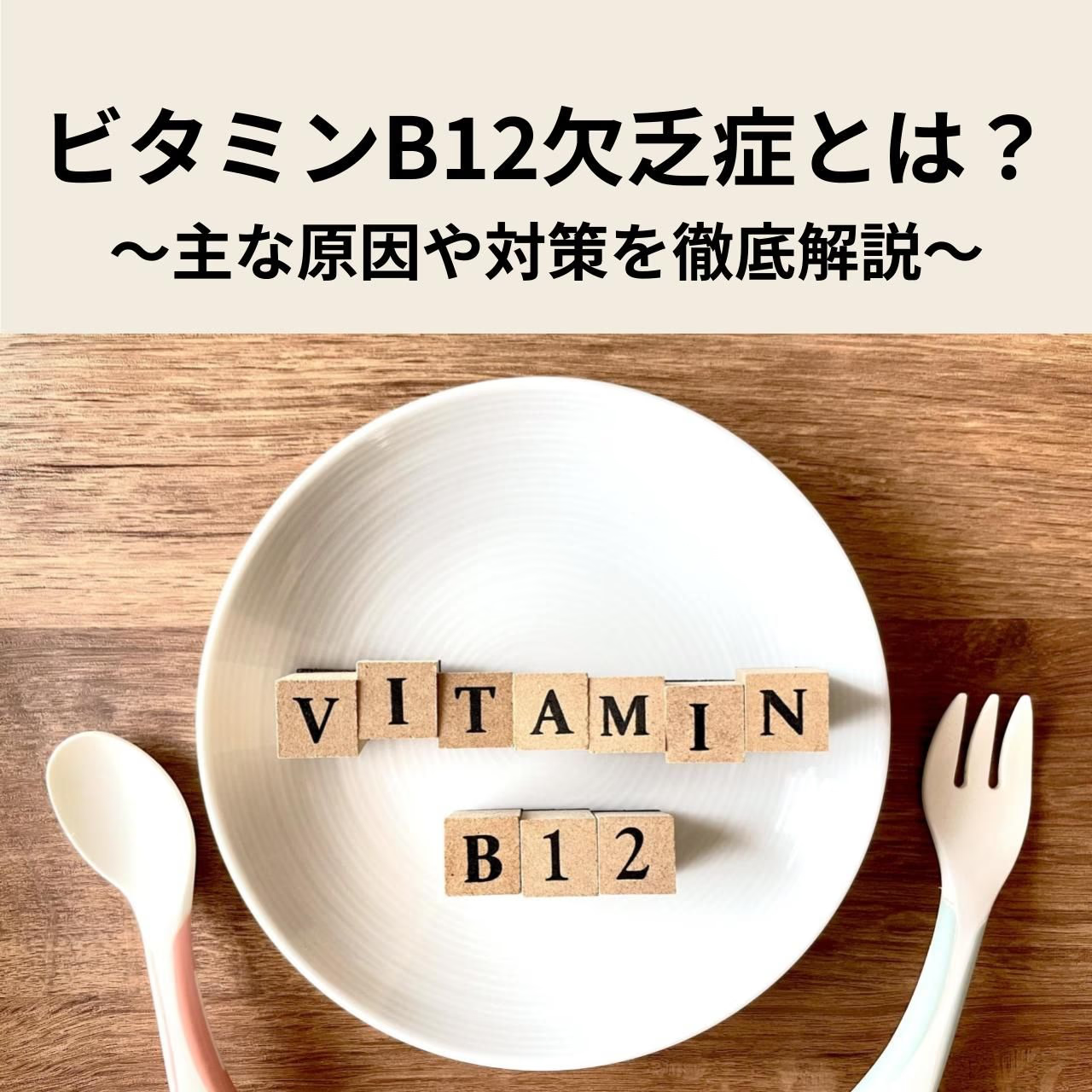
年齢を重ねると、「最近物忘れが増えた」「以前より疲れやすい」と感じることがあるかもしれません。それを単なる加齢の影響だと見過ごしてしまうと、思わぬ健康リスクを抱えるおそれがあります。
実は、神経や血液の働きを支えるビタミンB12が不足することで、集中力や記憶力の低下、さらには認知症に似た症状が現れることもあるのです。
そこで今回は、ビタミンB12欠乏症の原因や症状、予防法や対処法について詳しく解説します。今感じている不調の背景を理解し、健康な毎日を取り戻すための手がかりとしてご活用ください。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授

Webライター
岩城 裕大
認知症にもつながる?ビタミンB12欠乏症とは

ビタミンB12は、神経の働きや赤血球の生成を支える栄養素です。細胞内でのDNA合成やエネルギー代謝にも関与し、私たちの体調維持に欠かせない存在といえるでしょう。
このビタミンが不足すると、末梢神経に障害が生じて手足の痺れが出るほか、巨赤芽球性貧血と呼ばれる血液の異常を引き起こす可能性があります。
そのまま放置すれば、記憶力や集中力が衰え、やがて認知症につながる危険性も否定できません。加齢や胃腸の疾患、菜食中心の生活などが影響し、食事や吸収の面で問題を抱えていると、欠乏症の発症リスクが高まります。
ビタミンB12欠乏症の主な原因
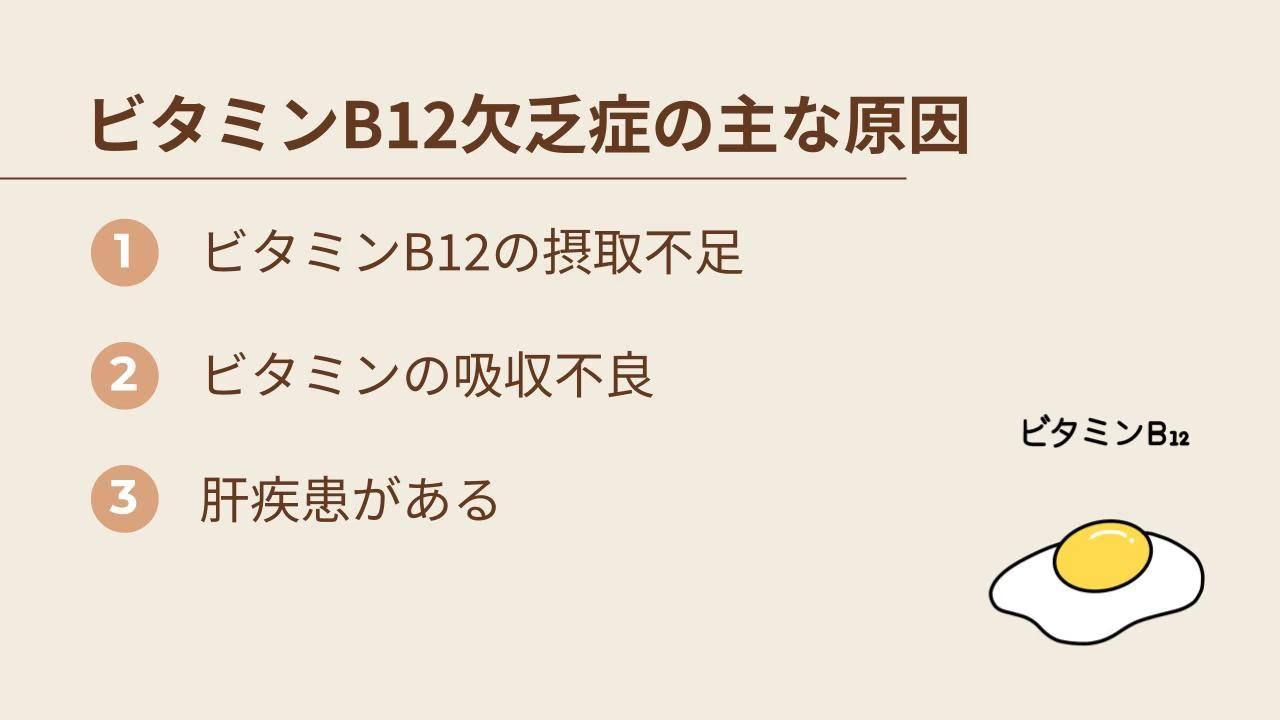
ビタミンB12が不足する原因は一つではなく、日々の食生活や体の状態によってさまざまな要因が関係しています。特に40代以降は、吸収機能や内臓の働きが徐々に衰えることで欠乏リスクが高まりやすくなるといわれています。
ここでは、ビタミンB12欠乏症を引き起こすといわれている代表的な3つの原因を見ていきましょう。
ビタミンB12の摂取不足
ビタミンB12は肉や魚、卵、乳製品などの動物性食品に豊富で、植物性食品にはごくわずかしか含まれていません。そのため、動物性食品を避ける食習慣では、慢性的に不足しやすくなります。
特に完全菜食主義を実践している方は、注意が必要です。さらに、授乳中の母親がビタミンB12を十分に摂っていない場合、母乳を通じて乳児の神経発達にも悪影響が及ぶ可能性があります。家族の健康を守るためにも、日々の食生活を見直し、必要に応じてサプリメントなどを活用することが大切です。
ビタミンの吸収不良
ビタミンB12は、摂取しても体内でうまく吸収されない場合があります。特に吸収には「内因子」と呼ばれる、胃から分泌されるたんぱく質が欠かせません。この内因子が不足すると、ビタミンB12は小腸で吸収されず、そのまま体外へ排出されてしまいます。
高齢者では胃酸の分泌量が減少しやすく、それに伴い内因子の分泌も低下する傾向があります。また、胃の手術歴がある方や小腸の疾患がある方に加え、制酸薬や糖尿病治療薬を服用している場合にも、吸収障害が起こることがあるのです。
こうした吸収不良が続くと、サプリメントを摂っても期待どおりの効果が得られないケースもあるため、必要に応じて医師の診察を受けることが望ましいでしょう。
肝疾患がある
ビタミンB12は、体内に取り込まれた後、主に肝臓に蓄えられ必要に応じて放出される仕組みになっています。しかし、慢性の肝疾患がある場合、貯蔵が妨げられ、体内のビタミンB12濃度が不安定になることがあります。そのため、食事から十分に摂取していても、欠乏症を招くケースが見られます。
特に肝機能が低下している方では、他の栄養素も含めた全体的な栄養管理が重要です。慢性肝炎や脂肪肝、肝硬変などの既往がある場合は、B12の蓄積機能が弱まっている可能性があるため、定期的な血液検査や専門的な栄養指導を受けることが推奨されます。
ビタミンB12欠乏症の主な症状
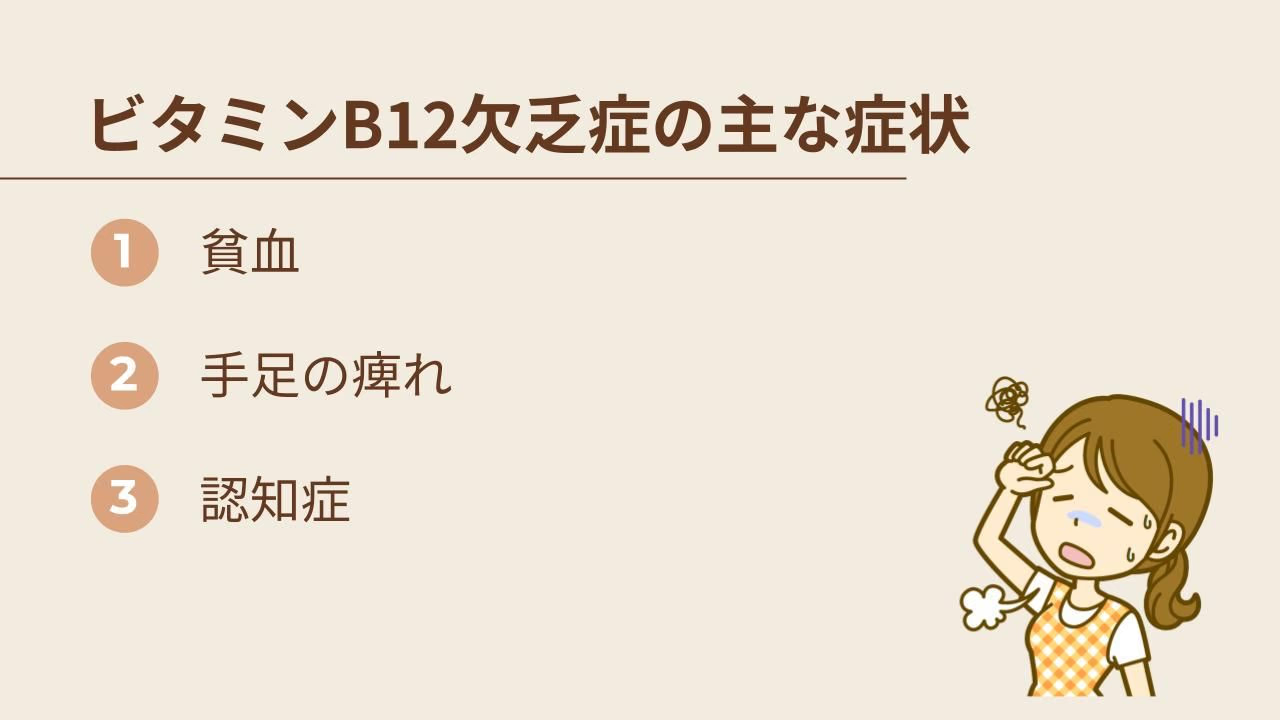
ビタミンB12が不足すると、体内のさまざまな機能に影響を及ぼし、日常生活に支障をきたす症状が現れます。特に40代以降では、原因がわからないまま「年齢のせい」と見過ごされることも少なくありません。
ここでは、見逃せない3つの代表的な症状について詳しく解説します。
貧血
ビタミンB12が不足すると、赤血球が正常に形成されず、大きく未熟な赤血球が増える「巨赤芽球性貧血」が起こることがあります。この貧血では酸素を全身に運ぶ能力が落ちるため、疲れやすくなったり、立ちくらみや息切れなどの症状が現れたりします。舌や粘膜が白っぽく見えることもあり、そうした見た目の変化が異常に気づく手がかりになるでしょう。
加齢や胃腸機能の低下、栄養の偏りがある場合、知らぬ間に貧血が進んでいることも考えられます。早期に気づくには、定期的な血液検査や日々の食生活の見直しを通じて、体調の変化を意識することが大切です。
手足の痺れ
ビタミンB12が欠乏すると、神経細胞の働きが低下し、末梢神経に障害が生じることがあります。その影響で、手足にピリピリとした痺れや感覚の鈍さが現れ、ひどい場合には物がつかみにくくなったり、足がもつれるといった筋力低下が起こることもあります。
症状が進むと、歩行時のバランスを保ちにくくなり、日常生活に支障をきたすおそれもあるため注意が必要です。少しでも異変を感じたら早めに医療機関で検査を受けましょう。
認知症
ビタミンB12が不足すると、神経細胞の働きに支障をきたし、記憶力や注意力の低下、思考の緩慢化など、認知症に類似した症状が現れることがあります。特に高齢者では、胃酸の分泌量が減少することで吸収が悪くなり、自覚のないまま進行するケースも少なくありません。
症状が進行すると、錯乱やせん妄、幻覚、妄想といった精神的な変化に加えて、歩行のふらつきや筋力の低下など、身体面にも影響が及ぶことがあります。
ビタミンB12欠乏症になりやすい人の特徴
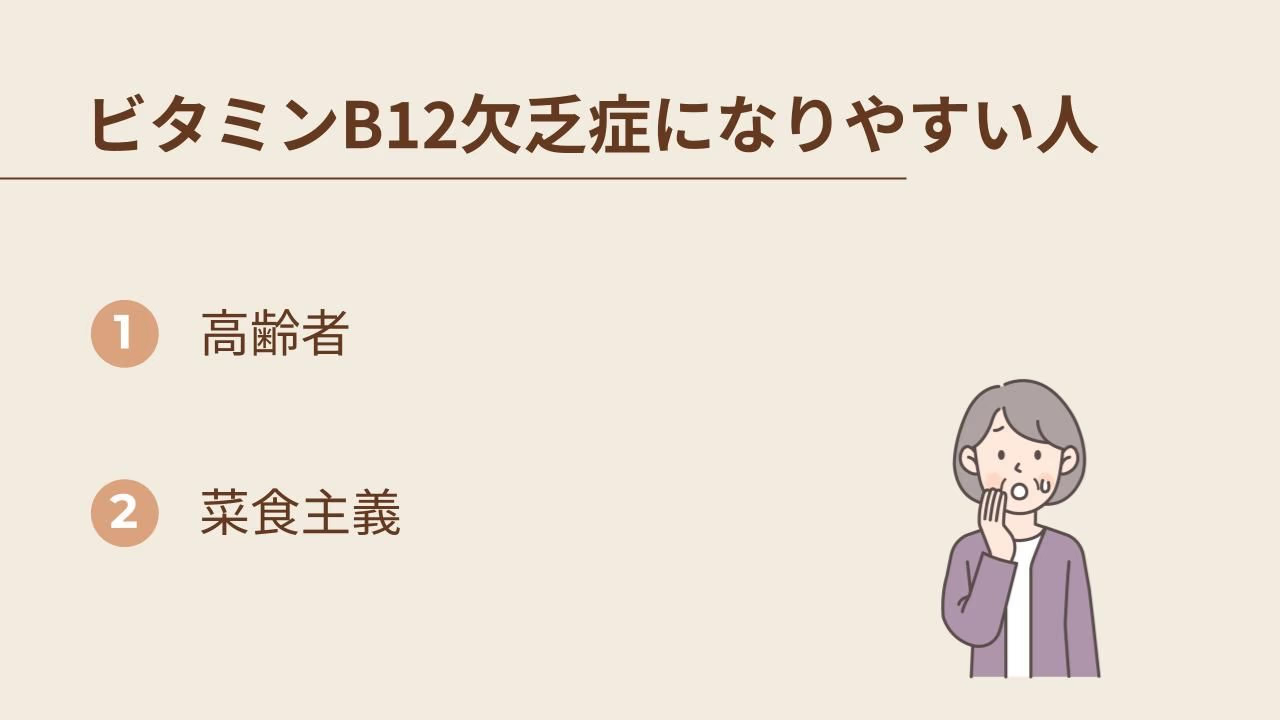
ビタミンB12欠乏症は、誰にでも起こり得るものですが、特に注意が必要な人には一定の共通点があります。ここでは、欠乏リスクが高いとされる人の特徴を紹介します。
高齢者
高齢になると胃酸の分泌が減少し、ビタミンB12の吸収効率も下がりやすくなります。B12の吸収には「内因子」と呼ばれる胃のたんぱく質が必要ですが、高齢者ではこの分泌も低下しやすく、食事からの補給だけでは足りない場合があるためです。
その影響で、貧血や手足の痺れのほか、認知症に近い症状が出る可能性も否めません。特に認知機能の衰えは加齢のせいと考えられがちですが、実際には栄養不足が原因となっていることもあります。
健康的な高齢期を維持するには、栄養状態の見直しとともに定期的な血液検査が効果的です。必要に応じてサプリメントを取り入れることも検討するとよいでしょう。
菜食主義
菜食主義者もビタミンB12が欠乏しやすい傾向があります。B12は肉や魚、卵、乳製品といった動物性食品に多く含まれており、植物性食品からはほとんど摂取できないためです。特に完全菜食主義(ヴィーガン)を実践している方は、気づかないうちに慢性的なB12不足に陥っている可能性もあります。
こうしたリスクを避けるためには、普段から栄養バランスを意識し、必要に応じてビタミンB12を含むサプリメントで補うなどの工夫が必要です。特に40代以降は吸収率の低下も重なるため、体調や食生活を見直す機会を意識的に持ちましょう。
ビタミンB12欠乏症による認知症への対策

ビタミンB12の欠乏によって認知症に似た症状が見られる場合は、まず栄養状態の確認と早期の対策が欠かせません。
特にレバーや魚介類にはビタミンB12が豊富に含まれているため、日々の食事に取り入れてみましょう。さらに、肉類もバランスよく摂ることで、ビタミンB1や亜鉛など他の栄養素の不足も防げます。
ただし、加齢や体調不良によって食事だけでは必要量を補いきれないこともあるため、その場合は葉酸やビタミンB群を一度に摂取できるサプリメントの活用がおすすめです。
日々の食生活を見直し、体の内側から認知機能を支える意識が、将来の安心につながるでしょう。
ビタミンB12欠乏症による認知症が気になる方におすすめのサプリメント「Rimenba」

ビタミンB12が不足すると、記憶力や集中力の低下に加え、認知症に似た症状を引き起こすことがあります。本来は食事からの摂取が理想ですが、加齢や多忙な生活によって十分に補えないことも少なくありません。
そうした場面で活用できるのが、必要な栄養素を手軽に摂取できるサプリメントです。例えば「Rimenba」はビタミンB12に加え、DHA・EPAや葉酸なども一度に摂れるオールインワン設計となっており、知力健康を支える20種類以上の栄養素をバランスよく補給できます。
また、脳神経内科の専門医が監修に関わり、GMP認定を受けた国内工場で製造されているのも特徴です。小粒のソフトカプセルのため毎日続けやすく、将来のリスクに備えたい40代以降の方にもおすすめ。初回購入はお得なキャンペーンが利用できるほか、15日間の返金保証もあるので、まずはお気軽にお試しください。
この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授
濱野 忠則
- 脳神経内科長
- 診療教授
【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター
岩城 裕大
SEO会社勤務を経て独立したWebライター。これまでに子育て・エンジニア・物流・EC運営など幅広いジャンルで、記事構成・執筆・運用を累計200本以上担当。実務に基づく確かな視点で、信頼性の高いコンテンツを届けることを大切にしています。